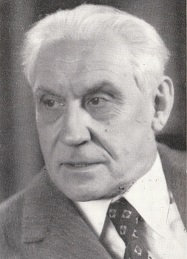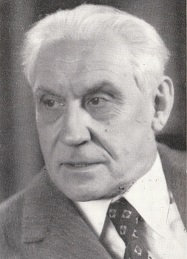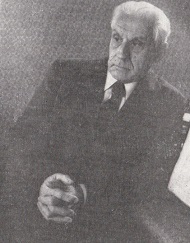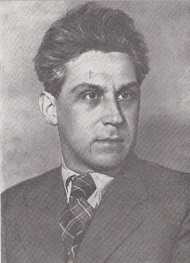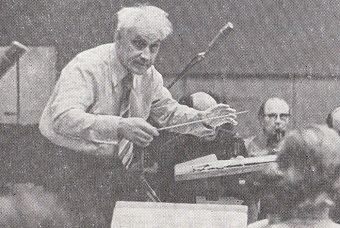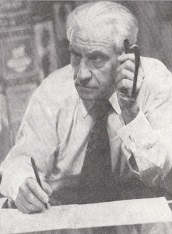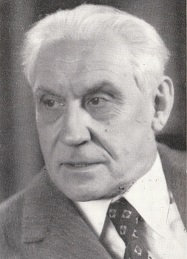 Nikolai Rakov
Russia
(1908 - 1990)
Nikolai Rakov
Russia
(1908 - 1990)
日本語表記: ニコライ・ペトロヴィチ・ラコフ
英語表記: Nikolai Petrovich Rakov
露語表記: Раков, Николай Петрович
英語等別表記:
(名) Nikolaj, Nicolas, Mykola (姓) Rakof, Rakow (*cA01)
日本語別表記: ニコライ・ラーコフ ニコライ・ペトロヴィッチ・ラーコフ
生没年月日: 1908年3月14日 ~ 1990年11月3日 (82歳)
---------------------------------------
◆ 略 歴
1908 モスクワの南西 200kmの都市 カルーガ(Kaluga)で商人の家の末っ子として生まれる.
1915 ピアノを習い始める.
1917 ヴァイオリンに転向する.
1920-24 ルビンシュタイン音楽学校でヴァイオリンを師事.
1920-24 ヴァイオリニスト 兼 ピアニストとしてカルーガ市交響楽団で演奏.
1922 モスクワ音楽院に入学. (ただし住む場所を確保できなかったため1か月で帰郷する)
以後 プライベートレッスンという形でダビッド・クレイン(D.Krein)にヴァイオリンを師事.
1924-30 ルービンシュタイン音楽大学(現 モスクワ音楽院附属アカデミック・ミュージック・カレッジ)でアニシム・ベルリン(A.Berlin)にヴァイオリンを師事.
1926-31 モスクワ音楽院でレインゴリト・グリエール(R.Glière)やセルゲイ・ヴァシレンコ(S.Vasilenko)に作曲法を師事.
1932- モスクワ音楽院で恩師 グリエールの助手として勤め始める.
1935- モスクワ音楽院の講師として自分のクラスを持つようになる.
1943- モスクワ音楽院楽器法教授に就任. 楽器法に関する著作あり.
1946 ヴァイオリン協奏曲第1番(1944)の功績を称えられスターリン賞受賞.
1949- 指揮者としての活動を始める. 自作や古典音楽を得意とする.
1966 ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国名誉芸術家(功労芸術家)の称号に輝く.
1975 ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国人民芸術家の称号に輝く.
1988 ソビエト連邦人民芸術家の称号に輝く.
1990 モスクワにて死去. ドンスコイ墓地に埋葬. 音楽院では亡くなるまでの58年間, 後進の指導にあたった.
◆ 出 自 ・ 人 柄
・同じ1908年生まれのニコライ・ラコフ(Nikolai Pavlovich Rakov, 1908-1978)というグレコローマンスタイルのレスリング選手がいるが,
同姓同名というだけで特に接点はない.
・ラコフの家は商人の家系であり, とりわけ父 ピョートルの代で大きな財を成した.
彼は当時のカルーガ市でちょっとした有名人であり, 実家の商店を市内一二を争う規模にまで発展させた.
・ピョートルは市内に複数の不動産を有し, 帝政ロシアの様式を多分に含んだ邸宅があったと伝えられている.
ただし, そのほとんどは(1棟を除いて)現存してはいない.
(ラコフの家に関しての記述は多少長くなるため, 折り畳んでおきます)
[+]
世界一の面積 17,124,442㎢(日本の面積の45倍)を誇るロシアにおいて,
道路の総延長は(「何を"道路"とするのか」という定義によってその距離は変わるものであるが) 98万km【世界の統計2012】に及ぶ.
そしてロシア全土の各地では, 偉人の名を冠した通り(*cA02)を目にすることがよくある.
中でもその街の中心的な大通り(目抜き通り)には, ロシア革命からソ連黎明期を率いた指導者 レーニン(Vladimir Lenin, 1870-1924)の名前を讃えた
「レーニン通り」なるものが見受けられる.
そんな カルーガ市のレーニン通り(*cA03)とキーロフ通り(*cA04)の交差点に面した角地にラコフの家があった.
この邸宅はニコライの生まれた1908年に起工し, 1911年に完成(*cA05)された.
 Rakov's house (early 20c.)
玄関に「П.С.РАКОВ」(P.S.Rakov)の表札が掲げられている
Rakov's house (early 20c.)
玄関に「П.С.РАКОВ」(P.S.Rakov)の表札が掲げられている
新居が建ったこの立地であるが, ニコライの父 ピョートルが土地を取得した時点では小さな庭のある2階建ての邸宅が建っていた.
この住居は1787年に有力商人 シェミヤキンが建て, 以後何度かその所有者を変えてきた.
 Shemiyakin's house [former-Rakov's house] (19c.)
Shemiyakin's house [former-Rakov's house] (19c.)
1794年にはカルーガ県(*cA07)の副知事を務めた フョードル・プーシキン(Fyodor Alexseevich Pushkin, 1752-1810)(*cA08)の手に渡る.
その後, 州検察官 アレクサンドル・ステパノフなど何人かの手に渡ったのち, おそらく19世紀末頃にピョートル・ラコフが所有するに至った.
すでに築 100年が経過し, 屋敷は荒れ始めていた.
 |
 |
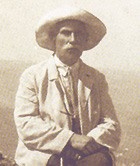 |
Fyodor Pushkin
(1752-1810) |
Alexei Pushkin
(1771-1825) |
Pyotr Rakov
(1868-1944) |
ピョートルは1894年に始めた貿易商の仕事が軌道に乗り, 19世紀終わりごろにはかなり裕福であったとされる.
すでにいくつかの不動産を有し, 住居に困っていなかった彼の新居の取得は, ニコライの誕生と不可分(*cA09)だったと思われる.
当時の実家はオブルプスカヤ通り(現在のテアトルナヤ通り(*cA10))9番地(*cA11), 『自転車を引くツィオルコフスキー像(2011年建立)(*cA12)』のすぐそばにあったとされる.
石造りの基礎に木造のアーチと装飾が施された柱が特徴的な, 帝国様式で建てられていたが, これは現存していない.
アール・ヌーヴォー様式が美しい1911年の「ラコフの家」は, 地元の建築家 ヴァシリ・ヴィノグラドフ(Vasiliy Dmitrievich Vinogradov)(*cA13)による設計で,
90度に直交しないレーニン通りとキーロフ通りに対して, 正面玄関をその角方向に設えることで通りに溶け込むようデザインされている.
天井の高い1階は商店『子どもの世界』が入り, ラコフの家族は2階のフロアを居住用として利用していた.
ラコフの商店は大きく明るい間取りで天井が高く, 清潔で愛想のよい店員が出迎え, 中央には金魚の泳ぐ大きなアクアリウムがあった.
また当時としてはかなり珍しかった電話が引かれており, 「1-25」の番号が与えられていた.
カルーガ市民はこの心躍るデパートを親しみを込めて『Ракушка(ラクシュカ)(*cA14)』と呼び, 彼の店での買い物を遠足に行くかの如く楽しみにしていた.
順風満帆に思えた新居での生活だったが, 1917年にロシア革命が勃発.
政治体制が大きく変わることとなり, 共産主義化が加速. 一部の企業や施設の国有化も行われるようになった.
1階を 経営する商店『子どもの世界』の売り場, 2階を居住用スペースとしていた一家の大黒柱 ピョートルは,
建物に関する権利を自発的に政府へと譲渡し, 自身は商店の売り子として働き続ける道を選択した.
(その方が建物や自分・家族にとってより安全だと考えたのかもしれない)
党員だったか定かではないが, 無欲で献身的で, また党に協力的であった ピョートル.
しかしながら, 1932年にはアルハンゲリスクへ移住するよう政府から強いられてしまう.
建物自体が市の中心部に近く, 市民の憩いの場でもあったラコフの家は, もともと2階 ないし 3階に談話室のようなスペースがあった.
そこで市職員や市議会議員が会談を行うこともあったらしい.
建物の権利が譲渡されたのちの1918年~1930年, および 大祖国戦争(1941~1945年)の間, この2階にはカルーガ市議会が設置されていた.
また, 1937年にはソビエト連邦共産党がこの2階を使っていた記録もある.
戦後, 2階は当局が占有していたものの, 1階は戦前と変わらず『子どもの世界』がカルーガ市民を出迎えていた. (ただし, この頃はすでにラコフ家の手を離れている)
店の建物の前では交通制御のための信号機を操作する交通警察ブースが建てられたり, 店先をトロリーバスが運行したり,
大きな交差点を臨むこの店の前はとかく賑やかで騒がしく, 活気にあふれていた.
 |
 |
| (1949) |
(1956) |
1978年, 商業施設の再編と区画の見直しが行われ, デパートは200人のスタッフを抱えるおもちゃ屋さんへと成長した.
同年, キーロフ通りの一角をデパートに拡張する計画や, 1986年にカルーガ百貨店の機能を移転する計画が持ち上がったものの,
これらは実現しなかった.
 |
 |
| (1960s) |
(1982) |
2000年6月, 1階にギフトショップ『オストロフ・ソクロヴィシ(Остров Сокровищ)』がオープン.
インテリア雑貨などを販売するお店として, 現在もこの地で営業しています.
オストロフ・ソクロヴィシはロシア語で「宝島」という意味.
幼いニコライ・ラコフが暮らしたこの家は, 今もカルーガ市の財産としてこうして佇んでいます.
参考:ロシアの道路の種類と名称 [ロシア・ビヨンド]
参考:ロシアからレーニン像がなくならない理由 [朝日新聞GLOBE+]
参考:Kaluga: foto programmer [LiveJournal]
参考:我が街カルーガの豪商とその運命 (ロシア語) [KP40.RU]
参考:ニコライ・ラコフ (ロシア語) [カルーガ市交響管弦楽団]
参考:オールド・カルーガ - ラコフの家, 市議会, 「宝島」 (ロシア語) [Kaluga24.tv]
・演奏会に際して, 10代~20代の頃はヴァイオリンやピアノの演奏家として活動していたが, 40歳を前後する頃から指揮活動に軸足を移した.
それは彼なりの哲学があったようで, 首都 モスクワで演奏活動をしなくなった彼に対し 友人が不満を漏らしたところ, 次のように答えたという.
『モスクワには指揮者はたくさんいるし, 楽団もある. でも地方では交響楽団がないこともあるし, いたとしても恒常的に人員不足だったりする.
そんな地方に生演奏の良さと世界には素晴らしい音楽があるということを届けたいんだ』
事実 彼は数十におよぶ地方都市や連邦共和国に足を運び, ベートーヴェンの『エグモント』やワーグナーのオペラといったさまざまな国・時代の音楽を指揮していた.
・正規の音楽学校での教育に加えて, アマチュアのワーキンググループに講師として通うなど幼少期の音楽教育指導に注力していた. それは
『国の音楽文化を未来へと発展させていくのは若い世代であるが, 若い才能にとって新しいものを生み出すためには長い期間かけて醸成された(先達の)知識が不可欠である』
といった彼の考えに基づいている.
◆ 交 友
* 女性名のうち, 結婚後の姓(現姓)と旧姓を併記する場合 [名前・父称・現姓 - 旧姓] という形に統一します.
* 家族 *
・[p] ピョートル・ステパノヴィチ・ラコフ (Pyotr Stepanovich Rakov, 1868-1944/1869-1943):
ニコライの父親. 商人.
地元 カルーガで商店を営んでいた両親を幼いころから手伝っていた.
公立学校卒業後はロシア帝国軍に従軍. 帰郷後は同業の商人仲間の娘 ナジェージダ・ザヴェーリナと結婚する.
実直で奉仕精神の強い人物で, 1911年に新築したばかりの立派な邸宅を1917年のロシア革命後, 自発的に政府に譲渡.
自分のお店で働く従業員を大切にしたり, カルーガ市民のために無料の図書館を開設したりするなど, 地元では非常に尊敬された人物だった.
1932年, 白海にほど近いロシア北西部の港湾都市 アルハンゲリスクに移住させられ, 1944年 同地で亡くなった.
・[p] ナジェージダ・ヴァシリェヴナ・ラコワ=ザヴェリナ) (Nadezhda Vasilievna Rakova-Zaverina, 1869-1958):
ニコライの母親.
地元 カルーガの有力穀倉商人 ワシーリー・ザヴェーリンの娘.
余談になるが, ナジェージダの兄 ニコライ・ザヴェーリン(1866-?)は夫 ピョートル・ラコフの姪 アレクサンドラ・ラコワ(1870-?)と結婚しており,
ラコフ家とザヴェーリン家の縁談は少なくとも2件(ピョートル・ラコフとナジェージダ・ザヴェーリナ / アレクサンドラ・ラコワとニコライ・ザヴェーリン)あることが確認できる.
アレクサンドラはピョートルの兄 アレクセイ(?-?)の子で, 姪といってもピョートルと2歳しか差がない.
2組の婚姻についてどちらが先か決定づける資料は今のところ見受けられないが, それぞれの長子が ヴァーヴァラ(1894-1969)とヴィクトル(1896-1943)であることを鑑みると
ピョートル&ナジェージダの方が先であるように思える.
・ リディヤ・アントナヴナ・ラコワ=スロボジョノク (Lydiya Antonovna Rakova-Slobodzionok, 1902-1981):
ニコライの妻. 職業 バレリーナ.
あまり詳しいことはわかっていませんが, 姉さん女房だったんですね…
+(2親等以上の親族)
・ ヴァーヴァラ・ペトロヴナ・ラコワ (Varvara Petrovna Rakova, 1894-1969):
ニコライの長姉.
・ ウラジーミル・ペトロヴィチ・ラコフ (Vladimir Petrovich Rakov, 1897-1942):
ニコライの長兄.
・ ジナイダ・ペトロヴナ・ロボワ=ラコワ (Zinaida Petrovna Lobova-Rakova, 1899-1984):
ニコライの次姉. ボリス・ロボフ (Boris Yakovlevich Lobov, 1884-1951)と結婚し, 2児を儲ける.
・ ソフィヤ・ペトロヴナ・クブラノワ=ラコワ (Sofiya Petrovna Kubranova-Rakova, 1901-1970):
ニコライの姉. …上から三番目の姉を表す日本語ってあるんですかね。。
ニコライ・クブラノフ (Nikolai Fyodorovich Kubranov, 1882-1953)と結婚し, 娘を儲ける.
・ ステパン・ミハイロヴィチ・ラコフ (Stepan Mikhailovich Rakov, ?-?): ニコライの父方の祖父(ピョートルの父).
・ エリザヴェータ・アンドリェエヴナ・ラコワ (Elizaveta Andreevna Rakova, ?-?): ニコライの父方の祖母(ピョートルの母).
カルーガ市内(当時の自宅はオブルプスカヤ通りに存在した)で小規模の商店を営んでいた.
ニコライの実父 ピョートルを含め, 8人の子を生した.
・[p] ワシーリー・マクシモヴィチ・ザヴェーリン (Vasiliy Maximovich Zaverin, 1846-1908): ニコライの母方の祖父(ナジェージダの父).
・ グラフィラ・ギリゴリェヴナ・ザヴェーリナ=ドルゴワ (Glafira Grigorievna Zaverina-Dolgova, 1842-1908): ニコライの母方の祖母(ナジェージダの母).
カルーガ市内で穀倉商人や桟橋で居酒屋を営んでいた.
ニコライの実母 ナジェージダを含め, 4人の子を生した. 奇しくも2人ともニコライの生まれた年にこの世を去っている.
・ マクシム・ドミトリェヴィチ・ザヴェーリン (Maxim Dmitrievich Zaverin, 1823-?): ニコライの母方の曾祖父(ナジェージダの祖父).
・ イリーナ・ワシリェヴナ・ザヴェーリナ (Irina Vasilyevna Zaverina, ?-?): ニコライの母方の曾祖母(ナジェージダの祖母).
* 師 *
・ ダヴィッド・セルゲエヴィチ・クレイン (David Sergeevich(Abramovich) Krein, 1869-1926):
ヴァイオリニスト. ロシア帝国スモレンスク県ドロオブズ生まれ生まれ. ユダヤの血を引く家系で父 アブラム(1838-1921)はユダヤ音楽(クレツマー)のフィドル弾きだった.
兄弟7人すべてが職業音楽家となり, そのうち末弟 アレクサンドル(Allexandr Abramovich Krein, 1883-1951)は作曲家として成功を収めた.
帝国ロシア音楽協会ニジニ・ノブゴロド支部でヴァシリー・ヴィルアン(Vasiliy Villan, 1850-1922), モスクワ音楽院でヤン・フジマリー(Jan Hřímalý, 1844-1915)に師事.
1900年 ボリショイ劇場管弦楽団のコンサートマスターに就任, 1918年からはモスクワ音楽院の教授を務めた.
主な門人にセミョン・ベズロドニー(イゴール・ベズロドニーの父), ヴァシリー・シリンスキー.
余談だが19世紀末にバプステマ(キリスト教の洗礼)を行ってからは父性を本来のアブラモヴィチからセルゲエヴィチに改めている.
・ アニシム・アレクサンドロヴィチ・ベルリン (Anisim Alexandrovich Berlin, 1896-1961):
ヴァイオリニスト. ロシア帝国(現 リトアニア)ヴェゲリー生まれ.
ペトログラード音楽院(現 N.A.リムスキー=コルサコフ記念サンクトペテルブルク国立音楽院)でユダヤ人ヴァイオリニストのレオポルド・アウアー(Leopold Auer, 1845-1930)に師事.
1928年よりモスクワ・フィルハーモニー交響楽団に属し, 1941~1952年の間 コンサートマスターを務めた.
教育家の側面としては1923~1934年に亘り, モスクワ音楽院で後進の指導に当たった.
なお, チェリスト ナタリヤ・グートマン(Nataliya Gutmann, 1942- )の実の祖父にあたり, 1956~1960年にかけて指導し少年期の技術と抒情性の生育に寄与したと彼女は述懐している.
余談だが, ナタリヤの実父 アルフレッド・ベルリン(1912-1978)はアニシム 16歳のときの子で有機化学の分野で相当の成果をあげた. ピアノ演奏に長けていたという.
ナタリヤの実母 ミラ・グートマン(1914-1982)は 伝説的なピアニスト・名教師のゲンリフ・ネイガウス(1888-1964)に師事した職業 ピアニストであった.
ナタリヤがチェロに目覚めたきっかけは継父ロマン・サポジニコフ(1903-1987)の影響が強く, チェロの教則本なども手掛けていた彼に5歳の頃から指導を受けていた.
さらに余談になるが, ナタリヤの父称は実父のものでも継父に基づいたものでもない"グリゴリェヴナ(Grigorievna)"を名乗っている.
日本と異なり, ロシアでは14歳以上であれば自分の意思で名前を変更することが可能で, 申請書のほか手数料(1600 ), 出生証明書といった書類さえあれば受理される.
これは苗字や父称に関しても同様であり, 結婚や離婚に限らないさまざまな人生の転機やタイミングで変更する人が中にはいるということである.
ナタリヤが父称を変えた理由は明らかにされていないが, グートマンは母親の姓であることを考えるとなんとなくわかるような気もしてきます..
・ レインゴリト・マリツォヴィチ・グリエール (Reinhold Moritzevich Glière, 1875-1956):
作曲家. ロシア帝国(現 ウクライナ)キエフ生まれ. ドイツ人とポーランド人を両親に持ち, モスクワ音楽院でタネーエフ, アレンスキーなどに師事.
留学の後, 1920-41年の間 母校であるモスクワ音楽院に勤めた. 主な門人に プロコフィエフ, ハチャトゥリアン, リャトシンスキー.
主な作品に, 交響曲第3番『イリヤ・ムーロメッツ』, バレエ音楽『赤いけしの花』, コロラトゥーラ・ソプラノのための協奏曲, 25の前奏曲.
ラコフとの関わりは, 彼が入学した1926年に始まり, 卒業後もグリエールの助手として10年近く付随した. ラコフの作風は彼の影響が強い.
・ セルゲイ・ニキフォロヴィチ・ワシレンコ (Sergei Nikiforovich Vasilenko, 1872-1956):
作曲家. 指揮者. モスクワ生まれ.
16歳から音楽教育を受け, 高等教育では最初法理学を修了する. のちにモスクワ音楽院でタネーエフに師事. ピアノと作曲を学ぶ.
1906-1956までモスクワ音楽院に勤務(作曲法・管弦楽法)し, ハチャトゥリアン, ロスラヴェッツ, A.メリカントらを育てた.
主な作品に, ヴィオラ・ソナタ, 中国組曲第1番, 日本組曲, トランペット協奏曲『演奏会用ポエム』.
民族音楽・民族楽器と管弦楽法の扱いに長け, ラコフの色彩ある管弦楽法は彼譲りのところがある.
* 共 演・同 僚・友 人 *
+
・ ニコライ・ゼルツァロフ (Nikolai Zertsalov, 1890-?):
ヴァイオリニスト.
ピアニスト: ナタリヤ・ゼルツァロワ(Nataliya Nikolaevna Zertsalova, 1930-2017)の実父.
ラコフより18歳年上だったが, 少年期のラコフの友人として渓流釣りやキャンプで遊びまわっていた.
娘のナタリヤはヴァイオリニスト イーゴリ・オイストラフ(Igor Oistrakh, 1931-2021)の妻である.
・ タチアナ・ドストエフスカヤ (Tatyana Fyodorovna Sofronickaya-Dostoyevskaya, 1886-1958):
ピアニスト.
作家のフョードル・ドストエフスキー(Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, 1821-1881)の兄で同じく作家のミハイル・ドストエフスキー(Mikhail Mikhailovich Dostoyevsky, 1820-1864)の孫娘にあたる.
実父 フョードル・ドストエフスキー(Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, 1842-1906)は大作家と父称含めて同姓同名であるが, その叔父が命名したとされる.
彼はアントン・ルービンシュタインに学んだピアニストであり, 娘のタチアナもピアニストとして活動する傍らラコフの学ぶ音楽学校に講師として赴任した.
余談だが, タチアナは名ピアニスト ヴラディーミル・ソフロニツキー(Vladimir Vladimirovich Sofronitsky, 1901-1961)の妻となり一子を儲けている.
一般的にソフロニツキーは1920年に作曲家スクリャービンの娘 エレーナ(Elena Alexandrovna Sofronitskaya-Skriabina, 1900-1990)と,
自身の教え子であった後妻 ヴァレンティナ・ドゥシノワ(Valentina Nikolayevna Sofronitskaya-Dushinova, 1921-1964)と結婚したことが知られているが,
その2人の前に婚約していたのがタチアナである. タチアナとの間にイリーナ(Irina Vladimirovna Kryukova-Sofronickaya, 1919-1972?)を儲けている.
* 教え子 (キリル文字順) *
[ 作 曲 家 ]
+
* 太 字は国内外に知られる著名な作曲家 (ただし, 日本で有名であるとは限らない) *
・[
p]
セルゲイ・アルテムィエヴィチ・アガバボフ (Sergei Artcemyevich Agababov, 1926-1959):
作曲家. 現 ダゲスタン共和国・マハチカラ生まれ.
弟のアルカディヤ・アガバボフ (Arkadiya Agababov, 1940-2013)も作曲家である.
1951年, 地元のダゲスタン医学学校とマハチカラ音楽学校(合唱指揮科専攻)をともに優秀な成績で卒業する.
翌 1952年にはモスクワ音楽院でアナトリー・アレクサンドロフ(Anatoly Alexandrov, 1888-1982)の作曲科を受講し, 1956年 卒業.
卒業後は自身のダゲスタンでの暮らしを色濃く反映した, コーカサス民族色の強い合唱曲・交響作品の分野で活躍した.
ダゲスタン民俗調査学会のメンバーの顔も持ち, 『ダゲスタン芸術音楽成因』(1960, 死後出版)などの著書もある.
将来を嘱望されていながら, 航空機事故による悲劇的な最期を遂げた.
1959年, 33歳の誕生日を迎える2日前, 彼が搭乗していた航空機が目的地であるヴヌーコヴォ国際空港(モスクワ)で数度目の着陸を試みている最中, 樹木に接触し墜落.
5人の乗組員と(助かった1人を除く)23名の乗客の命が奪われ, アガバボフも帰らぬ人となった.
主な作品に, カンタータ『自由の物語』(1959), レズギ民謡に基づくダゲスタン組曲(1954), ピアノのための トッカータ(1955), ヴァイオリンとピアノのための 変奏曲(1951).
参考: W
参考: L
・[
p] ユリィ・ミハイロヴィチ・アレクサンドロフ (Yuri Mikhailovich Aleksandrov, 1914-2001):
作曲家. 現 ウズベキスタン共和国・タシケント生まれ.
モスクワ音楽院作曲科でヴィッサリオン・シェバーリン(Vissarion Yakovlevich Shebalin, 1902-1963)に師事したのち,
忙しくなったシェバーリンの後釜としてゲンリフ・リチンスキー(Genrikh Heinrich(Ilychi) Litinsky, 1901-1985)に師事, 1942年 卒業.
1946年より, とある音楽評論雑誌の編集者(のち編集長)として仕事をしたことが縁で, 1969年~75年まで大手出版社『ムジカ社』に編集者として登用された.
1953年~59年の間, グネーシン音楽大学にて管弦楽法と初見演奏を指導した.
主な作品に, 2つの交響曲(1942, 1955), ポエム『霊廟(レーニンの追憶に寄す)』(1951), ピアノ・ソナタ(1947), ヴァイオリンとピアノのための『ロシア狂詩曲』(1952).
参考: L
参考: L
参考: W
参考: DC
・[
p]
エドゥアルド・ニコラエヴィチ・アルテミィエフ (Eduard Nikolaevich Artemyev, 1937- ):
作曲家. ノヴォシビルスク生まれ.
7歳の時にモスクワの叔父の許に預けられ, モスクワ合唱学校で初等教育を受ける.
その後, モスクワ音楽院作曲家でユーリ・シャポーリン(Yuri Alexandrovich Shaporin, 1887-1966)に師事. 1960年 卒業.
卒業後すぐの1960年, 世界初のシンセサイザーのひとつ "ANS" の製作者 エフゲニー・ムルジン(Yevgeny Murzin, 1914-1970)と出会う.
スクリャービン博物館内に設置された実験電子音楽スタジオで楽音と電子音の合成に関する研究を行う.
一方で, 1961年 作曲家 ヴァノ・ムラデリ(Vano Muradeli, 1908-1970)の助言から映画音楽の仕事を始める.
電子音楽・実験音楽はいわゆる前衛音楽と同様にスターリン存命期は退廃的で形式主義者の芸術として批判された.
スターリンの死後, それらは緩和されたものの電子音楽が公に演奏される機会が訪れることはそうそうなかった.
アルテミィエフはロシア(ソ連)における最初期のシンセサイザー作曲家ともいえるが, 当時はそうした電子音楽の発表場所が
映画などの映像劇伴音楽でしか存在し得なかったことが, 彼の活躍したふたつの領域を表しているといえる.
主な作品に, ANSのための『宇宙』(1961), モスクワオリンピック開閉会式式典曲『スポーツについて ― 永遠なる進歩』(1980), 映画音楽『ストーカー』(1979).
参考: W
・[
p] ドミトリー・ドミトリエヴィチ・ブラゴイ (Dmitri Dmitrievich Blagoi, 1930-1986):
ピアニスト. 指揮者. 作曲家. モスクワ生まれ.
名教師 アレクサンドル・ゴリデンヴェイゼル(Alexander Borisovich Goldenveizer, 1875-1961)の推薦で, 1936年 モスクワ音楽院付属中央音楽学校 入学し,
ゴリデンヴェイゼル門下のエレーナ・ホーヴェン(Elena Petrovna Khoven)にピアノを師事.
高等部ではゴリデンヴェイゼル自身にピアノを学び, 1948年 モスクワ音楽院に進学.
ピアノ科でゴリデンヴェイゼル, 作曲科でニコライ・ペイコ(Nikolai Peiko, 1916-1995)に師事.
1954年 ピアノ科を, 1957年 作曲科 ユーリ・シャポーリン(Yuri Alexandrovich Shaporin, 1887-1966)のクラスを卒業.
1958年にはモスクワ音楽院大学院を卒業. 卒業後は恩師 ゴリデンヴェイゼルの助手をする傍ら, 音楽院でピアノと室内アンサンブルの科目で教鞭をとった.
自身の才能を引き立ててくれたゴリデンヴェイゼルの信奉者で, 1970年には博士論文『校訂者-アレクサンドル・ゴリデンヴェイゼル』を上梓.
彼の死後, 遺稿を整理し『ゴリデンヴェイゼル版ベートーヴェン:ピアノソナタ』を出版するなど結びつきが強かった.
ピアニストとしてロシア古典派を得意とする一方で, 現代ロシア作品の録音も精力的に行い, 生涯で15のレコードをリリース.
作曲家としての側面も持ち, 自作の録音も残した. ラコフの作品では『ピアノソナタ 第1番』の録音がある.
主な作品に, ピアノのための24の前奏曲(1958), ピアノソナタ『おとぎ話』(1958), ピアノとオーケストラのための『華麗なる奇想曲』(1960).
以下, 余談ではあるがブラゴイの家系は王族の警備や外交使節団の一員を担った16世紀ごろの貴族 ブラゴヴォ家まで遡ることが出来る.
父の母方系にはロシア・トルコ戦争におけるチェスマ海戦(1770)で活躍した英雄 スピリドフ提督(Geigory Spiridov, 1713-1790)がいる.
ピアニスト ドミトリー・ブラゴイ(以下 ドミトリーJr. )の両親はともに文学研究者であり,
特に父 ドミトリー・ブラゴイ(Dmitri Dmitrievich Blagoy, 1893-1984, 以下ドミトリーSr. )はプーシキン研究の第一人者として名を馳せた.
余談の余談ではあるが, 同名の父親が有名人であったため, ドミトリーJr. は学生のあいだ, ドフトエフスキー研究家であった母親の旧姓を用いてドミトリー・ネチャエフと名乗っていた.
ドミトリーSr. は長男(ドミトリーJr. の兄にあたる)を幼くして亡くしており, 37歳のときの子である 一人息子ドミトリーJr. を大変可愛がった.
この偉大なる父は91歳で天寿を全うしたが, その死去に伴うショックは大きく, 疲弊したドミトリーJr. は医師の診察を仰ぐが癌が見つかり余命2か月を宣告されてしまう.
結果としてそれから2年近く生き抜いたのち, 56歳でこの世を去った.
さらに余談の余談の余談ではあるがブラゴイ家の長男は「ドミトリー」と名付ける習慣があるようで,
ピアニスト ドミトリー・ブラゴイ(1930-1986)の父は文学研究者 ドミトリー・ブラゴイ(1893-1984). 祖父は税務官・大学秘書であったドミトリー・ブラゴイ.
曾祖父は図書館運営者 ドミトリー・ブラゴイ. (ちなみに高祖父はイワン・ブラゴイとなり規則から外れるが, 長男でなかったのかもしれない)
ピアニスト ドミトリーは5人の子供を儲け, 長女 ベラ, 次女 マリア, 長男 ドミトリー, 三女 アンナ, 次男 イワン…とやはり規則どおりといえるようだ.
参考: W
参考: L
・[
p] ヴラジーミル・ミハイロヴィチ・ブローク (Vladimir Mikhailovich Blok, 1932-1996):
作曲家. モスクワ生まれ.
参考: W
・[
p] エフゲニー・ミハイロヴィチ・ボティャロフ (Evgeny Mikhailovich Botyarov, 1935-2010):
作曲家. 生まれ.
参考: L
参考: L
参考: L
参考: L
・[
p] ウラジーミル・ミハイロビッチ・ブルームベルク (Vladimir Mikhailovich Brumbelg, 1920-1998):
作曲家. 沿ヴォルガ連邦管区サラトフ州エカテリーノフスキー地区コレノ村生まれ.
ユダヤ人ピアニスト ミハイル・ブルームベルク(Mikhail Fedorovich Brumbelg, 1875-1934)と文学者 マリヤ・トロポフスカヤ(Mariya Naumovna Brumbelg-Tropovskaya, 1878-1956)の次男.
モスクワ音楽院では作曲科 ヴィッサリオン・シェバーリンとドミトリー・ショスタコーヴィチに師事.
1947年の音楽院卒業後は第23児童音楽学校で音楽理論・旋律法・作曲法について指導していた.
主な作品に, 交響曲(1964), 弦楽四重奏(1948), ピアノソナタ(1968), 子供のためのアルバム(1964).
余談だが, このページを最初に執筆したころ(2012年頃)は顔写真はおろか本人に関する評が一切得られなかった. いい時代になったね….
参考: L
参考: L
参考: L
・ グリゴリー・イヴァナヴィチ・ヴォスカニャン (Grigory Ivanovich Voskanyan, 1908-1987):
作曲家. ロストフ・ナ・ドヌ生まれ.
参考:
参考:
・ ユリィ・ヤコヴレヴィチ・ヴラジーミロフ (Yurii Yakovlevich Vladimirov, 1925-1978):
作曲家. 生まれ.
参考: L
参考: L
参考: L
・
ラウフ・ハジエフ (Rauf Soltan oglu Hadhiev, 1922-1995):
作曲家. 現 アゼルバイジャン・バクー生まれ.
参考: W
・ イサイ・ヤコヴレヴィチ・ハルキン (Isay Takovlevich Halkin, 1899-1968):
作曲家. 生まれ.
参考: L
参考: L
参考: L
・[
p] ニコライ・ボリソヴィチ・ゴルロフ (Nikolai Borisovich Gorlov, 1926-1989):
作曲家. 生まれ.
参考: L
参考: L
・[
p] ミハイル・オスカロヴィチ・グラチョーフ (Mikhail Oskarovich Grachov, 1911-1988):
作曲家. 生まれ.
参考:
参考:
参考:
・ S.グリゴリィエフ (С.Григорьев, ):
作曲家. 生まれ.
・ ニコライ・ペトロヴィチ・グバリコフ (Nikolai Petrovich Gaburykov, 1914-1985):
作曲家. バヤン奏者. ペンザ州ニジニロモフスク行政区(郡)ロシア=ムロカ(村?)生まれ.
1942年, モスクワ音楽院作曲科 ヴィクトル・ベリイ(Viktor Bely, 1904-1983)のクラスを卒業.
1942-51年 ロシア民謡楽団 及び モスクワ=ピオネール・市民の家(共産党施設) のアンサンブル長を歴任. 1968年, RSFSR文化功労者賞.
主な作品に, 合唱とオーケストラのためのポエム=カンタータ『モスクワ』(1942), 2つのピアノソナタ(1940, 1956), バヤンのための5つの練習曲(1966).
顔写真も残されていないマイナーな作曲家だが, 子供向け短編アニメ『ジョルティック (Жёлтик, 1966)』のための付随音楽でその作風を垣間見る(聞く?)ことができる.
…どことなーく, ラコフの音楽に通ずる匂いを感じる. ちなみに"ジョルティック"はこのアニメの主人公であるヒナの名前だそうだ.
参考: L
参考: Жёлтик
・[
p] アスラン・アリエヴィチ・ダウロフ (Aslan Alievich Daurov, 1940-1999):
作曲家. 教授. 指揮者. 作家. 民俗学者. 現・カラチャイ・チェルケス共和国ハベズスキー地区(村)生まれ.
参考: L
参考: L
参考: L
・
エディソン・デニソフ (Edison Vasilievich Denisov, 1929-1996):
作曲家. トムスク生まれ.
参考: W
・ ゲオルギー・ペトロヴィチ・ドミトリエフ (Georgy Petrovich Dmitriev, 1942- ):
作曲家. クラスノダール生まれ.
参考: W
・ マクシム・イサーコヴィチ・ドゥナィエフスキー (Maksim Isaakivich Dunaevsky, 1945- ):
作曲家. モスクワ生まれ.
参考: W
・ R.ジハイチス (Р.Жигаитис, ):
作曲家. 詳細不明. 1969年の著書に『Беспокоǐне птицы』がある.
・ ミハイル・パヴロヴィチ・ジフ (Mikhail Pavlovich Ziv, 1921-1994):
作曲家. 生まれ.
参考: W
・ シギスムント・アブラマヴィチ・カッツ (Sigizmund Abramovich Kats, 1908-1984):
作曲家. ウィーン生まれ.
参考: W
・ ヴラジーミル・コンスタンチノヴィチ・コマロフ (Vladimir Konstantcinovich Komarov, 1940- ):
作曲家. 生まれ.
参考: W
・ ヴラジーミル・イバナヴィチ・クリヴェツォフ (Vladimir Ibanovich Krivtsov, 1938-1990):
作曲家. モスクワ生まれ.
参考: W
・ ヴィクトル・ヴィクトロヴィチ・クプレヴィチ (Viktor Viktorovich Kuprevich, 1925- ):
作曲家. 現 リトアニア・カウナス生まれ.
参考: W
・ ロマーン・セミョーナヴィチ・レデニョフ (Roman Semyonovich Ledenyov, 1930- ):
作曲家. モスクワ生まれ.
参考: W
・ アナトリー・ヤコヴレヴィチ・レーピン (Anatoly Yakovlevich Lepin, 1907-1984):
作曲家. 生まれ.
参考: W
・[
p]
ヴァシリ・パヴロヴィチ・ロバノフ (Vasily Pavlovich Lobanov, 1947- ):
作曲家. ピアニスト モスクワ生まれ. ドイツ在住(1991年~).
1963年~71年の間在籍したモスクワ音楽院で多くの学友と机を並べている.
このうち, シニトケに関してラコフとの師弟関係が一致しているため, 二人はラコフの楽器法の授業を受けていたと思われる.
ピアニストとしては, オレグ・カガン(Oleg Kagan, 1946-1990; violinist)とナターリヤ・グートマン(Natalia Grigorievna Gutman, 1942- ; cellist)夫妻とよくリサイタルを開いていた.
主な作品に, ソポクレスの悲劇に基づくオペラ『アンティゴネ』作品51(1985-87), レフ・トルストイに基づくオペラの一幕『父―セルギウス』作品57(1995), チェロ協奏曲 作品42(1985).
参考:
参考: Official Site
参考: L
参考:
・ ピョートル(ペトル)・ペトロヴィチ・ロンドノフ (Pyotr Petrovich Londonov, 1928-1981):
作曲家. 生まれ.
1948年 ペンザ音楽学校 バヤン科 卒業. 1952年 モスクワ音楽院内音楽学校(大学相当?)作曲科 卒業.
1957年 モスクワ音楽院(大学院相当?)作曲科 エフゲニー・メスネル(Evgeny Iosifvich Messner, 1897-1967)のクラスを卒業.
1957年より音楽出版社『ムジカ("音楽")』(のちの『ソビエト作曲家』社)の音楽編集者として勤務. バヤンの奏法に関する著作, 楽曲集の編纂が残されている.
参考: L
参考: L
参考: L
参考: L
参考:
参考:
N
・
アレクサンドル・ロクシン (А.Локшин, 1920-1987):
作曲家. 生まれ.
参考:
・ アルカディー・ニコラエヴィチ・マザィエフ (Arkady Nikolaevich Mazaev, 1909-1987):
作曲家. ツァリーツィン(現 ヴォルゴグラード)生まれ.
参考: W
・
ヴラジーミル・イヴァナヴィチ・マルトゥィノフ (Vladimir Ivanovich Martuinov, 1946- ):
作曲家. モスクワ生まれ.
参考: W
・ ミハイル・アレクサンドロヴィチ・メィエロヴィチ (Mikhail Aleksandrovich Meyerovich, 1920-1993):
作曲家. 現 ウクライナ・キエフ生まれ.
参考: W
・
ヴァノ・ムラデリ (Vano Ilych Muradeli, 1908-1970):
作曲家. ロシア帝国(現 グルジア)ゴリ生まれ.
参考: W
参考: L
・ アレクセイ・アレクサンドロヴィチ・ニコラエフ (Aleksei Aleksandrovich Nikolaev, 1931-2003):
作曲家. 生まれ.
参考: L
参考: L
・
タチアナ・ペトロヴナ・ニコラエワ (Tat'yana Petrovna Nikolaeva, 1924-1993):
ピアニスト. 音楽教師. 作曲家. ベジツァ生まれ.
参考: W
・ アレクサンドル・パヴェロヴィチ・ネムチン (Aleksandr Pavlovich Nemtcin, 1936-1999):
作曲家. ペルミ生まれ.
参考: W
・ A.ネスチェロフ (А.Нестеров, ):
作曲家. 生まれ.
・ M.パルツァラーゼ (М.Парцхаладзе, ):
作曲家. 生まれ.
・
ニコライ・イヴァナヴィチ・ペイコ (Nikolai Ivanovich Peiko, 1916-1995):
作曲家. 指揮者. モスクワ生まれ.
参考: W
・ アレクサンドル・イヴァナヴィチ・ピルモフ (Aleksandr Ivanovich Pirumov, 1930-1995):
作曲家. 現 グルジア・ティフリス生まれ.
参考: L
・ T.ポパティエンコ (Т.Попатенко, ):
作曲家. 生まれ.
・ R.ロム (Р.Ромм, ):
作曲家. 生まれ.
・ V.ルカヴィシニコフ (В.Рукавишников, ):
作曲家. 生まれ.
・ A.セヴァスチャノフ (А.Севастьянов, ):
作曲家. 生まれ.
・
ミハイル・ニコラエヴィチ・シマンスキー (Mikhail Nikolaevich Simansky, 1910-2002):
作曲家. 生まれ.
参考:
・ ドミトリー・ブラニスラヴォヴィチ・スモリスキー (Dmitri Bronislavovich Smolysky, 1937- ):
作曲家. ミンスク生まれ.
参考: W
・
エフゲニー・スチーヒン (Evgeny Mikhailovich Stikhin, 1932- ):
作曲家. 生まれ.
参考: L
参考: W
・[
p] ボリス・ミハイロヴィチ・テレンティエフ (Boris Mikhailovich Terent'ev, 1913-1989):
作曲家. オペラ作家. オデッサ生まれ.
参考: L
参考: L
参考: L
参考: L
参考: L
・
カレン・ハチャトゥリアン (Karen Surenovich Khachaturian, 1920-2011):
作曲家. モスクワ生まれ.
参考: W
参考: L
・
ボリス・チャイコフスキー (Boris Alexandrovich Tchaikivsky, 1925-1996):
作曲家. 生まれ.
参考: W
・ シルヴァニ・ラマザノヴィチ・チャラィエフ (Shrvani Ramazanovich Chalaev, 1936- ):
作曲家. 現 ダゲスタン共和国・クリンスキー管区ホスレフ村近郊生まれ.
参考: W
・ トリブ=ホン・ジヤドゥルラエヴィチ・シャヒジ (Tolib-khon Ziyadullaevich Shakhidi, 1946- ):
作曲家. 指揮者. 現 タジキスタン・ドゥシャンベ生まれ.
参考: W
・
アルフレート・ガリエヴィチ・シニトケ (Alfred Garyevich Schnittke, 1934-1998):
作曲家. エンゲリス生まれ. ドイツ系の両親の元, 最初は父親の赴任先であるウィーンにて音楽教育を受け始める.
1961年 モスクワ音楽院卒業. 西側からの前衛・実験音楽の影響を受け, 自由な12音技法やセリー技法を採用した音楽や伝統音楽との共存を図った作品を残す.
ラコフからは楽器法(オーケストレーション)について学んだが, 作曲家としてシニトケの作風に与えた彼の影響はそれほど多くないといえる.
代表作は, 交響曲第1番, コンチェルト・グロッソ, オラトリオ『長崎』.
参考:
・ タイシャ・イヴァノヴナ・シュテンコ (Taisya Ivanovna Shtenko, 1905-1975):
作曲家. ハルキウ(現・ウクライナ)生まれ.
参考:
参考: W
・
アンドレイ・エシュパイ (Andrei Yakovlevich Eshpai, 1925-2015):
作曲家. マリ・エル共和国コズモデミャンスク生まれ.
参考: W
・[
p] エフゲニア・イオシフヴィチ・ヤフニナ (Evgenia Iosifovna Yakhnina, 1892-1979):
作曲家. 帝政ロシア時代のツァールスコエ・セロー生まれ(と思われる).
旧姓 ツェデルバウム. 本人に関する評はほとんど残されていないため, 詳細は不明だが,
トルコ出身のユダヤ人両親の家庭の末子(父親が53歳のときの子)として生まれ,
実兄は第一次ロシア革命前後でメンシェヴィキを率いた社会運動家で知られるユーリ・マルトフ(Yuliy Martov, 1873-1923).
及び 実子は翻訳家・文芸評論家のユリアナ・ヤフニナ(Yulyana Yakovlevna Yakhnina, 1928-2004).
娘 ユリアナはロシア語のほかフランス語・スウェーデン語・ノルウェー語・デンマーク語などに長けていた.
エフゲニア自身も語学に覚えがあったのか, ラコフ作品においてリトアニア語の詩をロシア語に直すお手伝いをしていたようだ.
父 オシフ(1839-?)は船会社の事務長であり, 幼少期から住まいを転々としていたこと, 1894年 兄 ユーリがリトアニアに追放されたことからも,
彼女がリトアニア語に慣れ親しんでいた根拠がないわけではないことを注記しておく.
余談だが, 彼女の生年は1892年 ないし 1891年であり, これはラコフより16歳程度年長である.
参考: L
参考: L
[ 音 楽 学 者 ]
+
・ ヴェラ・アンドリェーヴナ・ワシナ=グロスマン (Vela Andreevna Vasina-Grossman, 1908-1990):
音楽学者. (ロシア帝国)リャザン生まれ.
1931年, モスクワの音楽大学(不詳)ピアノ科を卒業. 1938年にはモスクワ音楽院 音楽史・音楽理論専攻を修了(E.Fermanに師事).
1939年より10年制中央音楽学校や中央通信音楽研究所などで音楽史の授業を受け持つようになる. 1942年~57年 モスクワ音楽院音楽史講師.
1949年以降はソ連文化省所属の芸術史研究所の主任研究員という顔もあった.
教育者としては音楽史が専門であり, また 執筆も盛んであった. 1938年~39年は芸術新聞『ソビエトアート』の記者でもあった.
著書に『ムソルグスキーとハルトマン』『ロシヤ音楽入門(1956)』『グリンカ―その作品と生涯(1957)』などがある.
なお, 奇しくもラコフと生没年を同じくしているが, 3月5日(当時のユリウス暦で 2月21日)生まれの彼女のほうがラコフより9日年上である.
参考: academic.ru (ロシア語)
参考: Wikipedia (ロシア語)
・[
p] ライサ・ウラジーミロヴナ・グレーゼル (Raisa Vladimirovna Glezer, 1914-1985):
音楽学者. (ロシア帝国)オレンブルク生まれ.
オレンブルク音楽大学でソフィア・ロストロポーヴィチ(Sofia Rostropovich-Fedotova, 1891-1971; ムスティスラフ・ロストロポーヴィチの母)に師事し,
1935年 モスクワ音楽院ピアノ科のグリゴリー・ギンズブルク(Grigory Ginzburg, 1904-1961)のクラスを卒業.
さらに, ソ連科学学会の芸術史研究所でボリス・アサフィエフ(Boris Asafiev, 1884-1949)指導の下 音楽史・音楽理論の研究に励む.
1941年 地元オレンブルクに戻るとオレンブルク市立音楽学校に音楽史科を開設, 責任者を務めた.
1943年 モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団の顧問を務め, 演奏家の指導に当たった.
『アラム・ハチャトゥリアン (1955)』『アナトリー・ノヴィコフ (1957)』『ドミトリー・カバレフスキー (1969)』といった作曲家個人の生涯とその作品に関する著作がある.
1985年, モスクワ州郊外の農村 スタラヤ・ルーザにある"作曲家の家"という施設でハチに刺されたことによるアレルギー性ショックでこの世を去った.
参考: Orenburgsky krai(ロシア語)
参考:
参考: Wikipedia (ロシア語)
・ L.ゴロホワ (, ):
音楽学者. 詳細不明.
・[
p] エレーナ・アンドリェエヴナ・グロシェワ (Elena Andreevna Grosheva, 1908-2002):
音楽学者. (現・アゼルバイジャン)バクー生まれ.
バクー・オペラ劇場管弦楽団のオーボエ奏者の娘として生まれる.
1932年 トビリシ音楽院でタマラ・テル=ステパノワ(Tamara Isaakovna Ter-Stepanova, 1874-1934)のピアノ科を卒業.
次いで 1937年 モスクワ音楽院 音楽史および音楽理論専攻修了.
1935年 全ソ連ラジオ委員会で音楽講師. 1937~41年 「ソビエトアート」「プラウダ」といった新聞・機関紙や「ソビエトアート」「シアター」などの雑誌に多くの記事を寄せた.
その後も編集委員などを経て, 1961~70年 雑誌「ソビエト音楽」の編集長を務めつつ, 1963~66年にはレーニン賞選考委員の一員でもあった.
オペラ・オペレッタ研究やロシアのオペラ劇場に関する歴史が専門で, 声楽家や作曲家に関する著書もある.
参考: LiveLib (ロシア語)
参考: Wikipedia (ロシア語)
・ レフ・ワシリェヴィチ・ダニレヴィチ (Lev Vasilievich Danilevich, 1912-1980):
音楽学者. イヴァノヴォ県シューヤ生まれ.
1936年 モスクワ音楽院 音楽史および音楽理論学部卒業, 以後は大学部で講師をしながら 1939年 同院大学院課程修了.
卒業後の1941~44年(大祖国戦争の期間) 南北コーカサス, ヴォロネジ, 第1ウクライナ戦線といった各地で赤軍での歌や踊りを統括する音楽監督を担う.
復帰後は音楽院での講師業に加えて, 全ソ連ラジオ放送の編集長やソ連作曲家連合の批評委員会委員長などを歴任した.
1949~1957年 モスクワ音楽院 准教授(音楽理論?), 1969~72年 グネーシン音楽教育研究所准教授など勤め上げた.
参考: d
参考: d
参考:
参考:
参考:
・ V.デリソン (, ):
音楽学者. 生まれ.
参考:
参考:
・ A.イコンニコフ (, ):
音楽学者. 生まれ.
参考:
参考:
・ V.コーネン (, ):
音楽学者. 生まれ.
参考:
参考:
・ イワン・イバナヴィチ・マルトゥイノフ (Ivan Ivanovich Martuinov, 1908-2005):
音楽学者. 現・ブリャンスク州 カラチェフ生まれ.
実子は作曲家・哲学者のウラジーミル・マルティノフ (Vladimir Ivanovich Martynov, 1946- ).
イワンとウラジーミルはともにラコフに学んでおり, 親子2代に渡ってラコフ先生にお世話になっている. いいなぁ…
参考:
参考:
・ K.ペトロワ (, ):
音楽学者. 生まれ.
参考:
参考:
・ Y.ペッケル (, ):
音楽学者. 生まれ.
参考:
参考:
・ M.リティッフ (, ):
音楽学者. 生まれ.
参考:
参考:
・ M.ロイターシュテイン (, ):
音楽学者. 生まれ.
参考:
参考:
・ N.ツマニナ (, ):
音楽学者. 生まれ.
参考:
参考:
+
・ R.アルタイェフ (, ):
指揮者. 生まれ.
参考:
参考:
・ A.ジュライティス (, ):
指揮者. 生まれ.
参考:
参考:
・ M.カーサヴィン (, ):
指揮者. 生まれ.
参考:
参考:
・ L.キラーゼ (, ):
指揮者. 生まれ.
参考:
参考:
・ A.ラザレフ (, ):
指揮者. 生まれ.
参考:
参考:
・ G.ロジェストヴェンスキー (, ):
指揮者. 生まれ.
参考:
参考:
・ I.シュピッレル (, ):
指揮者. 生まれ.
参考:
参考:
・ M.ユロフスキー (, ):
指揮者. 生まれ.
参考:
参考:
* 題 材 (詩 提 供) * +
・ ピョートル・ネズナモフ (Piotr Vasilievich Neznamov, 1889-1941):
ロシアアヴァンギャルド, 未来派の詩人. 文芸評論家. トランスバイカル地方ナルチン工場村生まれ.
参考: Пëтр Васильевич Незнамов
・ ヴィクトール・イリーチ・ヴィクトロフ (Viktor Ilyich Viktrov, 1925-1991):
詩人. 翻訳家. 劇作家. 小説家. 本名: ヴィクトール・イイェゼキーリェヴィチ・ベルリン.
参考: Викторов Виктор Ильич
・ アショート・ゲオルギェヴィチ・ガルナケリャン (Ashot Georgiievich Garnakeryan, 1907-1977):
詩人. ロストフ・ナ・ドヌ生まれ.
参考: Ашот Георгиевич Гарнакерьян
◆ 作 風
・ラコフは20世紀という時代を鑑みてもそれまでの西洋音楽が体系化してきた管弦楽法や旋律法に則った堅牢で保守的な作品を書いた.
師であるグリエールやグラズノフのスタイルを継承する形であるが, 表現の幅という点に於いて独自の拡張もみられる.
・予期せぬ転調や後期ロマン派の和声, 流麗な旋律線が彼の作品の特徴であり, ロシア国民楽派的側面も多分に含んでいた.
・一方で, 後期作品に於いては新古典主義の影響もみられる. (音楽院の試験曲などでもそういった作風のものがある)
・ロシア(ソ連)の各地に残る伝承音楽や民俗音楽に大きな関心があり, カルーガ時代集中的に採譜・研究した時期がある.
それらの素材は複数の自作品や楽器編成に生かされている. 採譜したメロディーがそのまま自作品の動機に生かされた例としては,
『交響曲第1番(1944)』(キルギスタン民謡に基づく)や『ロシア序曲(1947)』, ピアノのための『民謡に基づく10の小品(1951)』などがある.
・歌曲も多く取り上げているが, その中には19世紀前半の農奴 M.スハーノフのかなりマイナーな詩も含まれる.
農民の詩を採用しているのはラコフ自身 スラブ人の民俗習慣や農村の休日, 儀式といった民間伝承に精通していたことと不可分である.
・楽器法(管弦楽法)が専門であったが, (カバレフスキーらと同様に)同時に子供のための音楽に特別な関心を抱いていた.
そのため, 音楽教育を目的としたピアノ小品や室内楽作品も数多く残している.
・ソビエト連邦時代, こういった馴染みやすい要素によってラコフの作品は大変な人気を博した.
そのうち, 最も有名なものがヴァイオリニスト ダヴィッド・オイストラフによって披露された彼の『ヴァイオリン協奏曲第1番(1944)』である.
この作品の成功によってラコフは1946年, スターリン賞を受賞している.
◆ 作 品
太字は楽譜・音源が(一部または全部)手元にあるものです. (#: 楽譜のみ *: 音源のみ #*:楽譜・音源)
[ 略 記 号 説 明 ]
| 表示 | 内容/備考 |
|---|
| [ *● ] | 註釈 |
| (*c●) | 作品に対する備考・補足 c: "c"omposition |
| # | (一部分 または 全項の) 楽譜 所持 |
| * | (一部分 または 全ての) 音源 所持 |
| #* | (一部分 または 全ての) 楽譜 および 音源 所持 |
| [p] | 作品の譜例 p: "p"icture |
| [y] | Youtube上の参考動画・音源 y: from "Y"outube |
| [n] | ニコニコ動画上の参考動画・音源 (uploaded by chafall/chafall7) n: from "N"icodou |
| [d] | 参考文献・参考サイト・参照情報 d: "d"ata |
| [s] | 楽譜の購入サイト・所蔵図書館情報 s: "s"core |
| [sd] | 図書館共同体OCLCによる書誌データベースWorldCatによる学術情報ページ sd: "s"core "d"ata |
[ 日本語 表記 ]
管 弦 楽 作 品
スケルツォ (1930, 出版: 1936)
マリ風組曲 (作品7?) (1931, 出版: 1933)
[*1] * 全3楽章制 [sd]
[
p]
* 舞曲組曲 (1934, 出版: 1938) [*1]
I. ウズベクの踊り
II. アルメニアの踊り
III. タタールの踊り
IV. タジクの踊り
V. 終曲
[
p]
* 交響曲 第1番 ニ長調 (1940, 出版: 1947, 改訂: 1958) [*1] [sd]
* 英雄行進曲 ト長調 (*c1) (1942, 出版: 1948)
[
p]
* 演奏会用ワルツ イ長調 (*c2) (1946, 出版: 1948) [sd]
ロシア序曲 (1947, 出版: 1948)
[sd]
『カザフスタンの草原にて』 (1947, 出版: 1948)
[sd]
* 演奏会用組曲 ヘ長調 (1949, 出版: 1951) [d]
I. 行進曲
II. マズルカ
III. メロディ
IV. 舞曲
V. ワルツ
VI. フィナーレ
バレエ組曲 (1951, 出版: 1952)
[sd]
叙情的なメロディ (1951, 出版: 1952)
[sd]
[
p]
* 交響曲 第2番 ヘ長調 『青少年のために』 (1957, 出版: 1961) [y] [sd]
[
p]
* 弦楽オーケストラのためのシンフォニエッタ ト短調 (*c3) (*c4) (1958, 出版: 1961) [y] [y] [sd]
[
p]
* 交響曲 第3番 ハ長調 『小交響曲』 (1962, 出版: 1964) [*1] [y] {[y] [y] [y] [y]} [sd]
* 弦楽オーケストラのための5つの小品『夏の日々』 (1969, 出版: 1971) [*1]
I.
# 朝
II. 湖畔 (ワルツ)
III. たくましい行進曲
(*c5)
IV. まきばの散歩
V. ナイト・ゲームズ
* 2つのワルツ (1973) [sd]
第1番 祝典ワルツ ニ長調 (1973)
第2番 瞑想的なワルツ ホ短調 (1971)
(*c6)
交響曲 第4番 (1973)
弦楽オーケストラのための11の小品 (1975, 出版: 1982)
[sd]
No. 1: 前奏曲
No. 2: グレアの遊び
No. 3: 間奏曲
No. 4: ユーモレスク
No. 5: バガテル
No. 6: セレナード
No. 7: 聖歌
No. 8: マズルカ
No. 9: 夕べの歌
No.10: スケルツォ
No.11: メロディ
No.12: 行進曲
ロマンティックなワルツ (ワルツ第3番?) (1977)
* 弦楽オーケストラのための 詩曲 第1番『強靭なる精神』 (1979)
* 弦楽オーケストラのための 詩曲 第2番 (1981)
協 奏 曲 作 品
[
p]
#* ヴァイオリン協奏曲 第1番 ホ短調 (*c7) (1944, 出版: 1946, ピアノリダクション: 1952) [*1] [y] {[y] [y] [y]} {[y] [y] [y]} [d] [sd]
[
p]
#* ヴァイオリン・コンチェルティーノ ニ短調 (*c8) (1960, 出版: 1961) [sd]
[
p]
#* ヴァイオリン協奏曲 第2番 イ短調 (1954-63, 出版: 1970) [y]
2つのヴァイオリンとオーケストラのための 4つの小品 (1964, 出版: 1965)
#* クラリネットとオーケストラのための 幻想協奏曲 (*c9) (1968, 出版: 1971) [*1]
[
p]
#* ピアノ協奏曲 第1番 (*c10) (1969, 出版: 1974, ピアノリダクション: 1971) [y] [sd]
[
p]
#* ピアノ協奏曲 第2番 (*c10) (1969, 出版: 1974, ピアノリダクション: 1971) [y] [sd]
[
p]
# ピアノ協奏曲 第3番 (*c10) (1977/73?)
[
p]
# ピアノ協奏曲 第4番 (*c10) (1977)
クラリネット協奏曲 (1986, 出版: 1989)
[sd]
チェロとオーケストラのための 詩曲
[y]
オーボエ協奏曲 (1986)
イングリッシュ・ホルンと弦楽オーケストラのための 抒情詩
吹 奏 楽 作 品
コンバット・マーチ(戦闘行進曲)
(*c11) (1930, 出版: 1932)
カザフスタン民謡の主題による間奏曲 (1931, 出版: 1932)
組曲 第1番 (1933, 出版: 1938)
組曲 第2番 (1940, 出版: 1947)
行進曲『祖国のために』 (1941)
飛行士行進曲 (1941, 出版: 1948)
行進曲『迎撃』 (1942)
* 行進曲『戦艦乗り(戦車兵)』 (1942, 出版: 1947)
行進曲『英雄』
(*c1) (1943)
* 行進曲『衛兵』 (1943?)
春の序曲 (1952, 出版: 1958)
行進曲『人民の情け』 (1956, 出版: 1957)
ロシア序曲 (1960, 出版: 1961)
前奏曲 (1975, 出版: 1976)
[
p]
# 演奏会用行進曲『期に向かって』 変なタイトルだけど適切な和訳が思いつかないんやん…
ロ シ ア 民 族 楽 器 オ ー ケ ス ト ラ (*c12)
『輪舞とプリャソヴァヤ
(*c13) 』 (1949, 出版: 1950)
『懶い』 (1949, 出版: 1949)
ロシア民謡の主題による変奏曲 (1949?)
8つの小品 (1951, 出版: 1956)
序曲 (1952, 出版: 1954)
組曲 [4つの小品] (1965, 出版: 1967)
[sd]
『影法師』 [10の小品] (1974)
ジ ャ ズ オ ー ケ ス ト ラ 作 品
コンバット・マーチ
(*c11) (1930, 出版: 1937)
デモ行進曲 (1930, 出版: 1937)
タタール舞曲 (1933, 出版: 1935)
ギャロップ (1939, 出版: 1948)
#* セレナーデ (1942, 出版: 1956) [y]
# タンゴ (1942, 出版: 1956)
* 遅い舞曲 (1942, 出版: 1950) [y]
諧謔的ギャロップ (1949, 出版: 1949)
休日行進曲 (1949, 出版: 1949)
競技行進曲
(*c5) (1949, 出版: 1950)
『ロシアの砂浜』 (1949, 出版: 1952)
叙情的なワルツ (1949, 出版: 1952)
マズルカ (1949, 出版: 1954)
舞曲 (1949, 出版: 1953)
『ロシアン・ゲーム』
(*c14) (1951, 出版: 1954)
ワルツ (1954 pub.1954)
スロー・フォックストロット
(*c15) (1968, 出版: 1969)
『じゃじゃ馬娘』 (1970, 出版: 1972)
ボサ・ノヴァ(1970, 出版: 1972)
『共に…』 (1970, 出版: 1973)
『出逢いの歓び』 (1972, 出版: 1974)
[y]
# 古いワルツ
# 『ブィリーナ』
# 『冬の散歩道』
ピ ア ノ 作 品
[
p]
# 踊り 作品1 (1929, 出版: 1930)
[
p]
# 2つの練習曲 作品2 (1929, 出版: 1930)
I. イ短調
[y (MIDI)]
II. ホ短調
[y] [y]
# 4つの子供のための小品 (1929, 出版: 1937)
I. 子守歌
II. 行進曲
III. 昔話
IV. ペトルーシュカ
[
p]
# 4つの前奏曲 作品6 (*c16) (1930, 出版: 1933)
# 叙情的な小品 (1935, 出版: 1937)
I. ハ長調
II. ハ長調
III. イ短調
IV. ハ長調
[
p]
# 2つのマリ風小品 (1936, 出版: 1937)
I. イ短調
II. へ短調
[
p]
# 5つの前奏曲 (1936, 出版: 1940) [sd]
I. ハ長調
II. イ短調
III. ホ短調
IV. ニ長調
V. ロ短調
[
p]
# 10のノヴェレッテ (*c17)(1937, 出版: 1938)
I. ユーモレスク (ホ短調)
II. 寓話 (ハ長調)
(*c18)
III. アラベスク (ト長調)
IV. 行進曲 (変ロ短調)
V. ノヴェレッテ (変ホ長調)
VI. ワルツ (嬰へ短調)
(*c19)
VII. スケルツォ (二短調)
VIII. 歌 (変ロ長調)
IX. マズルカ (ロ短調)
(*c20)
X. タランテラ (イ長調)
(*c21)
[
p]
# 詩曲 (1938, 出版: 1940)
[
p]
# 古典組曲(組曲第1番) (*c22) (1943, 出版: 1946)
I. 前奏曲 (ハ短調)
II. メヌエット (変イ長調)
III. ガヴォット (変ホ長調)
IV. エア (ト長調)
V. ジーグ (変ロ長調)
[
p]
# 水彩画 (*c17) (1946, 出版: 1947) [sd] [sd]
I. 水彩画 (ヘ長調)
II.
* マズルカ (イ短調)
III. バガテル (ト長調)
IV.
* 寓話 (二短調) [y] [y] [y]
V. 間奏曲 (イ短調)
VI. メヌエット (変ロ長調)
VII.
* スケルツォ (ホ短調)
VIII. ノヴェレッテ (イ長調)
IX. ワルツ (ハ長調)
[
p]
# 変奏曲 ロ短調 (1949, 出版: 1950) [y] [sd]
#* ロシア民謡に基づく8つの小品 (1949, 出版: 1950) [sd]
I. 歌 (ハ長調)
II. お伽噺 (イ短調)
III. ワルツ (ホ短調)
(*c23)
IV. マズルカ (ト長調)
V. ポルカ (ハ長調)
VI. 子守歌 (へ短調)
VII. 行進曲 (ヘ長調)
VIII. フィナーレ (ハ長調)
# ピアノ・ソナチネ 第1番 ホ短調 (1950, 出版: 1951) * 3楽章制 [sd]
1st mvt. Allegro moderato (ホ短調)
2nd mvt. Andante (イ長調)
3rd mvt. Presto (ホ長調)
[
p]
# 少年時代 (1951, 出版: 1953) [sd]
I. 物語 (イ短調)
II. 遊戯 (ハ長調)
[y] [s]
III. 唱歌 (ト短調)
IV. 喜劇 (イ長調)
(*c24)
V. 読書 (ハ長調)
VI. 人形 (嬰ハ短調)
VII. 角笛 (変ロ長調)
VIII. 冬の情景 (二短調)
IX. ピオネール
(*c25) の行進 (ホ長調)
# ピアノ・ソナチネ 第2番 変ロ短調 (1954, 出版: 1956) * 4楽章制 [sd]
1st mvt. Allegro (変ロ短調)
2nd mvt. Andantino (ト短調)
3rd mvt. Allegro (ト長調)
4th mvt. Vivo (変ロ長調)
#* ピアノ・ソナチネ 第3番 『青少年のための』ハ長調 (1956, 出版: 1957) * 単一楽章
# 組曲 第2番 (1956, 出版: 1958) [sd]
I. 献呈 (イ短調)
II. バーレスク (ト長調)
III. マズルカ (ニ長調)
IV. パストラーレ (変ト長調)
V. 舞曲 (ト長調)
VI. カンツォーネ (ニ長調)
VII. ロンド (ヘ長調)
[
p]
#* 古典形式によるソナタ(ピアノ・ソナタ 第1番) [*2] (1959, 出版: 1960) [sd]
1st mvt. Allegro molto (ハ短調)
2nd mvt. Andantino poco capriccioso (ト長調)
3rd mvt. Vivace (ハ長調)
#* 3つの小品 (1960, 出版: 1966)
I. スケルツォ (変ロ長調)
II. 民謡 (嬰へ短調)
III. ポルカ (ハ長調)
# 『学生生活』 (1960)
No. 1 : 冬の夕方 (イ長調)
No. 2 : 練習曲 (ホ短調)
No. 3 : 魂揺さぶるメロディ (ハ短調)
No. 4 : ともに元気よく (ニ長調)
No. 5 : 春が来た (変ロ長調)
No. 6 : ハッピーバースデイ (変ニ長調)
No. 7 : 日曜日の午後 (ハ長調)
[
p]
# 全調による子供のための 24の小品『おはようからおやすみまで』 (1961, 出版: 1963) [sd]
No. 1 : 朝の授業 (in C major)
No. 2 : 歌 (in A minor)
No. 3 : ドラマーの先頭で (in G major)
No. 4 : 英雄の追憶に (in E minor)
No. 5 : 散歩に出かけよう (in D major)
No. 6 : 哀しきメロディ (in B minor)
No. 7 : ホタル (in A major)
* No. 8 : ある騎士のバラード (in F sharp minor)
No. 9 : 夏の朝 (in E major)
No.10 : 夢 (in C sharp minor)
No.11 : 深刻な小品 (in B major)
* No.12 : 白百合 (in G sharp minor)
* No.13 : ツバメ (in G flat major)
No.14 : いじめっ子 (in E flat minor)
No.15 : 幻想的な行軍 (in D flat major)
No.16 : 雪のかけら (in B flat minor)
No.17 : 物語 (in A flat major)
No.18 : 勇者の踊り (in F minor)
No.19 : トランペットの音 (in E flat major)
No.20 : 御伽噺 (in C minor)
No.21 : 散歩 (in B flat major)
No.22 : 古い町で (in G minor)
No.23 : わんぱくな子 (in F major)
No.24 : 斜陽 (in D minor)
# ピアノ・ソナチネ 第4番 『叙事』イ短調 [*3] (1964, 出版: 1971) * 単一楽章制 [s] [s] [d] [sd]
# 10の演奏会用練習曲 (*c26) (1964-67, 出版: 1966&1969)
[第1集]
[s] [sd]
No. 1 : イ短調 (Allegro molto)
[y] [y]
No. 2 : ニ短調 (Allegro)
No. 3 : ハ長調 (Allegro molto)
No. 4 : イ長調
[*4] (Moderato)
[y] [y]
No. 5 : ヘ音のミクソリディアン
[*4] (Allegro agitato)
[第2集]
No. 6 : ハ長調 (Allegro ma non troppo)
No. 7 : ホ短調 (Allegro vivo)
No. 8 : ヘ長調 (Allegro)
No. 9 : ト短調 (Moderato)
(*c4)
No. 10 : ハ長調 (Allegro molto)
[ 3つの小品 ] (1968, 出版: 1969)
・[
p]
# 『演奏会用ワルツ』 (*c2)
・
# 『困惑』
・『タンゴ』
# 民謡に基づく 10の小品 (1969, 出版: 1973)
No. 1 :
* メロディ (ベラルーシ民謡) (イ短調)
No. 2 :
* 結婚式の歌 (チュヴァシ民謡) (ニ長調)
No. 3 :
* 唱歌 () (ヘ長調)
No. 4 : 聞き古し唄 (ベラルーシ民謡) (ホ短調)
No. 5 : まきばの散歩 () (ヘ長調)
No. 6 : タタール人の踊り (ト長調)
No. 7 :
* なぜあなたは声を殺して泣くの? (ロ短調)
No. 8 :
* ロシアの歌 (イ短調)
No. 9 : 群衆に集いし少女たち () (ホ短調)
No.10 : ベラルーシ民謡の主題による変奏曲 (イ短調)
変奏曲 ヘ長調 (1969, 出版: 1971)
[ 2つの小品 ] (1969, 出版: 1970)
・
# フォックストロット (*c15)『君と』
・
# 速いワルツ『ハーディ=ガーディ (*c27) 』
[ 2つの小品 ] (1970, 出版: 1971)
・
# ブルース『日陰の公園にて』
・
# ブギウギ
[ 2つの小品 ] (1970, 出版: 1972)
・
# 『上機嫌』
・
# 『陽気なピエロ』
# 三部作 (1970, 出版: 1972) [sd]
I. 前奏曲 (イ短調)
II. 間奏曲 (ヘ長調)
III. グロテスク (ハ長調)
# ピアノ・ソナチネ 第5番 『青少年のために』ハ長調 (1970, 出版: 1975) * 単一楽章
# ピアノ・ソナチネ 第6番 『御伽噺』 ハ長調 (1970, 出版: 1971) * 単一楽章
# 子供のための 6つの小品 (1971, 出版: 1971)
I. 踊りましょう! (ハ長調)
II. 河で歌おう (ト長調)
III. 郭公 (ハ長調)
IV. 小さな悲しみ (イ短調)
V. 秋 (イ短調)
VI. 陽は輝く (ヘ長調)
# ピアノ・ソナチネ 第7番 『春』 (1972, 出版: 1973) * 単一楽章
# ピアノ・ソナチネ 第8番 『ロンド』 (1972, 出版: 1973) * 単一楽章
# ピアノ・ソナチネ 第9番 『ロマンティック』 (1972, 出版: 1974) * 単一楽章
# ピアノ・ソナチネ 第10番 『バラード』 (1972, 出版: 1974) * 単一楽章
# ピアノ・ソナチネ 第11番 『子供のために』 ニ短調 (1968, 出版: 1975) * 単一楽章
# ピアノ・ソナチネ 第12番 『ささやか』 ハ長調 (1968, 出版: 1975) * 単一楽章
[
p]
# ピアノ・ソナタ 第2番 (*c28) イ短調 (1973, 出版: 1979) [sd]
組曲 第3番 (1973, 出版: 1975)
4つの小品 (1973, 出版: 1974)
I. 雨のしずく
II. 5本の指
III. 早いほどいい
IV. オクターブ (練習曲)
[
p]
# 7つの肖像 (1974, 出版: 1976)
I. 空想家 (ト長調)
II. 悲哀 (イ短調)
III. 乱暴者 (変ロ長調)
IV. 無頓着 (ト長調)
V. 深刻 (ハ長調)
VI. おしゃれさん (ト長調)
VII. 憤慨 (ト短調)
[
p]
# 4つの練習曲 (1974, 出版: 1983)
I. 小川 (ヘ長調)
II. チャイム (ハ長調)
III. 舟で(海にて) (イ短調)
IV. グロテスク (ホ音のフリジアン)
# ピアノ・ソナチネ 第13番 (変ホ長調)[*4] (1974)
# ピアノ・ソナチネ 第14番 ト長調 (1975?)
# ピアノ・ソナチネ 第15番 (1975?)
# ピアノ・ソナチネ 第16番 ハ長調 (1975?)
# アンダンティーノ (1980)
[
p]
# 幻想ワルツ ト長調 (1983)
# ダンス=カプリース (1983?)
# シンコペイテッド・ダンス (1983?)
# 遅いワルツ
# 秋のワルツ
#
2台ピ ア ノ の た め の 作 品
2台ピアノのための 舞曲組曲 (1934, 出版: 1950)
# 2台ピアノのための 3つの小品 (1946, 出版: 1948)
I. ユーモレスク (ニ長調)
II. ワルツ (変ト長調)
III. ポルカ (ヘ長調)
2台ピアノのための 4つの小品 (1957, 出版: 1959)
I.
# 瞑想的な歌 (へ短調)
II.
# 陽気な民謡 (変イ長調)
III. 叙情的なワルツ
IV. 舞曲
[y]
2台ピアノのための 3つの小品 (1960, 出版: 1963)
I. セレナード
II. アンダンティーノ
III. ロンド
4手連弾のための 9つの小品 (出版: 1978)
No. 1 : 小さなワルツ
# No. 2 : 散歩中
No. 3 : 夢想
# No. 4 : 御伽噺の行列
No. 5 : 物悲しく鳴り響いて
No. 6 : 遊戯室
No. 7 : マズルカ
No. 8 : メロディ
No. 9 : ロシアの踊り
# 4手連弾のための 3つの小品 (1986-87, 出版: 1987?)
I. 気まぐれ (1987) (イ短調)
II. スタジアムにて (1987) (へ音のミクソリディアン)
III. 同世代 (1986) (ハ長調)
# 連弾のための 『おばあちゃんのワルツ』
# 連弾のための 『子どものワルツ』
# 連弾のための『小さなワルツ』
ヴ ァ イ オ リ ン と ピ ア ノ の た め の 作 品
[
p]
#* 即興 (1937, 出版: 1938)
[
p]
#* 小スケルツォ (1937, 出版: 1939) [sd]
[
p]
#* 詩曲 (1943, 出版: 1945)
[
p]
# ロマンス (*c29) (1943, 出版: 1970)
# ヴォカリーズ (*c30) (1946, 出版: 1952)
[
p]
#* ヴァイオリン・ソナタ 第1番 ホ短調 (1951, 出版: 1952) [sd]
15の小品 『青少年のために』 (1958, 出版: 1959)
I. 説話
II. 春の雪解け
III. 雪のかけら (小さなワルツ)
IV. 本の前に
V. プロムナード
VI. 聖歌
VII. エチュード=スケルツォ
VIII. 面白い遊び
IX. 御伽噺
X. 思い出 (Waltz)
XI. 唱歌
XII. ワルツ
XIII. マズルカ
XIV. タランテラ
XV. ヴォカリーズ (無言歌)
[
p]
# 2台のヴァイオリンとピアノのための 5つの小品 (1959, 出版: 1960) [sd]
I. ノヴェレッテ
II. アラベスク
III. 行進曲
IV. 舟歌
V. セレナード
2台のヴァイオリンとピアノのための 5つの小品 第2集 (1963, 出版: 1964)
[sd]
I. ピオネール
(*c24) 賛歌
II. 学校(教育用)ワルツ
[y]
III. 休日に
IV. ボートに乗って
[y]
V. 作業用
ヴァイオリン・ソナチネ 第1番 (1964, 出版: 1966)
[
p]
#* ヴァイオリン・ソナチネ 第2番 (1965, 出版: 1967) [sd]
1st mvt. Allegro moderato
2nd mvt. Allegro scherzando
3rd mvt. Allegro
[
p]
#* 三部作 (ヴァイオリン・ソナチネ 第3番) (*c31) (1968, 出版: 1970) [sd]
1st mvt. Allegro
2nd mvt. Moderato
3rd mvt. Vivo
3つのメロディ (1971, 出版: 1973)
[
p]
# 7つのメロディ (1971, 出版: 1974) [sd]
[
p]
#* ヴァイオリン・ソナタ 第2番 (1974, 出版: 1976)
# 24の調性による小品集 (1984)
[
p]
# 12の平易な小品 (*c32) (出版: 1988) [sd]
I. 物語
[y]
II. 小さなワルツ
III. Thawed Patches in the Wood
IV. プロムナード
[y] [y]
V. 陽気な遊び
(*c24)
VI. ワルツ
(*c19)
VII. タランテラ
(*c21)
VIII. マズルカ
(*c20)
IX. 思い出 (ワルツ)
(*c23)
X. ヴォカリーズ
(*c30) [y] [y] [y]
XI. 前奏曲
XII. ワルツ=スケルツォ
ヴ ィ オ ラ と ピ ア ノ の た め の 作 品
『御伽噺』 (1930, 出版: 1954)
チ ェ ロ と ピ ア ノ の た め の 作 品
[
p] 詩曲 (1942, 出版: 1943)
[y] [sd]
3つの小品 (1942, 出版: 1946)
[sd] [sd]
I. ワルツ
II. ユーモレスク [
y]
III.
* カンツォネッタ
ロマンスとセレナーデ [2つの小品] (1943, 出版: 1946)
[sd] [sd]
・ロマンス
(*c29) [
y]
・セレナーデ [
y]
9つの小品 (1959, 出版: 1961)
[d]
I. Dedication
II. Lyrical Waltz
[s]
III. Intermezzo
[s]
IV. Scherzino
[s]
V. Sad Song
VI. Russian Danse
[y]
VII. Melody
[s]
VIII. Arabesque
IX. Mazurka
8つの小品 『春がやって来た』
(*c33) (1962, 出版: 1964)
・朝
[y]
2つの簡単な小品 (1970, 出版: 1971)
変奏曲 ヘ長調 (1972, 出版: 1974)
ロシア舞曲
[y]
コ ン ト ラ バ ス と ピ ア ノ の た め の 作 品
ロマンス
(*c29) (1943, 出版: 1951)
弦 楽 と ピ ア ノ の た め の 作 品 (*c34)
チェロ合奏とピアノのための小品 (1964, 出版: 1966)
[sd]
I. メロディ
[y]
II. 間奏曲
III. 夜想曲 [
y]
IV. 序曲
V. セレナード
[y] [y]
チェロ四重奏 第1番 (1984)
[d] [s] [sd] [sd]
1st mvt. Allegro moderato
2nd mvt. Vivo
3rd mvt. Andante maestoso
4th mvt. Commodo
5th mvt. Allegro con fuoco
チェロ四重奏 第2番 (1986)
[d] [s]
ハープ と ピ ア ノ の た め の 作 品
ハープ・ソナチネ 第1番 (1965, 出版: 1966)
ハープ・ソナチネ 第2番 (1970, 出版: 1971)
ハープ・ソナチネ 第3番 (1971, 出版: 1972)
民話 (1972 pub.1974)
管 楽 器 の た め の 作 品
木管四重奏のための 3つの細密画 (1929, 出版: 1948)
I. 行進曲
II. 子守歌
III. ペトルーシュカ (パセリ)
# クラリネットとピアノのための ヴォカリーズ (*c30) とロシアの歌 (1946, 出版: 1953)
・ヴォカリーズ
[y]
フルートとピアノのための 3つの小品 (1946, 出版: 1955)
[sd]
I. バガテル
[y]
II. スケルツィーノ
III. ワルツ
ファゴットとピアノのための ヴォカリーズ
(*c30) (1946, 出版: 1955)
[y]
クラリネットとピアノのための 7つの小品 (1950, 出版: 1956)
・歌曲
[y]
・ワルツ
[y]
[
p]
# オーボエ・ソナタ 第1番 (1951, 出版: 1953) [y(1st mvt.) y(2nd mvt.) y(3rd mvt.)] [y (2nd mvt.)] [y (2nd mvt. ; fl&pf arr.)] [y (2nd mvt. ; fl&pf arr.)] [sd]
トランペットとピアノのための メロディ (1951, 出版: 1956)
[sd]
トロンボーンとピアノのための アリア (1954, 出版: 1955)
ファゴットとピアノのための 練習曲 (1955, 出版: 1956)
オーボエとピアノのための 歌 (1955, 出版: 1956)
[y]
オーボエとピアノのための ユーモレスク (1956, 出版: 1957)
[
p]
# クラリネット・ソナタ 第1番 (1956, 出版: 1958) {[y (1st mvt.)] [y (2nd mvt.)]} [y (2nd mvt.)] [sd]
# トランペットとピアノのための 組曲 (*c17) (1957, 出版: 1958) [sd]
I. カンツォーナ
II. 間奏曲
[y]
III. ロマンス
* IV. ユーモレスク [y]
トランペットとピアノのための 『ロンド=タランテラ』 (1961, 出版: 1963)
# クラリネット・ソナチネ (1963, 出版: 1969) [y] [sd]
トランペットとピアノのための ヴォカリーズと間奏曲 (1968, 出版: 1970)
# フルート・ソナタ (1970, 出版: 1972) [sd]
# フルート・ソナチネ(1971, 出版: 1972)
ファゴットとピアノのための 5つの小品 (1972, 出版: 1977)
・"Раздумье"
[y]
トランペット・ソナチネ (1973)
# チューバ・ソナチネ (1973, 出版: 1975)
# クラリネット・ソナタ 第2番 (1975, 出版: 1977) [y] [sd]
# オーボエ・ソナタ 第2番 (1978) [d]
1st mvt. Moderato - Allegro
2nd mvt. Andante
3rd mvt. Agitato - Allegro
# チューバとピアノのための ポエム=ファンタジー (1987) [y] [y]
[
p]
# ホルンとピアノのための ヴォカリーズ (*c30) (1946)
# パン・フルートとピアノのための ヴォカリーズ (1950?) [y] [y]
金管五重奏 第1番 (1987)
[d]
金管五重奏 第2番 (1988)
金管五重奏 第3番 (1989)
トランペットとピアノのための ソナタ (1989)
バ ヤ ン (*c35) の た め の 作 品
ワルツとポルカ (1963, 出版: 1964)
行進曲 (1964, 出版: 1965)
マズルカ (1966, 出版: 1968)
幻想曲 (1967, 出版: 1968)
(*c9)
演奏会用小品の形式による 12の民謡 (1969, 出版: 1970)
コントラスト (1969, 出版: 1976)
(無伴奏)バヤン・ソナチネ (1970, 出版: 1971)
# (無伴奏)バヤン・ソナタ (1971, 出版: 1973)
影絵 (1973, 出版: 1975)
曲集『年度』 (1973, 出版: 1976)
2台のチェロとピアノのための メロディ
[y]
# 瞑想曲
# 前奏曲 (D lydian)
# 前奏曲 (C)
# タンゴ
# 我が悲しみ
ド ム ラ (*c36) と ピ ア ノ の た め の 作 品
# ドムラ・ソナタ (1967, 出版: 1969) [http://domranotki.narod.ru/noty_piano14-19.html]
[
p]
# 3つの小品 (*c31) (1968, 出版: 1969)
[
p]
# 幻想曲 (*c9) (1969, 出版: 1971)
『無窮動』 (1973, 出版: 1975)
4つの小品 (1973, 出版: 1975)
I. メリスマ
(*c37)
II. 春
III. 白樺の間で
IV. 瞑想的なワルツ
(*c6)
合 唱 作 品 ( 無 伴 奏 )
ピオネール
(*c138) の行進『ミュード
(*c18) 』 [作詞: P.ネズモナフ
(*p01)] (1930, 出版: 1930)
『ヴォルガ河
(*c39) 下り』 (1940, 出版: 1943)
2つのウクライナ風小品 (1946, 出版: 1951)
I. "Нагадарось старой бабi" (英訳・邦訳不能)
II.
#『おぉ, 樫よ, 樫の木よ (*c40)』 [y] [y] [y] [y] [y] [y] [y]
『春は並木沿いにやって来る』 [作詞: V.ヴィクトロフ
(*p02)] (1970, 出版: 1972)
声 楽 作 品
* 2つのウクライナ民謡 (1940, 出版: 1944)
I.
#『斜陽 (*c41)』 [y]
II. 『あぁ、不幸だ』
# 4つのロマンス (1941, 出版: 1943)
I. 『愛の詞』 [作詞: A.クリロフ]
II.
* 『セレナード』 [作詞: A.フェット]
III. 『エレジー』 [作詞: A.ヤズィコフ]
IV. 『海辺にて』 (もしくは『舟で』) [作詞: H.ハイネ (露訳: N.ロジェストヴェンスキー)]
2つのロマンス (1945, 出版: 1947)
I.
* 『接吻』 [作詞: E.バラツィンスキー]
II.
# 『それでも仰望に悩まされ』 [作詞: F.チュチェフ]
(2つの)ロシア民謡 (1945, 出版: 1946)
I.
#『咲いたよ、咲いた。小さな花が (*c42) (*c43)』 [y] [y] [y]
II. 『空っぽの野原
(*c44)』
ヴォカリーズ 変イ短調
(*c30) (1946, 出版: 1947)
ソビエトの詩人による9つの詩(韻文) (1948, 出版: 1949)
[sd] [sd]
I. 『献身』 [作詞: A.ガルナケリャン
(*p10)]
II. 『庶幾』 [作詞: I.グリシャシュヴィリ]
III.
#『溌剌』 [作詞: A.ガルナケリャン]
IV. 『せせらぎ』 [作詞: A.ガルナケリャン]
V. 『饗宴』 [作詞: S.セヴァーツェフ]
VI. 『君は砂浜, 僕は飛沫』 [作詞: A.ガルナケリャン]
VII. 『誠はあるか?』 [作詞: S.セヴァーツェフ]
VIII. 『心に深くとどめて』 [作詞: A.ガヤモフ]
IX. 『塹壕』 [作詞: I.セオドフ
『絶壁』 [作詞: A.ガルナケリャン] (1949, 出版: 1949)
『春の夜
(*c45)』 [作詞: A.マシストフ] (1950, 出版: 1950)
『世界を見よ』 [作詞: A.マシストフ] (1950, 出版: 1951)
子守唄 [作詞: A.マシストフ] (1950, 出版: 1951)
『夏の夕べ
(*c45)』 [作詞: E.ガルケン] (1950, 出版: 1951)
[
p]
#『森』 (バラード) [作詞: S.セヴァーツェフ] (1950, 出版: 1951)
『調和』 [作詞: A.エリキエフ (露訳: A.ジャロワ)] (1950, 出版: 1952)
『正午』 [作詞: A.マシストフ] (1950, 出版: 1952)
『おはよう、おばかさん!
(*c46)』 [作詞: A.マシストフ] (1950, 出版: 1952)
『冬の日(冬の昼)
(*c45)』 [作詞: G.ニコラエフ] (1950, 出版: 1953)
# 10のヴォカリーズ (1950, 出版: 1952) [sd]
『白樺(カバノキ)』 [作詞: G.ニコラエフ] (1951, 出版: 1952)
『鷹狩り』 [作詞: A.マシストフ] (1951, 出版: 1953)
『ツバメ』 [作詞: M.シハノフ] (1952, 出版: 1953)
『秋』 [作詞: A.マシストフ] (1953, 出版: 1954)
2つの民謡 (1953, 出版: 1954)
I. 『笳
(*c47)』 [原語: リトアニア語 (露訳: E.ヤフニナ)]
II. 『仔ぐまの子守唄』 [原語: ラトビア語 (露訳: V.ヴィンニコフ)]
5つのエストニア民謡 (1957, 出版: 1966)
ロシア/ソビエトの詩人による20のロマンス集 『青少年』 (1961, 出版: 1963)
ソビエトの詩人による6つの歌 『風のロマンス』 (1963, 出版: 1965)
I. 『風のロマンス』 [作詞: Y.ハレツキー]
II. 『それでも私は信じてる…』 [作詞: Y.ハケツキー]
III. 『忘れないで…』 [作詞: Y.ハケツキー]
IV. 『わが街-わがモスクワ』 [作詞: Y.ポルーヒン]
V. 『18歳の少年』 [作詞: A.ガイコヴィチ]
VI. 『キミはモホヴァヤ暮らし』 [作詞: V.クゼツォフ]
ソビエトの詩人による8つの歌 『キミと…』(1963, 出版: 1963)
・
# Снова Сердца Стук
『冴えたタカ』
[y]
ピ ア ノ 伴 奏 つ き 二 重 唱
ソプラノとバリトンのための『平和のハト』 [Lyric: K.Akustia] (1963, 出版: 1964)
# ソプラノとバリトンのための『静かなうた』 [Lyric: U.Poluxhin] (1965, 出版: 1968)
ソプラノとメゾ・ソプラノのための『春』 [Lyric: F.Tyutchev] (1966, 出版: 1968)
楽器法試験課題曲(集)
(*c48) (1967-74, 出版: 1975)
***************************************************
For Symphony Orchestra and String Orchestra
Scherzo (1930 pub.1936)
Suite alla Mari (1931 pub.1933)
* Dance Suite (1934 pub.1938)
I. Uzbek Dance
II. Armenian Dance
III. Tatar Dance
IV. Tajik Dance
V. Finale
* Symphony No. 1 in D major (1940 pub.1947 rev.1958)
* Heroic March (1942 pub.1948)
* Concert Waltz (1946 pub.1948)
Russian Overture (1947 pub.1948)
"In the steppes of Kazakhstan" (1947 pub.1948)
* Concert Suite (1949 pub.1951)
I. March
II. Mazurka
III. Melody
IV. Dance
V. Waltz
VI. Finale
Ballet Suite (1951 pub.1952)
Lyrical Melody (1951 pub.1952)
* Symphony No.2 in F major "Pour la Jeunesse" (1957 pub.1961) [y]
* Symphonietta in G minor for string orchestra (1958 pub.1961) [y] [y]
* Symphony No. 3 in C major "Little Symphony" for string orchestra (1962 pub.1964) [y] {[y] [y] [y] [y]}
* "Summer Days" 5 Pieces for string orchestra (1969 pub.1971)
I. The Morning
II. On the Lake (Waltz)
III. Athletic March
IV. Walk in the Meadows
V. Night Games
* 2 Waltzes (1973)
No. 1: Festive Waltz
No. 2: Meditative Waltz
Symphony No. 4 (1973)
Romantic Waltz (Waltz No. 3?) for symphonic orchestra (1977)
12 Pieces for string orchestra (1977)
No. 1: Prelude
No. 2: Game of Glare
No. 3: Intermezzo
No. 4: Humoresque
No. 5: Bagathold
No. 6: Serenade
No. 7: Chant
No. 8: Mazurka
No. 9: Evening Song
No.10: Scherzo
No.11: Melody
No.12: March
* Poem No. 1 "Strong in Spirit" for strings orchestra (1979)
* Poem No. 2 for strings orchestra (1981)
* Waltz No. 4 "Elegy" in D minor for symphonic orchestra
Pieces on the Verses of Basse
[y (I)] [y (V)] [y (VI)] [y (VII)]
For Soloist and Orchestra
#* Concerto No. 1 in E minor for violin and orchestra (1944 pub.1946 [Vn+Pf 1952]) [y] {[y] [y] [y]} {[y] [y] [y]}
#* Concertino in D minor for violin and orchestra (1960 pub.1961)
#* Concerto No. 2 in A minor for violin and orchestra (1954-63 pub.1970) [y]
4 Pieces for 2 violins and orchestra (1964 pub.1965)
#* Concerto-Fantasy in G minor for clarinet and orchestra (1968 pub.1971)
#* Concerto No. 1 for piano and orchestra (1969 pub.1974 [Pf+Pf 1971]) [y]
#* Concerto No. 2 for piano and orchestra (1969 pub.1974 [Pf+Pf 1971]) [y]
# Concerto No. 3 for piano and orchestra (1977/73?)
# Concerto No. 4 for piano and orchestra (1977)
Poem for cello and orchestra
[y]
Concerto for oboe and string orchestra (1986)
Concerto for clarinet and orchestra (1986)
Lirical Poem for english horn and string orchestra
For Concert Band
Combat March (1930 pub.1932)
Intermezzo on the theme of Kazakhstan folksong (1931 pub.1932)
Suite No. 1 (1933 pub.1938)
Suite No. 2 (1940 pub.1947)
March "For the Motherland" (1941)
Pilot March (1941 pub.1948)
March "In the attack" (1942)
* March "Tanker (Tank Driver)" (1942 pub.1947)
March "Heroism" (1943)
Spring Overture (1952 pub.1958)
March "Friendship of Peoples" (1956 pub.1957)
Russian Overture (1960 pub.1961)
Prelude (1975 pub.1976)
# "Toward the Season" Concert March
For Russian Folk Orchestra
Round-dance and Plyasovaya (1949 pub.1950)
Plangent (1949 pub.1949)
Variations on the theme of Russian folk song (1949)?
8 Pieces (1951 pub.1956)
Overture (1952 pub.1954)
Suite [4 Pieces] (1965 pub.1967)
Silhouette [10 Pieces] (1974)
For Jazz Orchestra
Combat March (1930 pub.1937)
March-Cortege (1930 pub.1937)
Tatar Dance (1933 pub.1935)
Gallop (1939 pub.1948)
* Serenade (1942 pub.1956) [y]
Tango (1942 pub.1956)
*Slow Dance (1942 pub.1950) [y]
Scherzo-Galiop (1949 pub.1949)
Day-off March (1949 pub.1949)
# Athletic March (1949 pub.1950)
Russian Beach (1949 pub.1952)
Lyrical Waltz (1949 pub.1952)
Mazurka (1949 pub.1954)
Dance (1949 pub.1953)
"Russian Game" (1951 pub.1954)
Waltz (1954 pub.1954)
Slow Foxtrot (1968 pub.1969)
"Minx" (1970 pub.1972)
Bossa-Nova (1970 pub.1972)
"Together" (1970 pub.1973)
"The Joy of Meeting" (1972 pub.1974)
[y]
# Anthient Waltz
# "Bylina"
# "Winter Promnade"
For Piano
# Dance (1929 pub.1930)
# 2 Etudes (1929 pub.1930)
I. in A minor
[y (MIDI)]
II. in E minor
[y] [y]
# 4 Child's Pieces (1929 pub.1937)
I. Lullaby
II. March
III. Story
IV. Parsley
# 4 Preludes, Op. 6 (1930 pub.1933)
I. in C major
II. in G major
III. in F minor
IV. in D minor
# Lyrical Pieces (1935 pub.1937)
I. in C major
II. in C major
III. in A minor
IV. in C major
# 2 Mari Pieces (1936 pub.1937)
I. in A minor
II. in F minor
# 5 Preludes (1936 pub.1940)
I. in C major
II. in A minor
III. in E minor
IV. in D major
V. in B minor
# 10 Novellettes (1937 pub.1938)
I. Humoreska (in E minor)
II. Legenda (in C major)
III. Arabeska (in G major)
IV. March (in B flat minor)
V. Novelletta (in E flat major)
VI. Waltz (in F sharp minor)
VII. Scherzo (in D minor)
VIII. Song (in B flat major)
IX. Mazurka (in B minor)
X. Tarantella (in A major)
# Poem (1938 pub.1940)
# Classical Suite (1943 pub.1946)
I. Prelude in C minor
II. Menuet in A flat major
III. Gavotte in E flat major
IV. Air in G major
V. Gigue in B flat major
# Aquarelles (Watercolors) (1946 pub.1947)
I. Aquarelle (in F major)
II.
* Mazurka (in A minor)
III. Bagatelle (in G major)
IV.
* Legende (in D minor) [y] [y] [y]
V. Intermezzo (in A minor)
VI. Minuet (in B flat major)
VII.
* Schrzo (in E minor)
VIII. Novelette (in A major)
IX. Waltz (in C major)
# Variations in B minor (1949 pub.1950) [y]
#* 8 Pieces on theme of Russian folksong (1949 pub.1950)
I. Song (in C major)
II. Fairy Tale (in A minor)
III. Waltz (in E minor)
IV. Mazurka (in G major)
V. Polka (in C major)
VI. Berceuse (in F minor)
VII. March (in F major)
VIII. Conclusion (in C major)
# Sonatine No. 1 in E minor (1950 pub.1951)
1st mvt. Allegro moderato (in E minor)
2nd mvt. Andante (in A major)
3rd mvt. Presto (in E major)
# Chirldren Days (1951 pub.1953)
I. A Tale (in A minor)
II. Playing Games (in C major)
[y]
III. A Song (in G minor)
IV. Happy Entertainment (A Jolly Show) (in A major)
V. Reading a Book (in C major)
VI. Mannequins (in C sharp minor)
VII. The Horn Player (in B flat major)
VIII. A Winter Scene (in D minor)
IX. March of the Pioneers (in E major)
# Sonatine No. 2 in B flat minor (1954 pub.1956)
1st mvt. Allegro (in B flat minor)
2nd mvt. Andantino (in G minor)
3rd mvt. Allegro (in G major)
4th mvt. Vivo (in B flat major)
# Sonatine No. 3 "Humoresque" in C major (1956 pub.1957)
* Suite No. 2 (1956 pub.1958)
I. Degication in A minor
II. Burlesque in G major
III. Mazurka in D major
IV. Pastorale in E flat minor
#* Sonata in classical style (Piano Sonata No. 1 in C minor) (1959 pub.1960)
1st mvt. Allegro molto (in C minor)
2nd mvt. Andantino poco capriccioso (in G major)
3rd mvt. Vivace (in C major)
#* 3 Pieces (1960 pub.1966)
I. Scherzo (in B flat major)
II. Ditty (in F sharp minor)
III. Polka (in C major)
# "Schoole Years" (1960)
No. 1 : Winter Evening (in A major)
No. 2 : Etude (in E minor)
No. 3 : Soulful Melody (in C minor)
No. 4 : Cheerfully Together (in D major)
No. 5 : Spring is coming (in B flat major)
No. 6 : Happy Birthday (in D flat major)
No. 7 : Sunday Afternoon (in C major)
#* 24 Children's Pieces in all keys (1961 pub.1963)
No. 1 : Morning Lesson (in C major)
No. 2 : Song (in A minor)
No. 3 : Ahead of Drummer (in G major)
No. 4 : In Memory of Hero (in E minor)
No. 5 : Setting off for a Walk (in D major)
No. 6 : Sad Melody (in B minor)
No. 7 : Fireflies (in A major)
No. 8 : A Knight's Ballade (in F sharp minor)
No. 9 : Summer Morning (in E major)
No.10 : Dreaming (in C sharp minor)
No.11 : A Serious Piece (in B major)
No.12 : White Lily (in G sharp minor)
No.13 : Swallow (in G flat major)
No.14 : Bully (in E flat minor)
No.15 : Fantastic Procession (in D flat major)
No.16 : Snowflakes (in B flat minor)
No.17 : Narrative (in A flat major)
No.18 : Dance of the Brave (in F minor)
No.19 : Trumpets Sound (in E flat major)
No.20 : Fairy Tale(in C minor)
No.21 : (in B flat major)
No.22 : In the Old Town (in G minor)
No.23 : Naughty (in F major)
No.24 : The Day is Over (in D minor)
Sonatine No. 4 "Lyrical" in A minor (1964 pub.1971)
[d]
# 10 Concert Etude (1964-67 pub.1966&1969) [y (No. 1)] [y (No. 1)] [y (No. 4)] [y (No. 4)] [s]
[Volume 1]
[s] [sd]
No. 1 : Allegro molto (in A minor)
No. 2 : Allegro (in D minor)
No. 3 : Allegro molto (in C major)
No. 4 : Moderato (in /A/ major)
No. 5 : Allegro agitato (in F mixolydian)
[Volume 2]
No. 6 : Allegro ma non troppo (in C major)
No. 7 : Allegro vivo (in E minor)
No. 8 : Allegro (in F major)
No. 9 : Moderato (in G minor)
No.10 : Allegro molto (in C major)
"Confession"
# Concert-Waltz, "Tango" (1968 pub.1969)
# 10 Pieces on folksong (1969 pub.1973)
No. 1 :
* Melody (Belarusian) (in A minor)
No. 2 :
* Wedding Song (Chuvash) (in D major)
No. 3 :
* Song () (in F major)
No. 4 : Tune (Belarusian) (in E minor)
No. 5 : I'm walking in the meadow () (in F major)
No. 6 : Tartarian Dance (in G major)
No. 7 :
* Why are you crying silently? (in B minor)
No. 8 :
* Russian Song (in A minor)
No. 9 : The Girls Gathered in a Crowd () (in E minor)
No.10 : Variations on the Belarusian theme (in A minor)
Variations in F major (1969 pub.1971)
#"With You" Foxtrot,
#"Hurdy-gurdy" Fast-Waltz (1969 pub.1970)
#"In a Shady Park" (blues),
#Boogie-woogie (1970 pub.1971)
# "Good Mood",
# "Cheerful Clown" (1970 pub.1972)
# Triptych (1970 pub.1972)
I. Prelude (in A minor)
II. Intermezzo (in F major)
III. Grotesque (in C major)
# Sonatine No. 5 "Youth" in C major (1971 pub.1975)
# Sonatine No. 6 "Fable" in C major (1971 pub.1971)
# 6 Pieces for children (1971 pub.1971)
I. Let's dance! (in C major)
II. Sing at the river (in G major)
III. Cuckoo (in C major)
IV. Vzgrustnulosi (To feel little sad) (in A minor)
V. Autumn (in A minor)
VI. The Sun is shining (in F major)
# Sonatina No. 7 "Spring" (1972 pub.1973)
# Sonatine No. 8 "Ronde" (1972 pub.1973)
# Sonatine No. 9 "Romantic" (1972 pub.1974)
# Sonatine No. 10 "Ballade" (1972 pub.1974)
# Sonatine No. 11 "For children" in D minor (1968 pub.1975)
# Sonatine No. 12 "Little" in C major (1968 pub.1975)
# Piano Sonata No. 2 (1973)
Suite No. 2 (1973 pub.1975)
4 Pieces (1973 pub.1974)
I. Raindrops
II. Five fingers
III. The sooner the better
IV. Octave (Etude)
# 7 Portraits (1974 pub.1976)
I. The Daydreamer (in G major)
II. Sorrowful (in A minor)
III. The Hellion (in B flat major)
IV. Nonchalant (in G major)
V. Serious (in C major)
VI. The Swank (in G major)
VII. Offended (in G minor)
# 4 Etudes (1974 pub.1983)
I. Creek (in F major)
II. Chimes (in C major)
III. By the Sea (in A minor)
IV. Grotesque (in E Phrygian)
# Sonatine No. 13 in E flat major (1974)
Sonatine No. 14 in G major (1975?)
Sonatine No. 15 (1975?)
# Sonatine No. 16 in C major (1975?)
# Valse-Fantasy in G major (1983)
# Slow Waltz
For 2 Pianos / 4 hands
Dance Suite for 2 pianos(1934 pub.1950)
# 3 Pieces for 2 pianos (1946 pub.1948)
I. Humoresque (in D major)
II. Waltz (in G flat major)
III. Polka (in F major)
4 Pieces for 2 pianos (1957 pub.1959)
I.
# Melancholy Song (in F minor)
II.
# Cheerful Ditty (in A flat major)
III. Lyrical Waltz
IV. The Dance
[y]
3 Pieces for 2 pianos (1960 pub.1963)
I. Serenade
II. Andantino
III. Rondo
# 3 Pieces for 4 hands (1986-87, pub.1988)
I. The Whimsicality (in A minor) (1987)
II. At the Stadium (in F Mixorydian) (1987)
III. The Contemporary (in C major) (1986)
# Waltz for grandmother, for 4 hands
# Waltz for children, for 4 hands
# 9 Pieces for 4 hands (pub.1978)
No. 1 : Little Waltz
No. 2 : On a Walk
No. 3 : Reverie
No. 4 : Fairytale Procession
No. 5 : Plangent
No. 6 : Playroom
No. 7 : Mazurka
No. 8 : Melody
No. 9 : Russian Dance
For Violin and Piano
#* Improvisation (1937 pub.1938)
#* Scherzino (1937 pub.1939)
#* Poem (1943 pub.1945)
# Romance (1943 pub.1970)
# Vocalise (1946 pub.1952)
#* First Sonata (1951 pub.1952)
15 Pieces "Youth" (1958 pub.1959)
I. Storytelling
II. Spring Protalinki
III. Snowflakes (Little Waltz)
IV. Behing the Book
V. Walk
VI. Ingout
VII. Etude-Scherzo
VIII. Fun Game
IX. Fairy Tale
X. Reminiscence (Waltz)
XI. Song
XII. Waltz
XIII. Mazurka
XIV. Tarentella
XV. Vocalise (Romance without Words)
# 5 Pieces for 2 violins and piano (1959 pub.1960)
I. Novelette
II. Arabesque
III. March
IV. Barcarolle
V. Serenade
5 Pieces for 2 violins and piano (1963 pub.1964)
I. Pioneer Regards
II. Scholastic Waltz
[y]
III. In the Holiday
IV. On the Boat
[y]
V. For Work
# Sonatina No. 1 (1964 pub.1966)
#* Sonatina No. 2 (1965 pub.1967)
1st mvt. Allegro moderato
2nd mvt. Allegro scherzando
3rd mvt. Allegro
#* Triptych (Sonatina No. 3) (1968 pub.1970)
1st mvt. Allegro
2nd mvt. Moderato
3rd mvt. Vivo
3 Melodies (1971 pub.1973)
# 7 Melodies (1971 pub.1974)
#* Second Sonata (1974 pub.1976)
# 24 Pices dans tous les tons (1984)
# Easy Pieces (pub.1988)
I. A Story
[y]
II. Miniature Waltz
III. Thawed Patches in the Wood
IV. Promnade
[y] [y]
V. A Merry Game
VI. Waltz
VII. Tarantella
VIII. Mazurka
IX. Recollection (Waltz)
X. Vocalise
[y] [y] [y]
XI. Prelude
XII. Waltz-Scherzo
For Viola and Piano
The Tale (1930 pub.1954)
For Cello and Piano
Poem (1942 pub.1943)
[y]
3 Pieces (1942 pub.1946)
I. Waltz
II. Humoresque
[y]
III.
* Canzonetta
Romance
[y] and Serenade
[y] (1943 pub.1946)
9 Pieces (1959 pub.1961)
[d]
I. Dedication
II. Lyrical Waltz
[s]
III. Intermezzo
[s]
IV. Scherzino
[s]
V. Sad Song
VI. Russian Danse
[y]
VII. Melody
[s]
VIII. Arabesque
IX. Mazurka
8 Pieces "Spring has come" (1962 pub.1964)
・Morning
[y]
2 Easy pieces (1970 pub.1971)
Variation in A major (1972 pub.1974)
For Contrabass and Piano
Romance (1943 pub.1951)
For Strings ensembles and Piano
Pieces for cello-ensemble and piano (1964 pub.1966)
I. Melody
[y]
II. Intermezzo
III. Nocturne
[y]
IV. Overture
V. Serenade
[y] [y]
Quartet No. 1 for 4 cellos [without piano] (1984)
[d] [s]
1st mvt. Allegro moderato
2nd mvt. Vivo
3rd mvt. Andante maestoso
4th mvt. Commodo
5th mvt. Allegro con fuoco
Quartet No. 2 for 4 cellos [without piano] (1986)
[d] [s]
For Harp and Piano
Sonatina No. 1 (1965 pub.1966)
Sonatina No. 2 (1970 pub.1971)
Sonatina No. 3 (1971 pub.1972)
The Tale (1972 pub.1974)
For Wind instrument
3 Miniatures for woodwind quartet (1929 pub.1948)
I. March
II. Berceuse
III. Petrushka (Parsley)
Vocalise and Russian Song for clarinet and piano (1946 pub.1953)
・
# Vocalise [y]
3 Pieces for flute and piano (1946 pub.1955)
I. Bagatelle
[y]
II. Schrzino
III. Waltz
Vocalise for fagot and piano (1946 pub.1955)
[y]
7 Pieces for clarinet and piano (1950 pub.1956)
・Chant
[y]
・Waltz
[y]
# Sonata No. 1 for oboe and piano (1951 pub.1953) [y] [y (2nd mvt.)] [y (2nd mvt. ; fl&pf arr.)] [y (2nd mvt. ; fl&pf arr.)]
Melody for trumpet and piano (1951 pub.1956)
[sd]
Aria for trombone and piano (1954 pub.1955)
Etude for fagot and piano (1955 pub.1956)
Song for oboe and piano (1955 pub.1956)
[y]
Humoresque for oboe and piano (1956 pub.1957)
# Sonata No. 1 for clarinet and piano (1956 pub.1958) {[y (1st mvt.)] [y (2nd mvt.)]} [y (2nd mvt.)]
# Suite for trumpet and piano (1957 pub.1958)
II. Intermezzo
[y]
IV. Humoresque
[y]
Rondo-Taranterlla for trumpet and piano (1961 pub.1963)
# Sonatina for clarinet and piano (1963 pub.1969) [y]
Vocalise and Intermezzo for trumpet and piano (1968 pub.1970)
# Sonata for flute and piano (1970 pub.1972)
# Sonatine for flute and piano (1971 pub.1972)
5 Pieces for fagot and piano (1972 pub.1977)
・Meditation
[y]
# Sonatine for tuba and piano (1973 pub.1975)
Sonatine for trumpet and piano (1973)
# Sonata No. 2 for clarinet and piano (1975 pub.1977) [y]
# Sonata No. 2 for oboe and piano (1978) [d]
1st mvt. Moderato - Allegro
2nd mvt. Andante
3rd mvt. Agitato - Allegro
# Poem-Fantasy for tuba and piano (1987) [y] [y]
# Vocalise for horn and piano
Vocalise for Pan-flute and piano
[y] [y]
Quintet No. 1 ( for brass quintet ) (1987)
[sd]
Quintet No. 2 for brass-quintet (1988)
Quintet No. 3 for brass-quintet (1989)
Sonata for trumpet and piano (1989)
For Bayan
Waltz and Polka (1963 pub.1964)
March (1964 pub.1965)
Mazurka (1966 pub.1968)
Fantasia (1967 pub.1968)
12 Folk Songs in form of concert pieces (1969 pub.1970)
Contrast (1969 pub.1976)
Sonatine (1970 pub.1971)
# Sonata (1971 pub.1973)
Silhouette (1973 pub.1975)
"Schoole Years" (miscellany pieces) (1973 pub.1976)
Melody for 2 cello and bayan
[y]
# Meditation
# Prelude (D lydian)
# Prelude (C)
# Tango
# Melancholy to me
For Domra and Piano
# Sonata (1967 pub.1969)
# 3 Pieces (1968 pub.1969)
# Fantasia (1969 pub.1971)
"In fast motion" (1973 pub.1975)
4 Pieces (1973 pub.1975)
I. Melisma
II. Spring
III. Amang Birches
IV. Meditative Waltz
For Choir with piano accompaniment
"Myud" Pioneer's March [Lyric: P.Neznamov] (1930 pub.1930)
"Down the Volga River" (1940 pub.1943)
2 Ukrainanian Pices (1946 pub.1951)
I. "Нагадарось старой бабі"
II.
# "Oh, Oak, Oakling" [y] [y] [y] [y] [y] [y] [y]
"Spring walks on roads" [Lyric: V.Viktorov] (1970 pub.1972)
For Voice and Piano
* 2 Ukrainanian Folk Songs (for tenor and orchestra) (1940 pub.1944)
I.
# "The Sun Shorty" (or "The Sun Set") [y]
II. "Oh, I'm unhappy"
4 Romances (1941 pub.1943)
I. "Words of Love" [Lyric: A.Krylov]
II.
* "Serenade" [Lyric: A.Fet]
III. "Elegy" [Lyric: N.Yazyikov]
IV. "At the Seaside" ("By the Sea") [Lyric: H.Heine in translation by N.Rodjestvensky]
2 Romances (1945 pub.1947)
I.
* "Kiss" [Lyric: E.Baratsynsky]
II.
# "Still haunted by longing" [Lyric: F.Tutchev]
Russian Folk Songs (1945 pub.1946)
I.
# "Bloomed, Bloomed Little Flower (Bloomed, Blossoms Bloomed)" [y] [y] [y]
II. "Nothing in Field"
Vocalise (1946 pub.1947)
9 Romances Verses of Soviet Poets (1948 pub.1949)
I. "Dedication" [Lyric: A.Garnakeriyan]
II. "Desire" [Lyric: I.Grishashvili]
III.
# "Juvenility" [Lyric: A.Garnakeriyan]
IV. "Rill" [Lyric: A.Garnakeriyan]
V. "Drinking" [Lyric: S.Severtsev]
VI. "You're Beach, I'm Blue Surf" [Lyric: A.Garnakeriyan]
VII. "Are You Faithful?" [Lyric: S.Severtsev]
VIII. "I Kept Deep In My Heart" [Lyric: A.Gayamov]
IX. "In the Trench" [Lyric: I.Seodov]
"The Cliff" [Lyric: A.Garnakeriyan] (1949 pub.1949)
"Spring Night" [Lyric: A.Mashistov] (1950 pub.1950)
"Watch the World" [Lyric: A.Mashistov] (1950 pub.1951)
Lullaby [Lyric: A.Mashistov] (1950 pub.1951)
"Summer Evening" [Lyric: E.Gerken] (1950 pub.1951)
# "The Forest" (Ballade) [Lyric: S.Severtsev] (1950 pub.1951)
"Harmony" [Lyric:A.Erikeev in translation by A.Jarova] (1950 pub.1952)
"The Noon" [Lyric: A.Mashistov] (1950 pub.1952)
"Hello, Flax!" ("Hello, the Lazy!" ?) [Lyric: A.Mashistov] (1950 pub.1952)
"Winter Day" [Lyric: G.Nikolayev] (1950 pub.1953)
# 10 Vocalises (1950 pub.1952)
"The Birch" [Lyric: G.Nikolayev] (1951 pub.1952)
"Flew My Falcon" [Lyric: A.Mashistov] (1951 pub.1953)
"The Swallow" [Lyric: M.Sxhanov] (1952 pub.1953)
"Autumn" [Lyric: A.Mashistov] (1953 pub.1954)
2 Folk Songs (1953 pub.1954)
I. "The Reedpipe" [From Lithuanian, in translation by E.Yaxninoi]
II. "Lullaby-the-little-bear" [From Latbian, in translation by V.Vinnikov]
5 Estonian Songs (1957 pub.1966)
"The Juvenile" 20 Romances Verses of Russian/Soviet Poets (1961 pub.1963)
"Wind Romance"-6 Songs Verses of Soviet Poets (1963 pub.1965)
I. "The Wind of Romance" [Lyric: Y.Khaketsky]
II. "And Yet I Believe …" [Lyric: Y.Khaketsky]
III. "Do not Forget …" [Lyric: Y.Khaketsky]
IV. "My City - My Moscow" [Lyric: Y.Polukhin]
V. "An Eighteen-year-old Boy" [Lyric: A.Gaikovich]
VI. "You lived in Mokhovaya" [Lyric: V.Kuzetsov]
"With You"-8 Songs Verses of Soviet Poets (1963 pub.1963)
・
# Снова Сердца Стук
Lucid Falcon
[y]
For Vocal Duets with Piano
"The Dove of Peace" for soprano and baritone [Lyric: K.Akustia] (1963 pub.1964)
# "The Quiet Song" for soprano and baritone [Lyric: U.Poluxhin] (1965 pub.1968)
"Spring" for soprano and mezzo-soprano [Lyric: F.Tyutchev] (1966 pub.1968)
Problems of Instrumentation (1967-74 pub.1975)
◆ 録 音 ・ 出 版
C D
+
Russian Violin Concertos
![Violinist: Andrew Hardy [Olympia]](../img/rak_cd_01b.jpg)
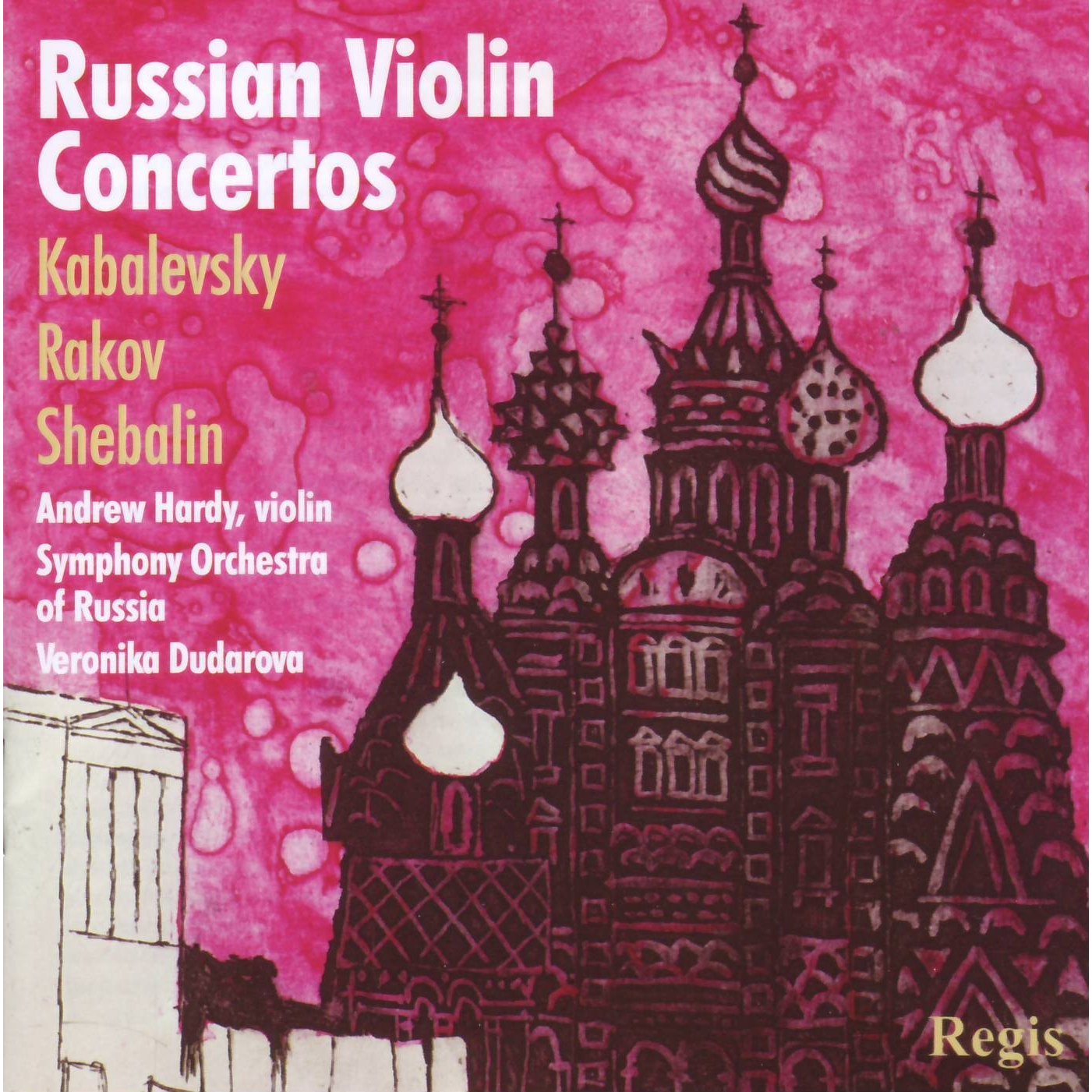
Andrew Hardy (vn) [TR.01-09]
Symphony Orchestra of Russia [TR.01-09]
Veronika Dudarova (cond) [TR.01-09]
1996/06/20 [Olympia], 2009/05/31 [Regin]
★★★☆☆☆
amazon.jp [1]
amazon.jp [2]
hmv
|
01. Violin Concerto No. 1 in E minor: 1st mvt. Allegro (Rakov)
02. Violin Concerto No. 1 in E minor: 2nd mvt. Andante (Rakov)
03. Violin Concerto No. 1 in E minor: 3rd mvt. Allegro molto vivace (Rakov)
04. Violin Concerto in C major, Op. 48: 1st mvt. Allegro molto e con brio (Kabarevsky)
05. Violin Concerto in C major, Op. 48: 2nd mvt. Andante cantabile (Kabarevsky)
06. Violin Concerto in C major, Op. 48: 3rd mvt. Vivace Giocoso (Kabarevsky)
07. Violin Concerto in F major, Op. 21: 1st mvt. Introduzione e fuda (Shebalin)
08. Violin Concerto in F major, Op. 21: 2nd mvt. Aria. Andante (Shebalin)
09. Violin Concerto in F major, Op. 21: 3rd mvt. Rondo. Allegro (Shebalin) |
|
Nikolai Rakov - Violin Sonatas
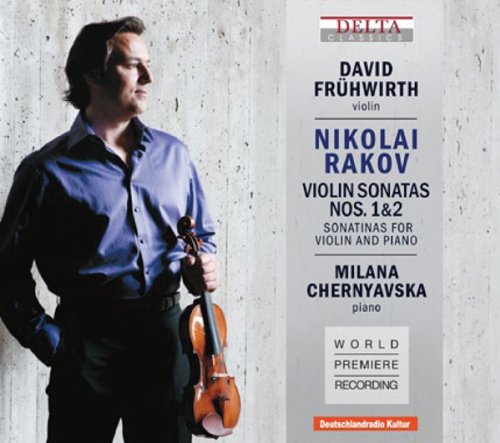
David Frühwirth (vn) [TR.01-15], Milana Chernyavska (pf) [TR.01-15]
2012/05/12
★★★★★☆
amazon.jp
hmv
|
01. 3 Pieces for violin and piano: I. Improvisation. Moderato e molto rubato
02. 3 Pieces for violin and piano: II. Scherzino. Presto
03. 3 Pieces for violin and piano: III. Poem. Andante
04. Sonata No. 2 for violin and piano in G major: 1st mvt. Allegro
05. Sonata No. 2 for violin and piano in G major: 2nd mvt. Andante sostenuto
06. Sonata No. 2 for violin and piano in G major: 3rd mvt. Allegro agitato
07. Sonatina No. 3 for violin and piano "Little Triptych": 1st mvt. Allegro
08. Sonatina No. 3 for violin and piano "Little Triptych": 2nd mvt. Moderato
09. Sonatina No. 3 for violin and piano "Little Triptych": 3rd mvt. Vivo
10. Sonatina No. 2 in D major for violin and piano: 1st mvt. Allegro moderato
01. Sonatina No. 2 in D major for violin and piano: 2nd mvt. Allegro scherzando
02. Sonatina No. 2 in D major for violin and piano: 3rd mvt. Allegro
03. Sonata No. 1 for violin and piano: 1st mvt. Allegro energico
04. Sonata No. 1 for violin and piano: 2nd mvt. Andante sostenuto
05. Sonata No. 1 for violin and piano: 3rd mvt. Allegro giocoso
All composed by N.Rakov |
|
Rakov - Symphony No. 2 "Youth Symphony" & Concert Waltz
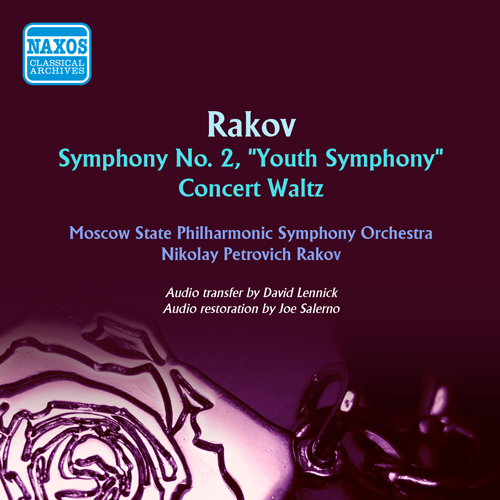
Moscow State Philharmonic Symphony Orchestra [TR.01-05]
Nikolai Rakov (cond) [TR.01-05]
2013/01/08
★★★★☆☆
amazon.jp
|
01. Symphony No. 2 in F major, "Youth Symphony": I. Moderato
02. Symphony No. 2 in F major, "Youth Symphony": II. Vivo
03. Symphony No. 2 in F major, "Youth Symphony": III. Andantino
04. Symphony No. 2 in F major, "Youth Symphony": IV. Allegro giocoso
05. Concert Waltz in A major
All composed by N.Rakov |
|
The Bekova Sisters - ELEGY
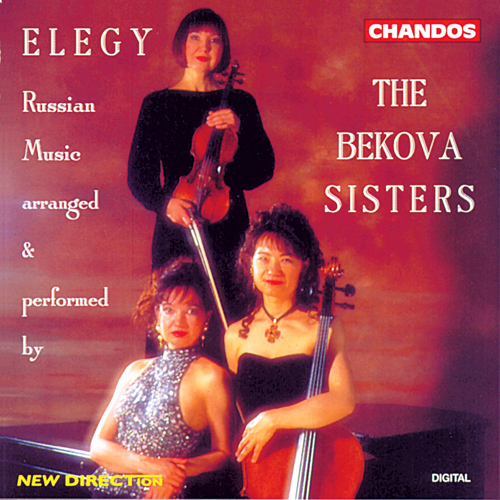
Bekova Sisters [TR.01-17]
1995/05/23
★★★★☆☆
amazon.jp
|
01. Morceaux de fantaisie, Op. 3: No. 1. Elegie in E-Flat Minor (Rachmaninov)
02. 12 Songs, Op. 21: No. 5. Siren' (Lilacs) (Rachmaninov)
03. Romance, Op. 3 (Gliere)
04. The Love for Three Oranges Suite, Op. 33bis: III. March (Prokofiev)
05. Petite Suite: VI. Serenade (Borodin)
06. Voyna i mir (War and Peace), Op. 91: Waltz (Prokofiev)
07. Spartacus: Adagio (Khachaturian)
08. 24 Preludes, Op. 34: No. 6 in B Minor (Shostakovich)
09. Soirees a Saint-Petersbourg, Op. 44: No. 1. Romance in E-Flat Major (A.Rubinstein)
10. Canzonetta (Rakov)
11. Meditation, Op. 14b (Gretchaninov)
12. Petrushka: Scene 4: Russian Dance (Stravinsky)
13. 6 Songs, Op. 38: No. 3. Margaritki (Daisies) (Rachmaninov)
14. Orientale (Shebalin)
15. Yolka (The Christmas Tree), Op. 21: Waltz (Revikov)
16. Chant sans paroles (Song without Words) in F Major, Op. 2, No. 3 (Tchaikovsky)
17. Ne iskushay menya bez nuzhdi (Do not tempt me needlessly) (Glinka)
All arranged by A. Bekova, E. Bekova and E. Bekova for piano trio |
|
Gennady Rozhdestvensky - CD9
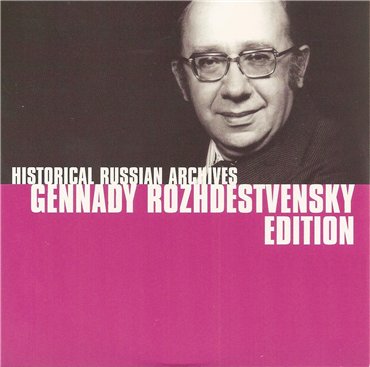
USSR Ministry of Culture Symphony Orchestra [TR.01-04]
State Academy Symphony Orchestra of the USSR [TR.05-10]
USSR State TV and Radio Symphony Orchestra [TR.11-19]
Gennady Rozhdestvensky (cond) [TR.01-19]
****/**/**
★★★★☆☆
hmv
|
01. Symphony No. 3 in C major, Op. 17: I. Allegro assai (Shebalin)
02. Symphony No. 3 in C major, Op. 17: II. Andante (Shebalin)
03. Symphony No. 3 in C major, Op. 17: III. Vovo assai (Shebalin)
04. Symphony No. 3 in C major, Op. 17: IV. Andante - Allegro assai (Shebalin)
05. The Flea - Suite: I. Moderato assai (Shaporin)
06. The Flea - Suite: II. Andante con moto (Shaporin)
07. The Flea - Suite: III. Andantino (Shaporin)
08. The Flea - Suite: IV. Andantino (Shaporin)
09. The Flea - Suite: V. Tempo di valse (Shaporin)
10. The Flea - Suite: VI. Moderato (Shaporin)
11. Sinfonietta for string orchestra: I. Allegro moderato (Rakov)
12. Sinfonietta for string orchestra: II. Allegretto grazioso (Rakov)
13. Sinfonietta for string orchestra: III. Vivo (Rakov)
14. Sinfonietta for string orchestra: IV. Andante sostenuto (Rakov)
15. Sinfonietta for string orchestra: V. Allegro con fuoco (Rakov)
16. Symphony No. 3 in C major for string orchestra: I. Allegro moderato (Rakov)
17. Symphony No. 3 in C major for string orchestra: II. Andante (Rakov)
18. Symphony No. 3 in C major for string orchestra: III. Vivo (Rakov)
19. Symphony No. 3 in C major for string orchestra: IV. Andante sostenuto - Allegro (Rakov) |
|
Sergei Lemeshev - Words of Love
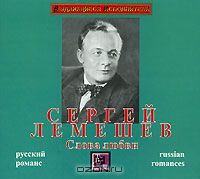
Sergei Lemeshev (tenor) [TR.01-28]
2006
OZON
|
01-18. Various Song
19. "Words of Love" from 4 Romances (Rakov)
20. "Still haunted by longing" from 2 Romances (Rakov)
21-28. Various Song |
|
Anthology Russian Romances, vol. 4
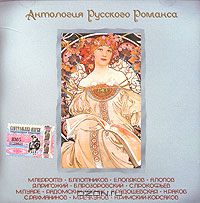
****/**/**
OZON
|
01-19. Various Song
20. "Summer Evening" (Rakov)
21-113. Various Song |
|
Rare Repertoire 1: Violin Concertos
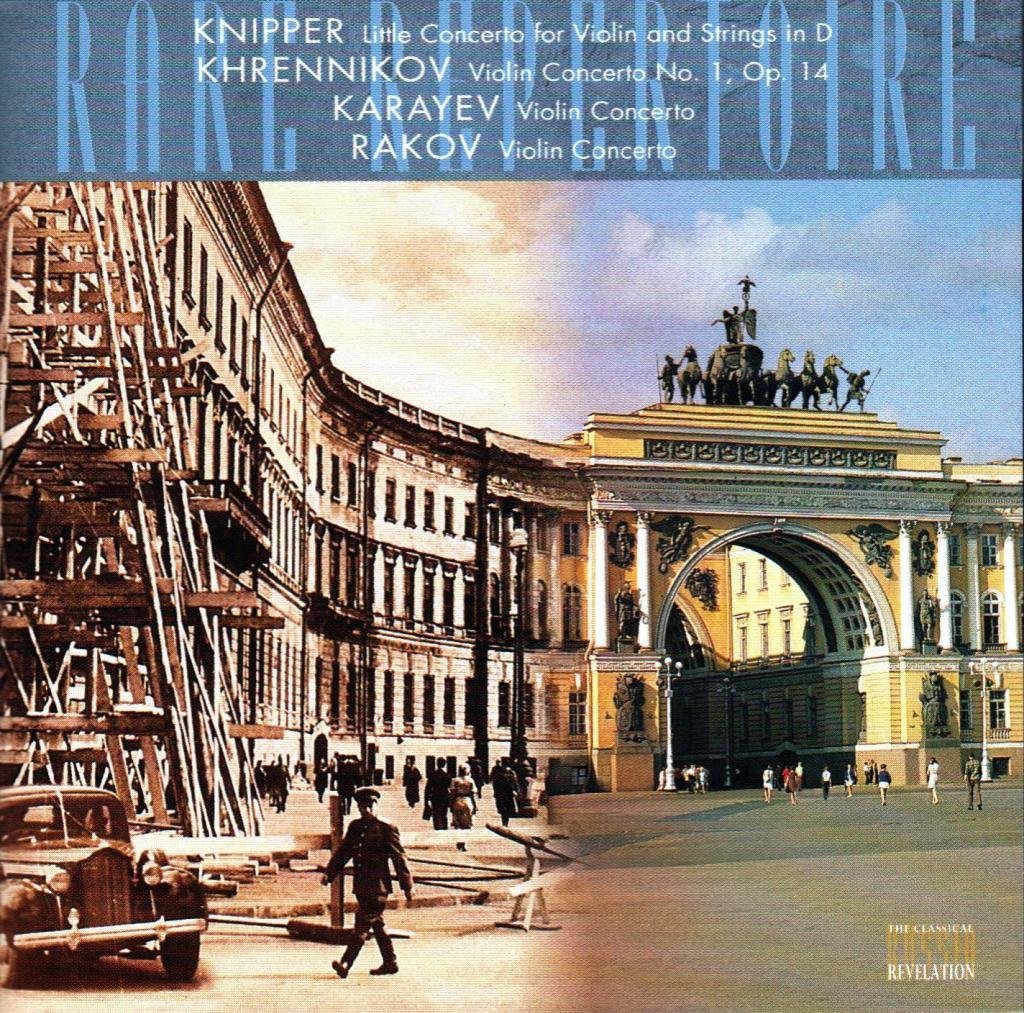
Arkady Futer (vn) [TR.01-03]
Gennadi Rozhdestvensky [TR.01-06]
Members of the Grand Symphony Orchestra of All Union Radio & TV [TR.01-03]
Yako Sato (vn) [TR.04-06]
Grand Symphony Orchestra of All Union Radio & TV [TR.04-09]
Gidon Kremer (vn) [TR.07-09]
Vladimir Kozhukar [TR.07-09]
David Oistrakh (vn) [TR.10-12]
Karl Eliasberg [TR.10-12]
State Symphony Orchestra [TR.10-12]
1998/07/07
amazon.com
|
01. Little Concerto for violin and string orchestra in D: 1st mvt. Allegro (Knipper)
02. Little Concerto for violin and string orchestra in D: 2nd mvt. Adagio (Knipper)
03. Little Concerto for violin and string orchestra in D: 3rd mvt. Vivo (Knipper)
04. Concerto for violin and orchestra No. 1, Op. 14: 1st mvt. Allegro non troppo - Allegro con brio (Khrennikov)
05. Concerto for violin and orchestra No. 1, Op. 14: 2nd mvt. Andante espressivo (Khrennikov)
06. Concerto for violin and orchestra No. 1, Op. 14: 3rd mvt. Allegro agitato (Khrennikov)
07. Concerto for violin and orchestra: 1st mvt. Allegro moderato (Karayev)
08. Concerto for violin and orchestra: 2nd mvt. Andante (Karayev)
09. Concerto for violin and orchestra: 3rd mvt. Allegro ben marcato (Karayev)
10. Concerto for violin and orchestra (No. 1 in E minor): 1st mvt. Allegro (Rakov)
11. Concerto for violin and orchestra (No. 1 in E minor): 2nd mvt. Andante (Rakov)
12. Concerto for violin and orchestra (No. 1 in E minor): 3rd mvt. Allegro moderato (Rakov) |
|
Igor Oistrach - Khachaturian/Rakov: Violin Concertos
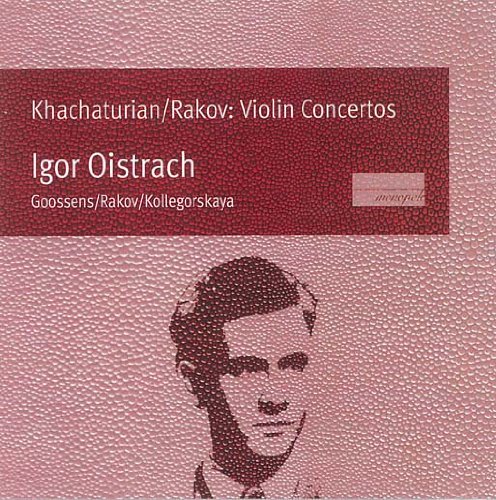
Igor Oistrakh (vn) [TR.01-06]
Eugene Goossens (cond) [TR.01-03]
Philharmonia Orchestra [TR.01-03]
Nikolai Rakov (cond) [TR.04-06]
State Radio Orchestra of the USSR [TR.04-06]
Inna Kollegorskaya (pf) [TR.07-08]
2011/10/25
amazon
Tower Records
amazon.de
|
01. Concerto per violino, Op. 46 [1940]: 1st mvt. (Khachaturian)
02. Concerto per violino, Op. 46 [1940]: 2nd mvt. (Khachaturian)
03. Concerto per violino, Op. 46 [1940]: 3rd mvt. (Khachaturian)
04. Concerto per violino n.1 [1944]: 1st mvt. Allegro (Rakov)
05. Concerto per violino n.1 [1944]: 2nd mvt. Andante (Rakov)
06. Concerto per violino n.1 [1944]: 3rd mvt. Allegro moderato (Rakov)
07: Poema per piano [1927] (Khachaturian)
08: Poeme per cello e piano [1942] (Rakov) |
|
Dokshitser: Scherzo Virtuoso
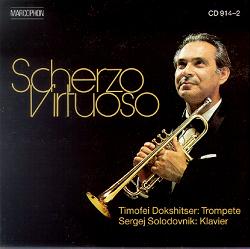
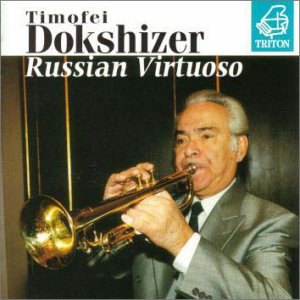
Timofei Dokshitser (tp) [TR.01-15]
Sergei Solodovnik (pf) [TR.01-15]
1996/09/25
★★★★★★
amazon
hmv
楽天
EMR
|
01. Poème N° 1 (Peskin)
02. Präludium (Peskin)
03. Konzert-Etüde (Goedicke)
04. Pionier-Suite - Morgen - Spiele - Abend (Chemberdgi)
05. Konzertscherzo (Arutunian)
06. Romanze (Geifmann)
07. Zwei jüdische Stücke (Geifmann)
08. Scherzo Virtuoso (Jurowski)
09. Etüde (Schelokov)
10. Scherzo (Schelokov)
11. Humoreske (Rakow)
12. Scherzo (Blazhevich)
13. Nordlied (Antjufeew)
14. Scherzo (Djerbashian)
15. Konzertstück (Trotsuk) |
|
Tatiana Lavrova Vol. 2
Recording of Different Periods (1950s)

Tatiana Lavrova (sop) [TR.01-12]
Orchestra of the Leningrad "Maly" Opera Theater [TR.01-04]
Eduard Grikurov (cond) [TR.01, 04]
Yuri Bogdanov (cond) [TR.02,03]
Orchestra of the Russian Folk Instruments [TR.05-09]
Semion Brog (cond) [TR.05]
Avenir Mikhailov (cond) [TR.06-09]
Instrumental Quartet [TR.10]
Orchestra Under Mikhail Volovats [TR.11-12]
Tower Records
amazon.uk
amazon.fr
amazon.de
Russian CD Shop
|
01. Duet of Lakme and Gerald from "Lakme" 1st act (Delibe)
Lakme - Tatiana Lavrova, Gerald - Mikhail Dovenman
02. Scene of Esmeralde and Pheb from "Esmeralde" 1st act (Dargomyzhsky)
Esmeralde - Tatiana Lavrova, Pheb - Vladimir Tchuiko
03. Scene in a prison from "Esmeralde" 1st act (Dargomyzhsky)
Esmeralde - Tatiana Lavrova, Kvasimodo - Alexander Sutiagim
04. Scene and duet from "Lolanthe" (Tchaikovsky)
lolanthe - Tatiana Lavrova, Vodemon - Mikhail Dovenman, Robert - Sergei Shaposhnikov
05. Solveig"s song from music to H. Ibsen"s "Peer Gynt", Op.55 (Grieg)
06. The flower were in blossom (arr. Rakov)
07. Flax (arr. Rakov)
08. Nightingale's Song (Gliere)
09. A Bird (Dyubiuk)
10. Weeping willow (Slovak folk song)
11. Katon's Song from "Kasanova" (Ruzhitsky)
12. Serenade (Toselli) |
|
L P
+ (かなり長いので注意してください…)
Rakov - Concerto for violin

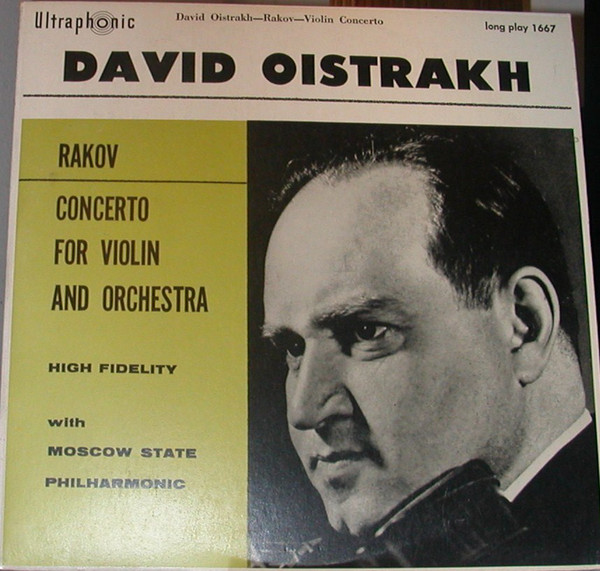
David Oistrach (vn) [TR.01-03]
Kiril Kondrashin (cond) [TR.01-03]
Russian State Symphony [TR.01-03]
1949 / 1956(アメリカ販売)
microgroove record
Discogs
Discogs
|
01. Concerto (No. 1) for violin and orchestra: 1st mvt. Allegro moderato (Rakov)
02. Concerto (No. 1) for violin and orchestra: 2nd mvt. Andante (Rakov)
03. Concerto (No. 1) for violin and orchestra: 3rd mvt. Allegro molto (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
![ГОСТ 5289-56 Д—3224/Д—3225]()
Mikhail Khomitser (vc) [TR.01-06]
Nikorai Rakov (pf) [TR.01-03]
Aleksei Zwibtsev [TR.04-06]
1956
Aprelevskii Zavod
Discogs
Discogs
|
01. Romance for cello and piano (Rakov)
02. Serenade for cello and piano (Rakov)
03. Poem for cello and piano (Rakov)
04. Elegy for cello and piano (Khomitser)
05. Колыбельная (Khomitser)
06. Waltz from ballet "Каменный Цветок" (Khomitser) |
|
![Д—2685/Д—2686]()
Igor Oistrakh (vn) [TR.01-03]
Nikorai Rakov (cond) [TR.01-03]
All-Union Soviet Radio Symphony Orchestra [TR.01-03]
1956
Aprelevskii Zavod
Discogs
|
01. Concerto (No. 1) for violin and orchestra: 1st mvt. Allegro moderato (Rakov)
02. Concerto (No. 1) for violin and orchestra: 2nd mvt. Andante (Rakov)
03. Concerto (No. 1) for violin and orchestra: 3rd mvt. Allegro molto (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
N.Rakov - Symphony No. 1

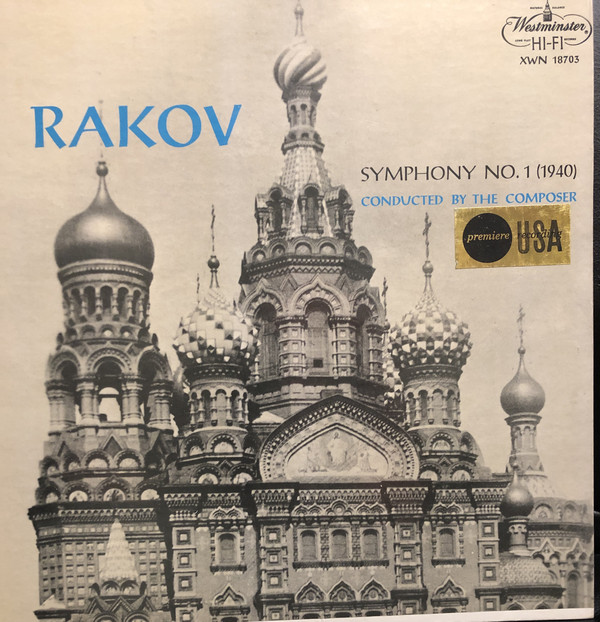
Nikorai Rakov (cond) [TR.01-04]
Moscow State Philharmonic Society Symphony Orchestra [TR.01-04]
1958 / 1964(輸出盤)
Leningradskij Zavod / Melodia / Westminster
Discogs
Discogs
Discogs
Discogs
|
01. Symphony No. 1: 1st mvt. Andante (Rakov)
02. Symphony No. 1: 2nd mvt. Vivo (Rakov)
03. Symphony No. 1: 3rd mvt. Andante molto sostenuto (Rakov)
04. Symphony No. 1: 4th mvt. Moderato - Allegro giocoso (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Rakov, I.Oistrakh - Violin Concerto in E minor
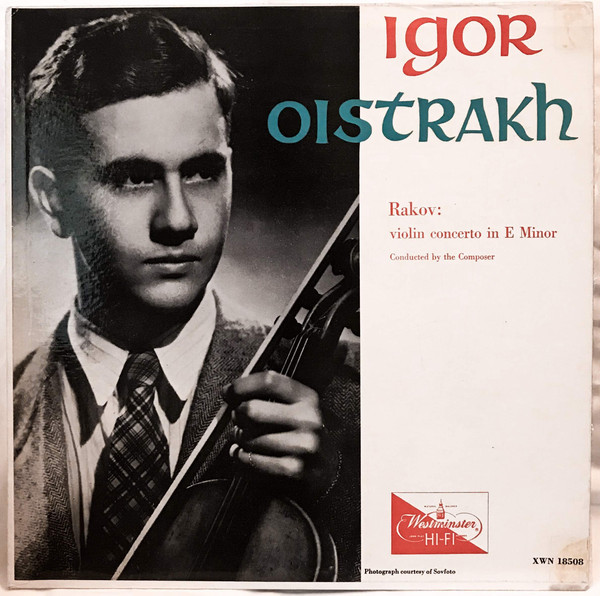
Igor Oistrakh (vn) [TR.01-03, 05-08]
Nikorai Rakov (cond) [TR.01-03]
State Orchestra of USSR [TR.01-03]
Inna Kollegorskaya (pf) [TR.04-08]
1958
Westminster
Discogs
|
01. Violin Concerto in E minor: 1st mvt. Allegro (Rakov)
02. Violin Concerto in E minor: 2nd mvt. Andante (Rakov)
03. Violin Concerto in E minor: 3rd mvt. Allegro molto vivace (Rakov)
04. Etude, Op. 8-11 (Scriabin)
05. Chante Poeme (Khachaturian)
05. Poem in E minor (Rakov)
06. Grave (C.P.E.Bach=Kreisler)
07. Rondo in G major (Mozart=Kreisler) |
|
Shostakovich & Rakov - Violin Concerto played by Oistrakh
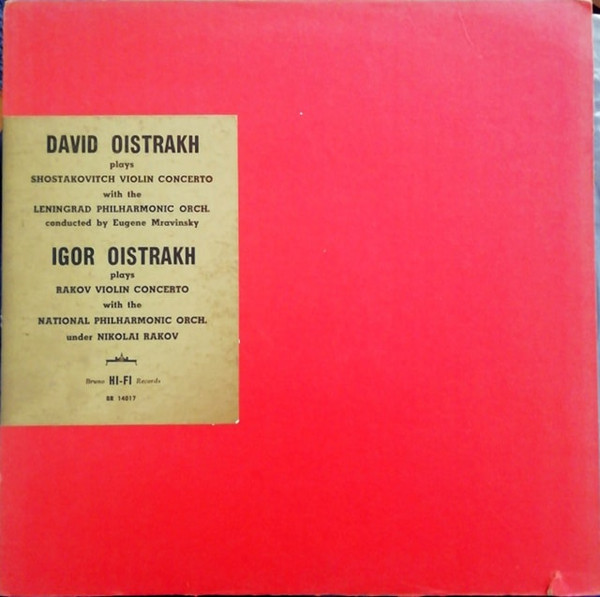
David Oistrakh (vn) [TR.01-04]
Evgeny Mravinsky (cond) [TR.01-04]
Leningrad Philharmonic Orchestra [TR.01-04]
Igor Oistrakh (vn) [TR.05-07]
Nikorai Rakov (cond) [TR.05-07]
National Philharmonic Orchestra [TR.05-07]
1958
Bruno Records
Discogs
|
01. Violin Concerto: 1st mvt. Nocturne: Moderato (Shostakovich)
02. Violin Concerto: 2nd mvt. Scherzo: Allegro (Shostakovich)
03. Violin Concerto: 3rd mvt. Passacaglia: Andante (Shostakovich)
04. Violin Concerto: 4th mvt. Burlesca: A;llegro con brio (Shostakovich)
05. Violin Concerto (No. 1): 1st mvt. Allegro (Rakov)
06. Violin Concerto (No. 1): 2nd mvt. Andante (Rakov)
07. Violin Concerto (No. 1): 3rd mvt. Allegro motto vivace (Rakov) |
|
David Oisatrakh - Sonata for violin and piano / Poem /
Moldavskaya Rhapsody
![non images]()
David Oistrakh (vn) [TR.01-06]
Yuri Levitine (pf) [TR.01-04]
Nikorai Rakov (pf) [TR.05]
Moisei Vainberg (pf) [TR.06]
1959
Aprelevski Zavod
Discogs
|
01. Sonata in C major for violin and piano, Op. 43: 1st mvt. Adagio (Levitine)
02. Sonata in C major for violin and piano, Op. 43: 2nd mvt. Allegro (Levitine)
03. Sonata in C major for violin and piano, Op. 43: 3rd mvt. Andantino (Levitine)
04. Sonata in C major for violin and piano, Op. 43: 4th mvt. Vivo (Levitine)
05. Poem in E minor for violin and piano (Rakov)
06. Moldovian Rhapsody in G minor for violin and piano, Op. 47 (Vainberg) |
|
N. Rakov - Symphony No. 2 "Youth" / Concert Waltz
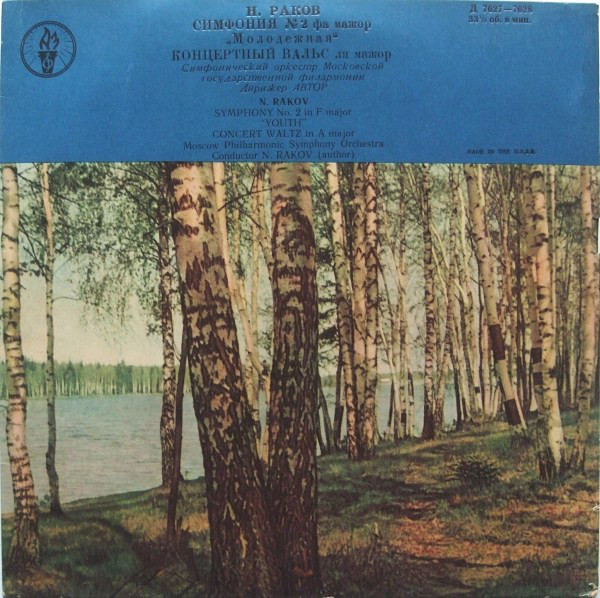
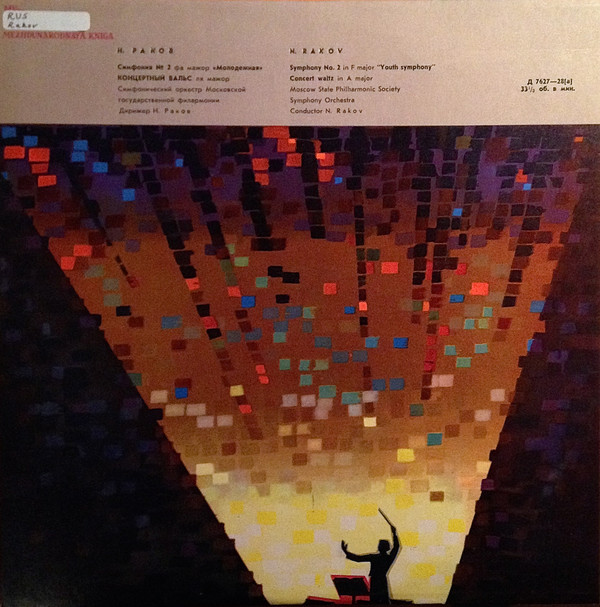
Nikolai Rakov (cond) [TR.01-05]
Moscow State Philharmonic Society Symphony Orchestra [TR.01-05]
1961
Aprelevskii Zavod / Līgo / Melodiya
Discogs
Discogs
Discogs
Discogs
Discogs
|
01. Symphony No. 2 in F major "Youth": 1st mvt. Moderato (Rakov)
02. Symphony No. 2 in F major "Youth": 2nd mvt. Vivo (Rakov)
03. Symphony No. 2 in F major "Youth": 3rd mvt. Andantino (Rakov)
04. Symphony No. 2 in F major "Youth": 4th mvt. Allegro Giocoso (Rakov)
05. Concert Waltz in A major (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Works by S. Feinberg, N. Rakov, N. Peiko, G. Galyinin

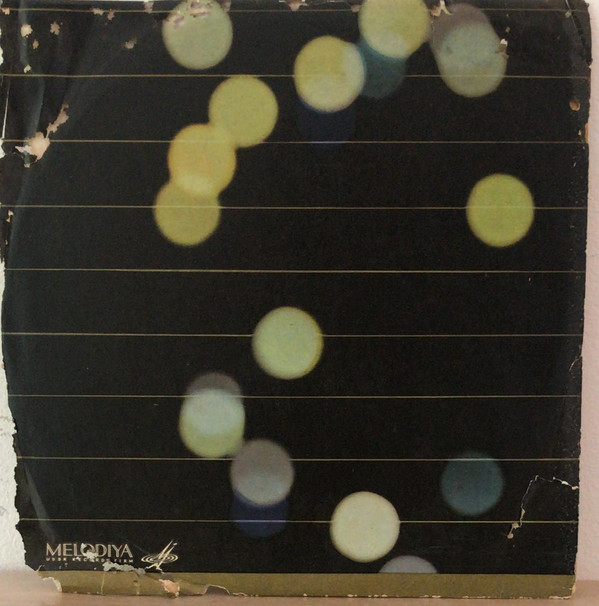
Dmitri Blagoy (pf) [TR.01-10]
1963
Discogs
Discogs
|
01. Rhapsody on theme of Kabardino-Balkarsk in F major, Op. 45 (Feinberg)
02. Sonata in classical style: 1st mvt. Allegro con inpento (Rakov)
03. Sonata in classical style: 2nd mvt. Andantino poco capriccioso (Rakov)
04. Sonata in classical style: 3rd mvt. Ben ritmico (Rakov)
05. Ballade in B minor (Peiko)
06. Suite for piano: I. Toccata (Galynin)
07. Suite for piano: II. Intermezzo (Galynin)
08. Suite for piano: III. Dance (Galynin)
09. Suite for piano: IV. Aria (Galynin)
10. Suite for piano: V. Presto agitato (Galynin) |
|
David Oistrakh
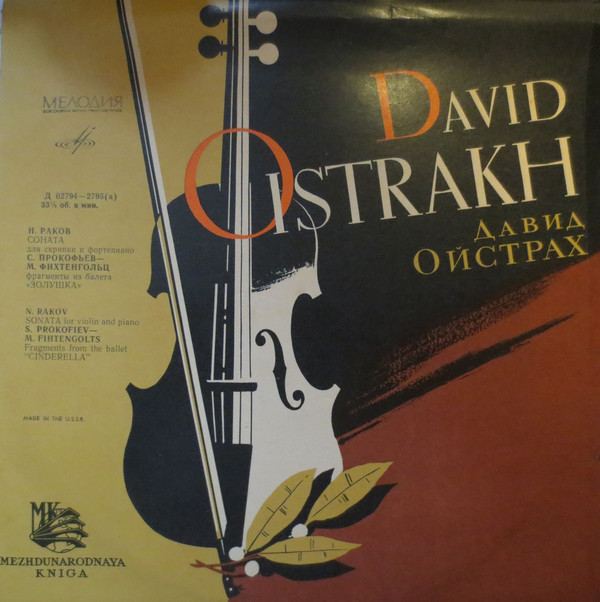
David Oistrakh (vn) [TR.01-08]
Nikolai Rakov (pf) [TR.01-03]
Vladimir Yampolsky (pf) [TR.04-08]
1964(?)
Aprelevsky Zavod / Melodiya
Discogs
Discogs
Discogs
|
01. Sonata (No. 1) in E minor for violin and piano: 1st mvt. Allegro moderato (Rakov)
02. Sonata (No. 1) in E minor for violin and piano: 2nd mvt. Andante sostenuto (Rakov)
03. Sonata (No. 1) in E minor for violin and piano: 3rd mvt. Allegro (Rakov)
04. Fragments from the ballet "Cinderella" : Waltz (Prokofiev=Fikhtengolts)
05. Fragments from the ballet "Cinderella" : Gavotte (Prokofiev=Fikhtengolts)
06. Fragments from the ballet "Cinderella" : Fairy of Winter (Prokofiev=Fikhtengolts)
07. Fragments from the ballet "Cinderella" : Paspier (Prokofiev=Fikhtengolts)
08. Fragments from the ballet "Cinderella" : Mazurka (Prokofiev=Fikhtengolts) |
|
B.Lyatoshinskii / L.Knipper / N.Rakov
- Symphony No. 4/Malenkii Concert for violin/Malenkaya Symphony
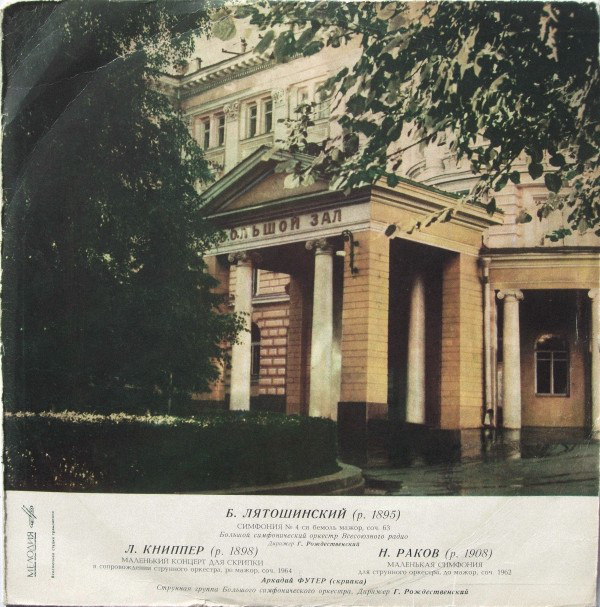
Gennady Rozhdestvensky (cond) [TR.01-10]
USSR State Radio Symphony Orchestra [TR.01-06]
Arkadii Futer (vn) [TR.04-06]
Strings Group from USSR State Radio Symphony Orchestra [TR.07-10]
1968
Melodiya
Discogs
|
01. Symphony No. 4 in B flat major, Op. 53: 1st mvt. Andante sostenuto e maestoso (Lyatoshinsky)
02. Symphony No. 4 in B flat major, Op. 53: 2nd mvt. Lento tenebroso (Lyatoshinsky)
03. Symphony No. 4 in B flat major, Op. 53: 3rd mvt. Allegro molto risoluto (Lyatoshinsky)
04. Small Concerto for violin accompanied with string orchestra, in D major: 1st mvt. Allegro (Knipper)
05. Small Concerto for violin accompanied with string orchestra, in D major: 2nd mvt. Adagio (Knipper)
06. small Concerto for violin accompanied with string orchestra, in D major: 3rd mvt. Vivo (Knipper)
07. Little Symphony for string orchestra, in C major: 1st mvt. Allegro moderato (Rakov)
08. Little Symphony for string orchestra, in C major: 2nd mvt. Moderato (Rakov)
09. Little Symphony for string orchestra, in C major: 3rd mvt. Vivo (Rakov)
10. Little Symphony for string orchestra, in C major: 4th mvt. Finale. Allegro (Rakov) |
|
Nikolai Rakov - Piano Pieces for young performers
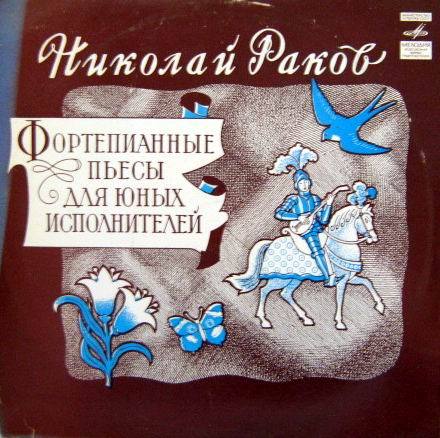
Alexei Nasedkin (pf) [TR.01-17]
1972
|
01. from "Children's Days": I. A Tale (Rakov)
02. from "Children's Days": II. Playing Games (Rakov)
03. from "Children's Days": III. A Song (Rakov)
04. from "Children's Days": VI. (Rakov)
05. from "Children's Days": IX. (Rakov)
06. from "Children's Days": IV. (Rakov)
07. from "Novellettes": II. Legend (Rakov)
08. from "Novellettes": VI. Waltz (Rakov)
09. from "Novellettes": IX. Mazurka (Rakov)
10. from "Novellettes": X. Tarantella (Rakov)
11. Russinan Song (Rakov=Ginzburg)
12. Piano Sonatina No. 3 in C major "Youthful"
13. Piano Sonatina No. 4 in A minor "Lyrical"
14. Piano Sonatina No. 5 in C major "Youth"
15. Piano Sonatina No. 1 in E minor: 1st mvt. Allegro moderato
16. Piano Sonatina No. 1 in E minor: 2nd mvt. Andante
17. Piano Sonatina No. 1 in E minor: 3rd mvt. Presto
All composed by N.Rakov |
|
Eduard Grach plays A.Babadzhanian/A.Eshpai/N.Rakov
- Sonata/Sonata No.2/2 Sonatinas

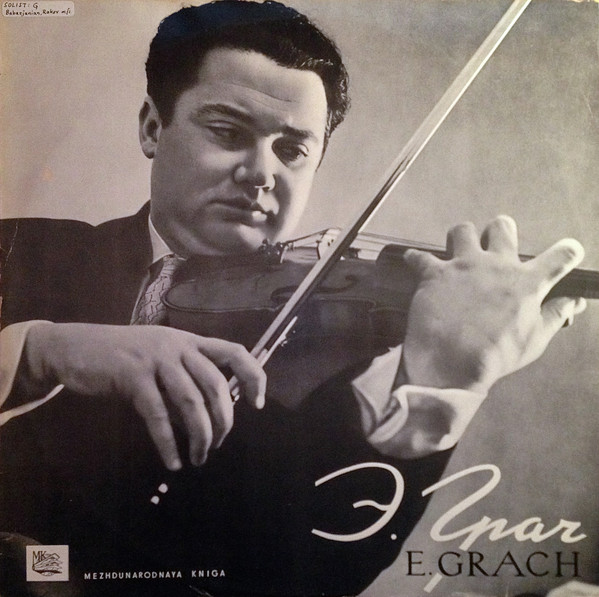
Eduard Grach (vn) [TR.01-10]
Arno Babadzhanian (pf) [TR.01-03]
Andrei Eshpai (pf) [TR.04]
Nikolai Rakov (pf) [TR.05-10]
1972
Melodiya
Discogs
Discogs
Discogs
|
01. Sonata in B flat minor for violin and piano: 1st mvt. Grave - Allegro energico (Babadzhanian)
02. Sonata in B flat minor for violin and piano: 2nd mvt. Andante sostenuto (Babadzhanian)
03. Sonata in B flat minor for violin and piano: 3rd mvt. Allegro risoluto (Babadzhanian)
04. Sonata No. 2 for violin and piano (Eshpai)
05. Sonatina No. 2 for violin and piano, in D major: 1st mvt. Allegro moderato (Rakov)
06. Sonatina No. 2 for violin and piano, in D major: 2nd mvt. Allegro scherzando (Rakov)
07. Sonatina No. 2 for violin and piano, in D major: 3rd mvt. Allegro (Rakov)
08. Tryptich (Sonatina No. 3) for violin and piano: 1st mvt. Allegro (Rakov)
09. Tryptich (Sonatina No. 3) for violin and piano: 2nd mvt. Moderato (Rakov)
10. Tryptich (Sonatina No. 3) for violin and piano: 3rd mvt. Vivo (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Conductor: Neheme Järvi


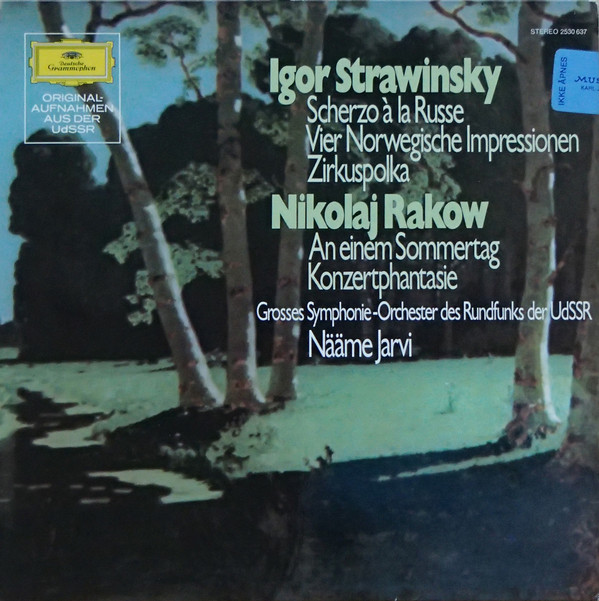
Neheme Järvi (cond) [TR.01-12]
USSR Radio Large Symphony Orchestra [TR.01-12]
Lev Mikhailov (cl) [TR.12]
1972 / 1975
Melodiya / Deutsche Grammophon
Discogs
Discogs
Discogs
Discogs
|
01. Russian Scherzo (Stravinsky)
02. 4 Norwegian Moods: I. Intrade (Stravinsky)
03. 4 Norwegian Moods: II. Chant (Stravinsky)
04. 4 Norwegian Moods: III. Danse Nuptiale (Stravinsky)
05. 4 Norwegian Moods: IV. Cortège (Stravinsky)
06. Circus Polka (Stravinsky)
07. "Summer Days", 5 Pieces for chamber orchestra: I. The Morning
08. "Summer Days", 5 Pieces for chamber orchestra: II. On the Lake
09. "Summer Days", 5 Pieces for chamber orchestra: III. Athletic March
10. "Summer Days", 5 Pieces for chamber orchestra: IV. Walk in the Meadows
11. "Summer Days", 5 Pieces for chamber orchestra: V. Night Games
12. Concert Fantasy for clarinet and oechstra (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Nikolai Rakov - Easy Piano Pieces

Nikolai Rakov (pf) [TR.01-27]
1973
Melodiya
★★★★★★
Discogs
|
01. 8 Pieces on theme of Russian folk song for piano [1949]: I. Song (Rakov)
02. 8 Pieces on theme of Russian folk song for piano [1949]: II. Fairy Tale (Rakov)
03. 8 Pieces on theme of Russian folk song for piano [1949]: III. Waltz (Rakov)
04. 8 Pieces on theme of Russian folk song for piano [1949]: IV. Mazurka (Rakov)
05. 8 Pieces on theme of Russian folk song for piano [1949]: V. Polka (Rakov)
06. 8 Pieces on theme of Russian folk song for piano [1949]: VI. Berceuse (Rakov)
07. 8 Pieces on theme of Russian folk song for piano [1949]: VII. March (Rakov)
08. 8 Pieces on theme of Russian folk song for piano [1949]: VIII. Finale (Rakov)
09. 24 Children's Pieces in all keys [1961] : No. 8; Ballad of the Knight (Rakov)
10. 24 Children's Pieces in all keys [1961] : No. 12; White Lily (Rakov)
11. 24 Children's Pieces in all keys [1961] : No. 13; Swallow (Rakov)
12. Aquarelles for piano [1946] : II. Mazruka (Rakov)
13. Aquarelles for piano [1946] : IV. Legende (Rakov)
14. Aquarelles for piano [1946] : VII. Scherzo (Rakov)
15. Little Suite for piano [1929?] : I. (Rakov)
16. Little Suite for piano [1929?] : II. (Rakov)
17. Little Suite for piano [1929?] : III. (Rakov)
18. Little Suite for piano [1929?] : IV. (Rakov)
19. 10 Pieces on folksong for piano [1969] : I. Melody (Rakov)
20. 10 Pieces on folksong for piano [1969] : II. Wedding Song (Rakov)
21. 10 Pieces on folksong for piano [1969] : III. Song (Rakov)
22. 10 Pieces on folksong for piano [1969] : VII. Why are you crying silently? (Rakov)
23. 10 Pieces on folksong for piano [1969] : VIII. Russian Song (Rakov)
24. First Violet(Rakov)
25. Scherzo (Rakov)
26. Spring coming (Rakov)
27. Polka in C major (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Alexei Nasedkin
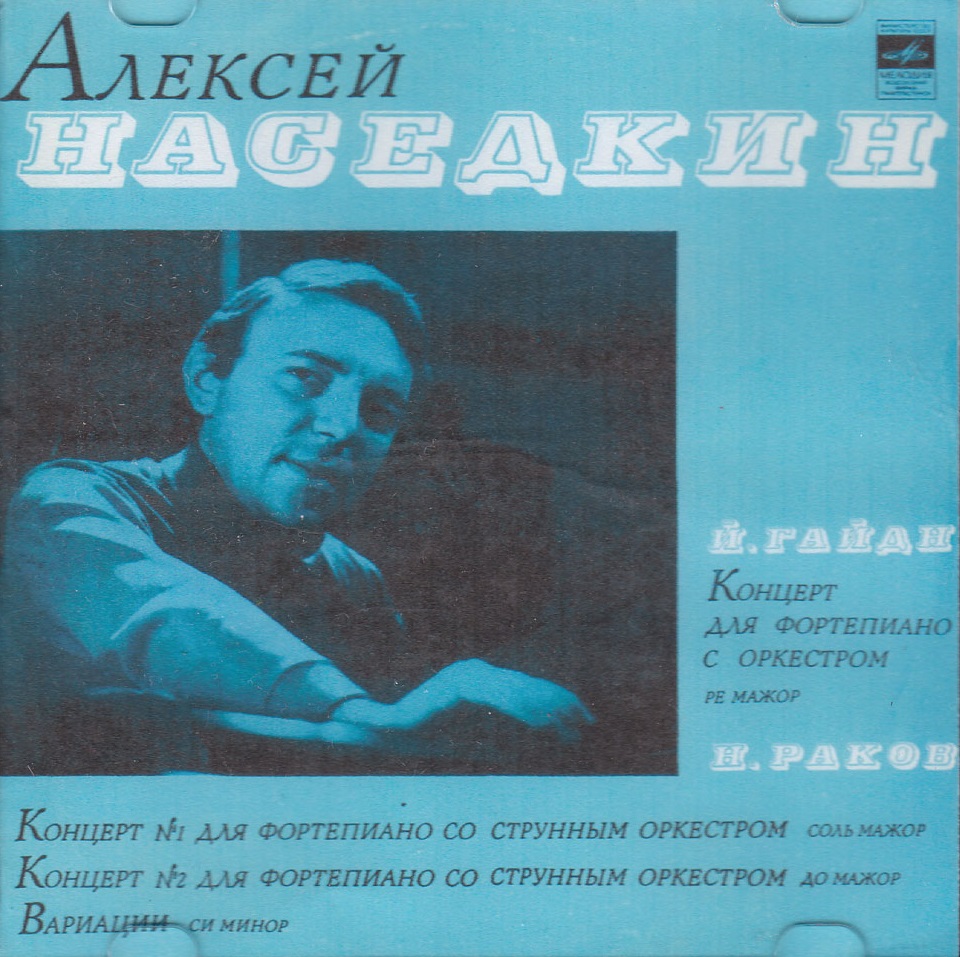

Alexei Nasedkin [TR.01-06]
Chamber Orchestra [TR.01-03]
Lev Markiz (cond) [TR.01-03]
All-Union Radio Symphony Orchestra String Group [TR.04-05]
Nikolai Rakov (cond) [TR.04-05]
1974
Melodiya
★★★★★☆
Discogs
Discogs
Discogs
|
01. Concerto for piano and orchestra in D major: I. Vivace (Haydn)
02. Concerto for piano and orchestra in D major: II. Un poco adagio (Haydn)
03. Concerto for piano and orchestra in D major: III. Rondo all' Ungarese. Allegro assai (Haydn)
04. Concerto No. 1 for piano and string orchestra in G major (Rakov)
05. Concerto No. 2 for piano and string orchestra in C major (Rakov)
06. Variations in B minor (Rakov) |
|
Nikolai Rakov - Sinfonietta, Small Symphony, Violin Concerto No.2
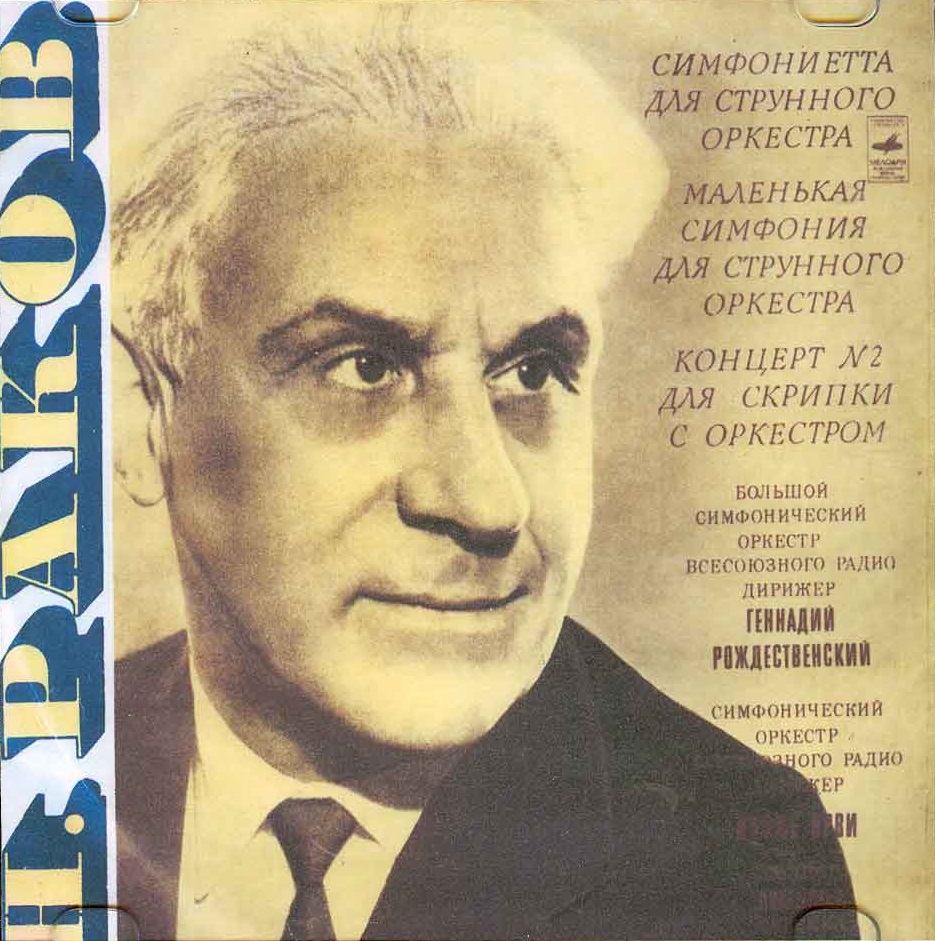

All-Union Radio Large Symphony Orchestra [TR.01-09]
Gennadi Rozhdestvensky (cond) [TR.01-09]
Oleg Kagan (vn) [TR.10]
All-Union Radio Symphony Orchestra [TR.10]
Neeme Jarvi (cond) [TR.10]
1974
Melodiya
★★★★★☆
Discogs
Discogs
Discogs
|
01. Sinfonietta for string orchestra in G minor: I. Allegro moderato - Allegro molto
02. Sinfonietta for string orchestra in G minor: II. Allegretto grazioso
03. Sinfonietta for string orchestra in G minor: III. Vivo
04. Sinfonietta for string orchestra in G minor: IV. Andante sostenutop
05. Sinfonietta for string orchestra in G minor: V. Allegro con fuoco
06. Small Symphony (Symphony No. 3) for string orchestra in C major: I. Allegro moderato
07. Small Symphony (Symphony No. 3) for string orchestra in C major: II. Andante
08. Small Symphony (Symphony No. 3) for string orchestra in C major: III. Vivo
09. Small Symphony (Symphony No. 3) for string orchestra in C major: IV. Andante sostenuto - Allegro
10. Concerto No. 2 for violin and orchestra in A minor
All composed by N.Rakov |
|
Nikolai Rakov - Concert Suite/Heroic March/Waltz

Nikolai Rakov (cond) [TR.01-10]
USSR State Radio an Television Symphony Orchestra [TR.01-10]
1976
Melodiya
Discogs
|
01. Festive Waltz in D major for symphonic orchestra (Rakov)
02. Brooding Waltz in E minor for string orchestra (Rakov)
03. Concert Waltz in A major for symphonic orchestra (Rakov)
04. Concert Suite in F major for symphonic orchestra: I. March (Rakov)
05. Concert Suite in F major for symphonic orchestra: II. Mazurka (Rakov)
06. Concert Suite in F major for symphonic orchestra: III. Melody (Rakov)
07. Concert Suite in F major for symphonic orchestra: IV. Dance (Rakov)
08. Concert Suite in F major for symphonic orchestra: V. Waltz (Rakov)
09. Concert Suite in F major for symphonic orchestra: VI. Finale (Rakov)
10. Heroic March in G major for symphonic orchestra (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Nikolai Rakov - Symphony No. 2
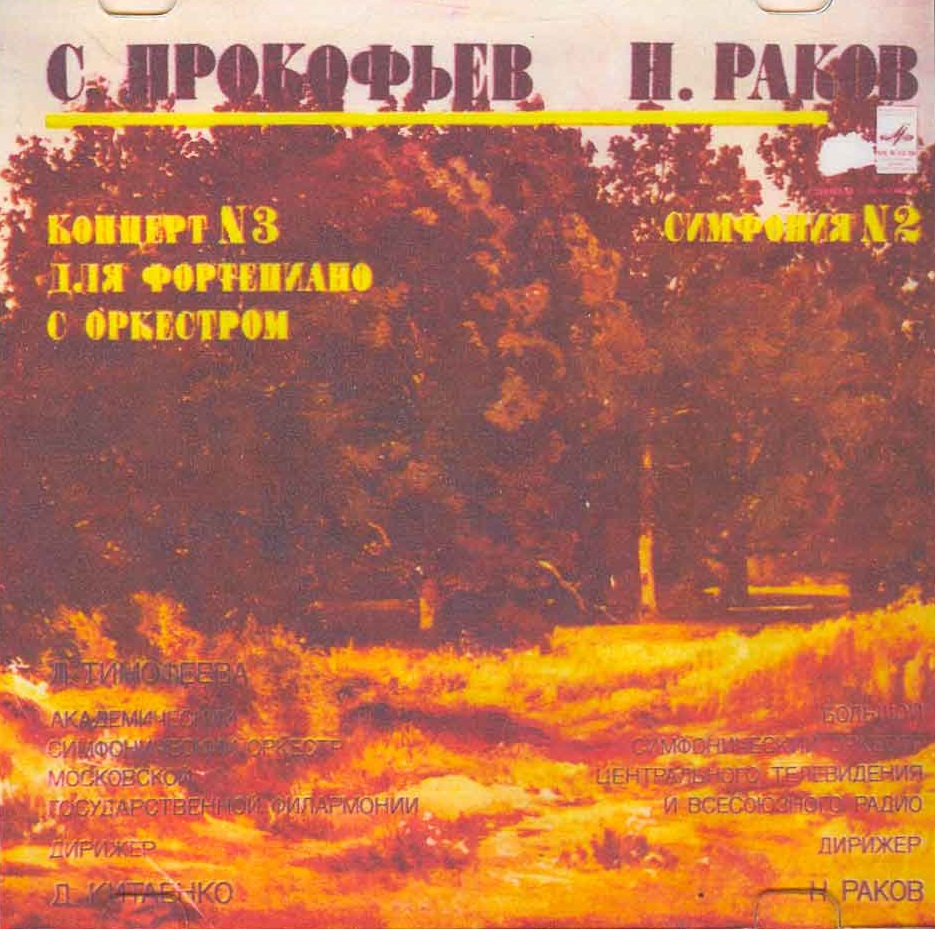
Lybov Timofeeva (pf) [TR.01-03]
Moscow Philharmonic Symphony Orchestra [TR.01-03]
Dmitry Kitaenko (cond) [TR.01-03]
The USSR TV and Radio Large Symphony Orchestra [TR.04-07]
Nikolai Rakov (cond) [TR.04-07]
1978
Melodiya
★★★★★☆
Discogs
Discogs
Discogs
|
01. Concerto No. 3 for piano and orchestra in C major, Op. 26: I. Andante allegro (Prokofiev)
02. Concerto No. 3 for piano and orchestra in C major, Op. 26: II. Theme and Variations. Andantino (Prokofiev)
03. Concerto No. 3 for piano and orchestra in C major, Op. 26: III. Allegro ma non troppo (Prokofiev)
04. Symphony No. 2 in F major "Young": I. Moderato - Allegro (Rakov)
05. Symphony No. 2 in F major "Young": II. Vivo (Rakov)
06. Symphony No. 2 in F major "Young": III. Andante (Rakov)
07. Symphony No. 2 in F major "Young": IV. Allegro giocoso (Rakov) |
|
Nikolai Rakov - Symphony No. 1, Summer Day
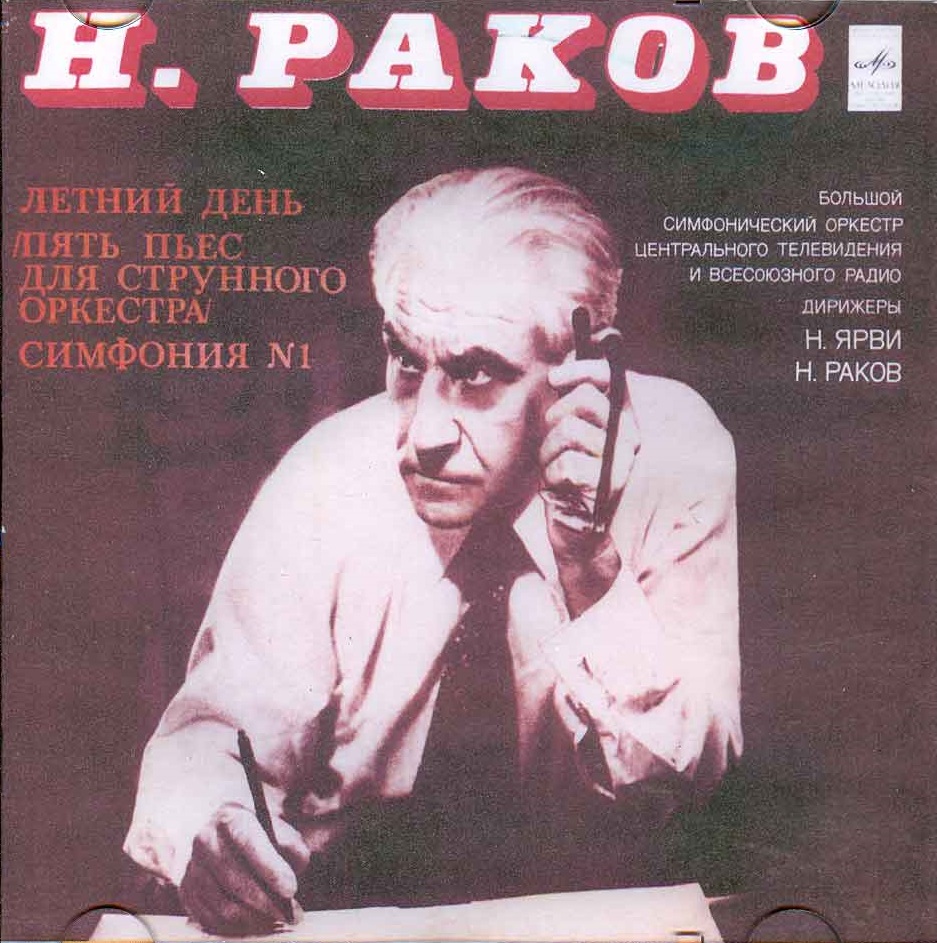
The USSR TV and Radio Large Symphony Orchestra String Group [TR.01-05]
Neeme Jarvi (cond) [TR.01-05]
The USSR TV and Radio Large Symphony Orchestra [TR.06-09]
Nikolai Rakov (cond) [TR.06-09]
1978
Melodiya
★★★★★☆
Discogs
|
01. "Summer Days", 5 Pieces for chamber orchestra: I. The Morning
02. "Summer Days", 5 Pieces for chamber orchestra: II. On the Lake
03. "Summer Days", 5 Pieces for chamber orchestra: III. Athletic March
04. "Summer Days", 5 Pieces for chamber orchestra: IV. Walk in the Meadows
05. "Summer Days", 5 Pieces for chamber orchestra: V. Night Games
06. Symphony No. 1 in D major: I. Andante
07. Symphony No. 1 in D major: II. Vivo
08. Symphony No. 1 in D major: III. Andante molto sostenuto
09. Symphony No. 1 in D major: IV. Moderato - Allegro giocoso
All composed by N.Rakov |
|
Nikolai Rakov - 4 Sonatas
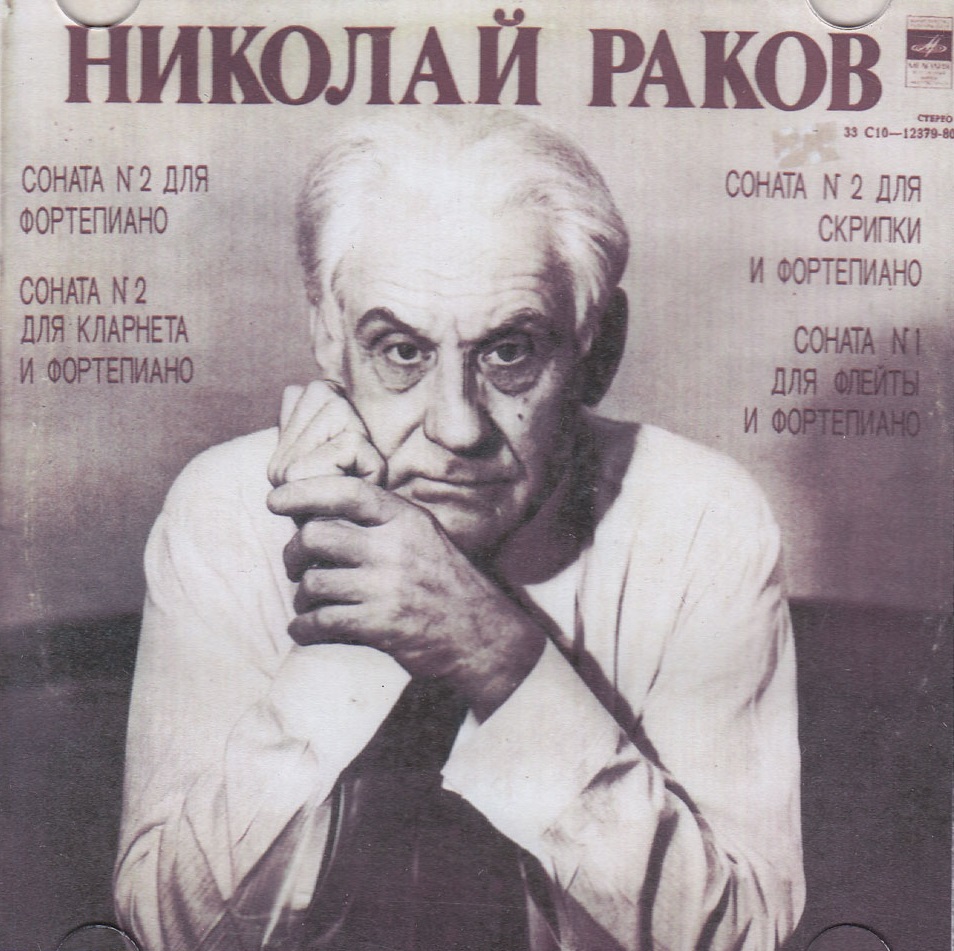
Alexei Nasedkin (pf) [TR.01-06, 10-12]
Lev Mikhailov (cl) [TR.04-06]
L.Blok (pf) [TR.07-09]
Valery Klimov (vn) [TR.07-09]
Valentin Zverev (fl) [TR.10-12]
1979
Melodiya
Discogs
|
01. Piano Sonata No. 2 in A minor: 1st mvt. Allegro
02. Piano Sonata No. 2 in A minor: 2nd mvt. Andante sostenuto
03. Piano Sonata No. 2 in A minor: 3rd mvt. Vivo
04. Sonata No. 2 in F major for clarinet and piano: 1st mvt. Allegro ma non troppo
05. Sonata No. 2 in F major for clarinet and piano: 2nd mvt. Moderato
06. Sonata No. 2 in F major for clarinet and piano: 3rd mvt. Vivo
07. Sonata No. 2 in G minor for violin and piano: 1st mvt. Allegro
08. Sonata No. 2 in G minor for violin and piano: 1st mvt. Andante sostenuto
09. Sonata No. 2 in G minor for violin and piano: 1st mvt. Allegro agitato
10. Sonata in A for flute and piano: 1st mvt. Allegro
11. Sonata in A for flute and piano: 2nd mvt. Andante Cantabile
12. Sonata in A for flute and piano: 3rd mvt. Vivo
All composed by N.Rakov |
|
Nikolai Rakov - Symphonic Music

Nikolai Rakov (cond) [TR.01-XX]
Strings Group from USSR State Radio an Television Symphony Orchestra [TR.01-02]
USSR State Radio an Television Symphony Orchestra [TR.01-10]
1983
Melodiya
Discogs
|
01. Poem in E minor for string orchestra (Rakov)
02. Poem in C major "Strong in Spilit" for string orchestra (Rakov)
03. Dance Suite for symphonic orchestra: I. Uzbek Dance (Rakov)
04. Dance Suite for symphonic orchestra: II. Armenian Dance (Rakov)
05. Dance Suite for symphonic orchestra: III. Tatar Dance (Rakov)
06. Dance Suite for symphonic orchestra: IV. Tajik Dance (Rakov)
07. Dance Suite for symphonic orchestra: V. Finale (Rakov)
08. Waltz No. 4 "Elegy" in D minor for symphonic orchestra (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Oleg Kagan
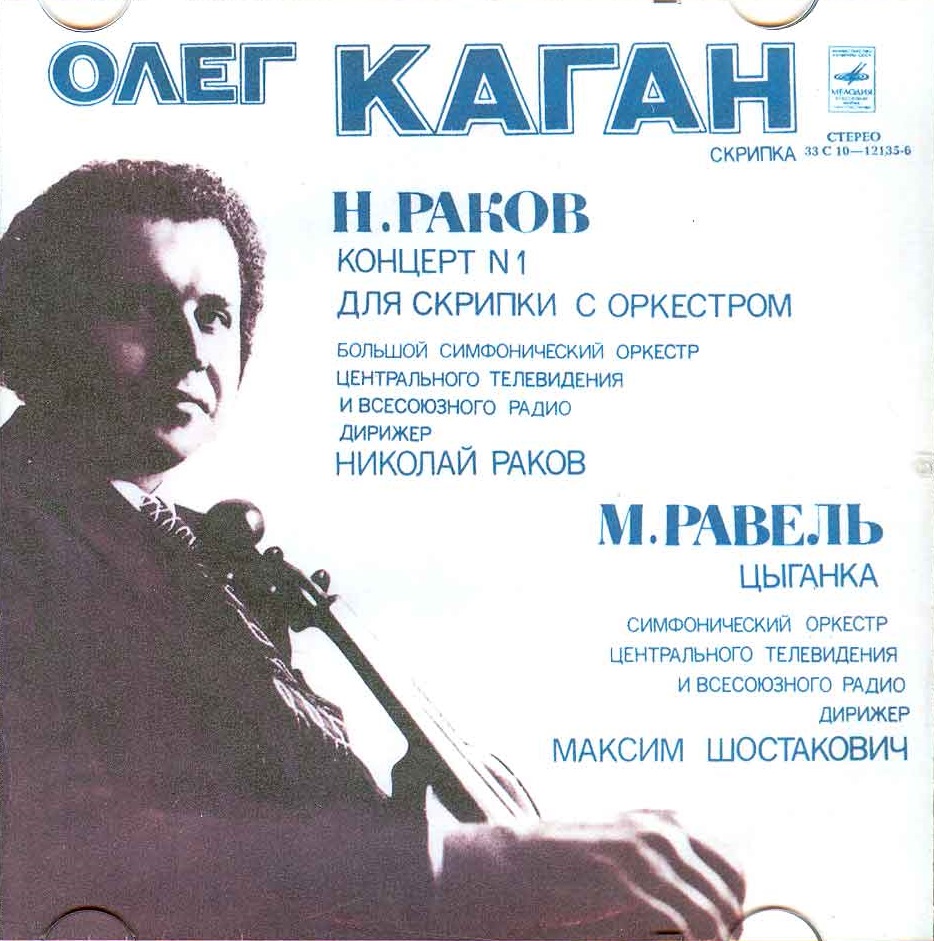
Oleg Kagan (vn) [TR.01-04]
The USSR TV and Radio Large Symphony Orchestra [TR.01-03]
Nikolai Rakov (cond) [TR.01-03]
The USSR TV and Radio Symphony Orchestra [TR.04]
Maxim Shostakovich (cond) [TR.04]
1986
Melodiya
Discogs
Discogs
Discogs
Discogs
|
01. Concerto No. 1 for violin and orchestra in E minor: I. Allegro (Rakov)
02. Concerto No. 1 for violin and orchestra in E minor: II. Andante (Rakov)
03. Concerto No. 1 for violin and orchestra in E minor: III. Allegro molto vivace (Rakov)
04. Tzigane, Rhapsody for violin and orchestra (Ravel) |
|
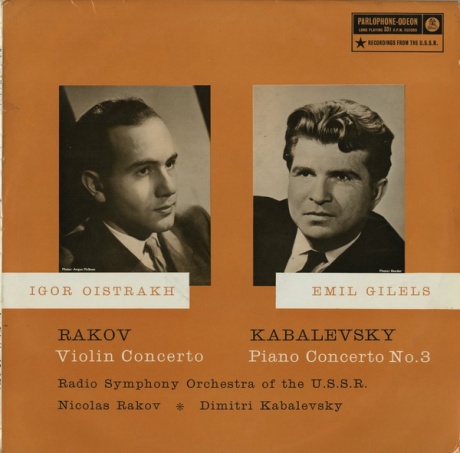
Igor Oistrakh (vn) [TR.01-03]
Nikolas Rakov [TR.01-03]
Emil Gilels (pf) [TR.04-06]
Dimitri Kabalevsky [TR.04-06]
Radio Symphony Orchestra of the U.S.S.R. [TR.01-06]
****/**/**
Parlophone Odeon
Record Sound
Discogs
|
01. Violin Concerto No. 1 in E minor: 1st mvt. Allegro (Rakov)
02. Violin Concerto No. 1 in E minor: 2nd mvt. Andante (Rakov)
03. Violin Concerto No. 1 in E minor: 3rd mvt. Allegro molto vivace (Rakov)
04. Piano Concerto No. 3 in D major, Op. 50: 1st mvt. Allegro molto (Kabalevsky)
05. Piano Concerto No. 3 in D major, Op. 50: 2nd mvt. Andante con moto (Kabalevsky)
06. Piano Concerto No. 3 in D major, Op. 50: 3rd mvt. Presto (Kabalevsky) |
|
楽 譜
・入手可 - 出版年順 -
+
・入手 (難) - 出版年順 -
+
Concerto for violin and orchestra

State Music Pablishing [Moscow-Leningrad]
1952
44 pages
OZON.ru
|
01. Concerto (No. 1) for violin and orchestra (Reduction. accompanished with piano) [1944] (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Concert Waltz for 2 pianos
![non image]()
Muzika [Moscow]
1959
44 pages
Rgub.ru
|
01. Concert Waltz for 2 pianos [] (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
"Youth"; 15 Light Pieces for violin and piano
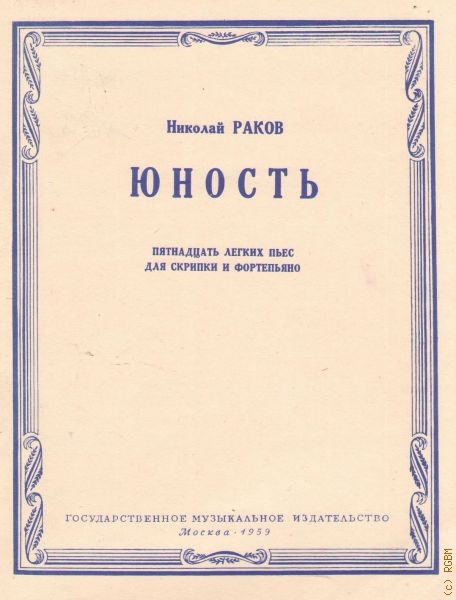
Muzika [Moscow]
1959
49 pages / 16 pages(vn)
Rgub.ru
|
01. "Youth" 15 pieces for violin and piano [1958]: I. Storytelling (Rakov)
02. "Youth" 15 pieces for violin and piano [1958]: II. Spring Protalinki (Rakov)
03. "Youth" 15 pieces for violin and piano [1958]: III. Snowflakes (Rakov)
04. "Youth" 15 pieces for violin and piano [1958]: IV. Behind the Book (Rakov)
05. "Youth" 15 pieces for violin and piano [1958]: V. Walk (Rakov)
06. "Youth" 15 pieces for violin and piano [1958]: VI. Ingout (Rakov)
07. "Youth" 15 pieces for violin and piano [1958]: VII. Etude-Scherzo (Rakov)
08. "Youth" 15 pieces for violin and piano [1958]: VIII. Fun Gmae (Rakov)
09. "Youth" 15 pieces for violin and piano [1958]: IX. Fairy Tale (Rakov)
10. "Youth" 15 pieces for violin and piano [1958]: X. Reminiscence (Rakov)
11. "Youth" 15 pieces for violin and piano [1958]: XI. Song (Rakov)
12. "Youth" 15 pieces for violin and piano [1958]: XII. Waltz (Rakov)
13. "Youth" 15 pieces for violin and piano [1958]: XIII. Mazurka (Rakov)
14. "Youth" 15 pieces for violin and piano [1958]: XIV. Tarantella (Rakov)
15. "Youth" 15 pieces for violin and piano [1958]: XV. Vocalise (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
3 Pieces for violin and piano
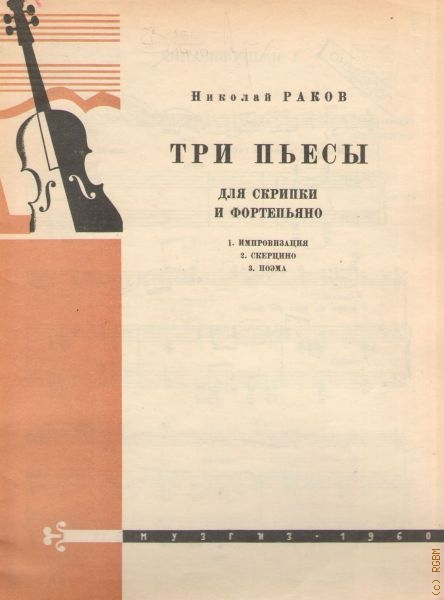
Muzgiz [Moscow]
1960
21 pages / 9 pages(vn)
Rgub.ru
|
01. Improvisation for violin and piano [1937] (Rakov)
02. Scherzino for violin and piano [1937] (Rakov)
03. Poem for violin and piano [1943] (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
"Wind Romance"-6 Songs Verses of Soviet Poets [1963]

Muzika [Moscow]
1965
26 pages
Rgub.ru
|
01. 6 Songs Verses of Soviet Poets [1963]: No. 1: The Wind of Romance (Rakov, words by Y.Khaketsky)
02. 6 Songs Verses of Soviet Poets [1963]: No. 2: And Yet I Believe …(Rakov, words by Y.Khaketsky)
03. 6 Songs Verses of Soviet Poets [1963]: No. 3: Do not Forget … (Rakov, words by Y.Khaketsky)
04. 6 Songs Verses of Soviet Poets [1963]: No. 4: My City - My Moscow (Rakov, words by Y.Polukhin)
05. 6 Songs Verses of Soviet Poets [1963]: No. 5: An Eighteen-year-old Boy (Rakov, words by A.Gaikovich)
06. 6 Songs Verses of Soviet Poets [1963]: No. 6: You lived in Mokhovaya (Rakov, words by V.Kuzetsov)
All composed by N.Rakov |
|
Sonatina No. 2 for violin and piano
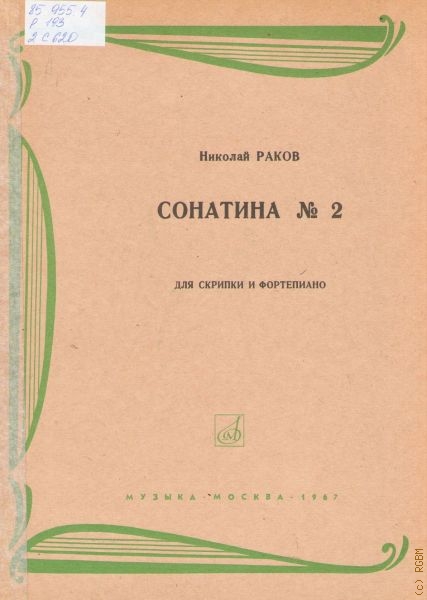
Muzika [Moscow]
1967
20 pages / 7 pages(vn)
Rgub.ru
|
01. Sonatina No. 2 for violin and piano [1965] (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Romance (N.Rakov) / Scherzo (V.Blok)
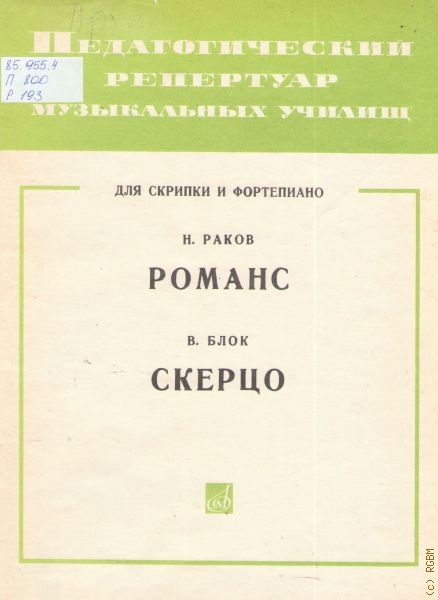
Muzika [Moscow]
1969
22 pages / 7 pages(vn)
Rgub.ru
|
01. Romance for violin and piano [1943] (Rakov)
02. Scherzo for violin and piano [] (Blok) |
|
Little Symphony for string orchestra; score
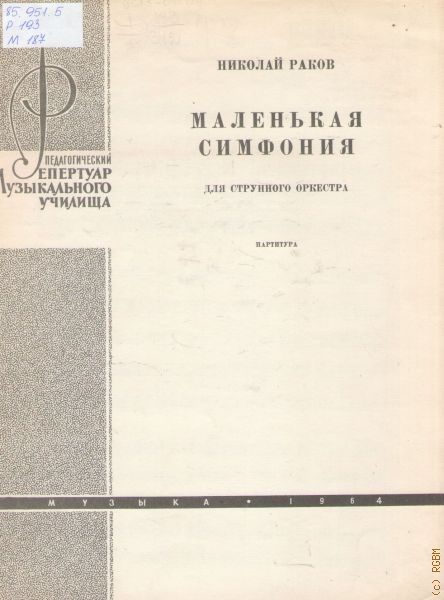
Muzika [Moscow]
1971
23 pages
Rgub.ru
|
01. Symphony No. 3 in C major for string orchestra [1962] (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Pieces "Summer Days" for school string orchestra; score and parts
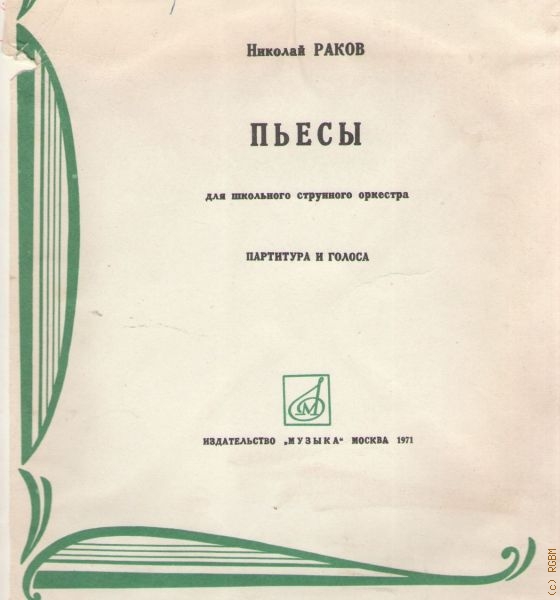
Muzika [Moscow]
1971
28 pages / 8pg(vn1), 8pg(vn2), 8pg(va), 8pg(vc), 7pg(cb)
Rgub.ru
|
01. "Summer Days" for string orchestra [1969]: I. The Morning (Rakov)
02. "Summer Days" for string orchestra [1969]: II. On the Lake (Rakov)
03. "Summer Days" for string orchestra [1969]: III. Athletic March (Rakov)
04. "Summer Days" for string orchestra [1969]: IV. Walk in the Meadows (Rakov)
05. "Summer Days" for string orchestra [1969]: V. Night Games (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Sonata for flute and piano
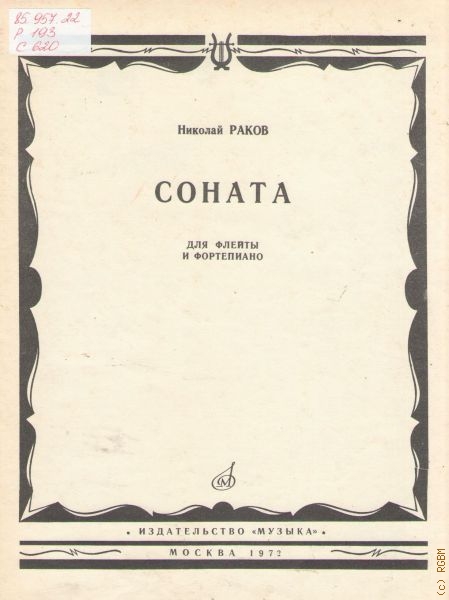
Muzika [Moscow]
1972
30 pages / 11 pages(fl)
Rgub.ru
|
01. Sonata for flute and piano [1970] (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Concert Etudes for piano; Vol. 1
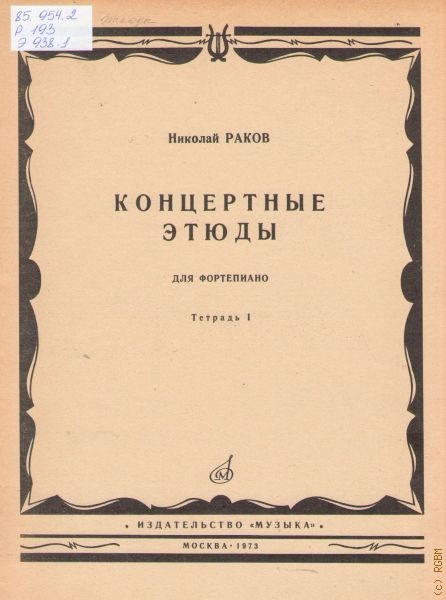
Muzika [Moscow]
1973
31 pages
Rgub.ru
|
01. Concert Etudes for piano; Vol. 1 [1965]: No. 1 in A minor (Rakov)
02. Concert Etudes for piano; Vol. 1 [1965]: No. 2 in D minor (Rakov)
03. Concert Etudes for piano; Vol. 1 [1965]: No. 3 in C major (Rakov)
04. Concert Etudes for piano; Vol. 1 [1965]: No. 4 in A major (Rakov)
05. Concert Etudes for piano; Vol. 1 [1965]: No. 5 in F Lydian (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Sonata No. 2 / Variations; for piano
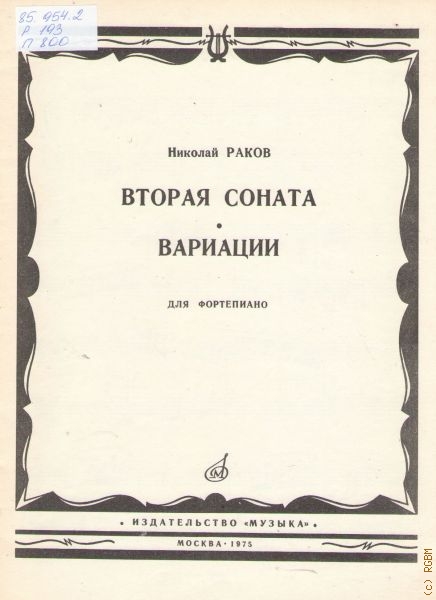
Muzika [Moscow]
1975
34 pages
Rgub.ru
|
01. Sonata No. 2 for piano [1973] (Rakov)
02. Variations in B minor for piano [1949] (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Concertos for piano and orchestra (Piano reduction)
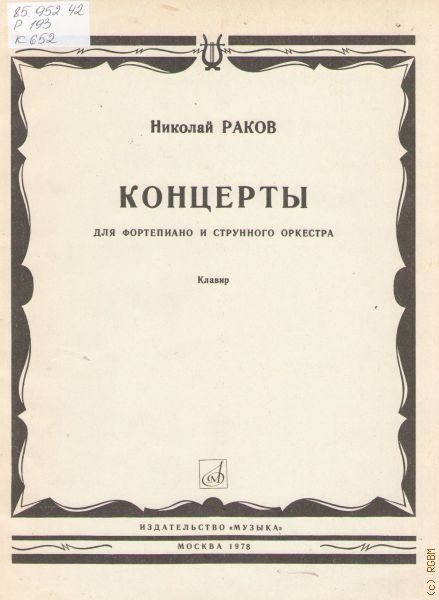
Muzika [Moscow]
1978
88 pages
Rgub.ru
|
01. Concerto No. 1 in G major [1969] (Rakov)
02. Concerto No. 2 in C major [1969] (Rakov)
03. Concerto No. 3 [1977] (Rakov)
04. Concerto No. 4 [1977] (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Aquarelles, 9 Pieces for piano
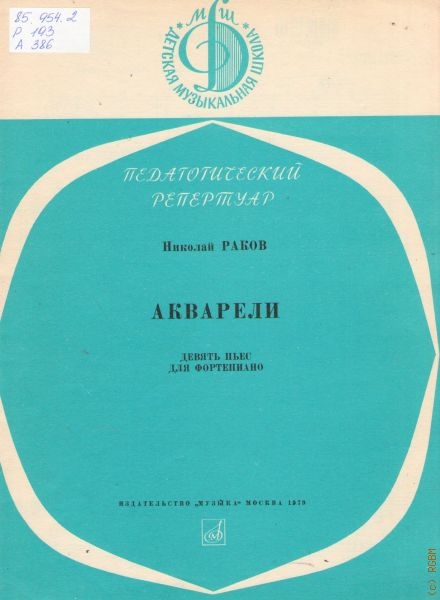
Muzika [Moscow]
1979
39 pages
Rgub.ru
|
01. Aquarelles for piano [1945]: I. Aquarelle (Rakov)
02. Aquarelles for piano [1945]: II. Mazurka (Rakov)
03. Aquarelles for piano [1945]: III. Bagatelle (Rakov)
04. Aquarelles for piano [1945]: IV. Legende (Rakov)
05. Aquarelles for piano [1945]: V. Intermezzo (Rakov)
06. Aquarelles for piano [1945]: VI. Minuet (Rakov)
07. Aquarelles for piano [1945]: VII. Scherzo (Rakov)
08. Aquarelles for piano [1945]: VIII. Novelette (Rakov)
09. Aquarelles for piano [1945]: IX. Waltz (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Music for 2 pianos
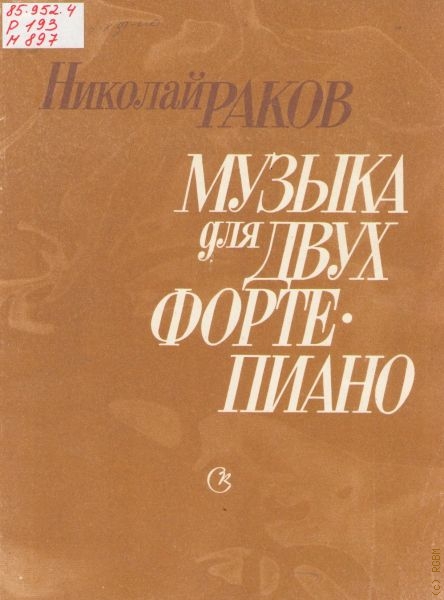
Soviet Conposers [Moscow]
1982
95 pages
Rgub.ru
|
01. Грустная песенка; [] (Rakov)
02. Веселая песенка (Rakov)
03. Лирический Вальс (Rakov)
04. Танец (Rakov)
05. Маски (Rakov)
06. Причудливые тени (Rakov)
07. Отзвуки (Rakov)
08. Вечерняя встреча (Rakov)
09. Веселый разговор (Rakov)
10. Юмореска (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Music for Strings; score
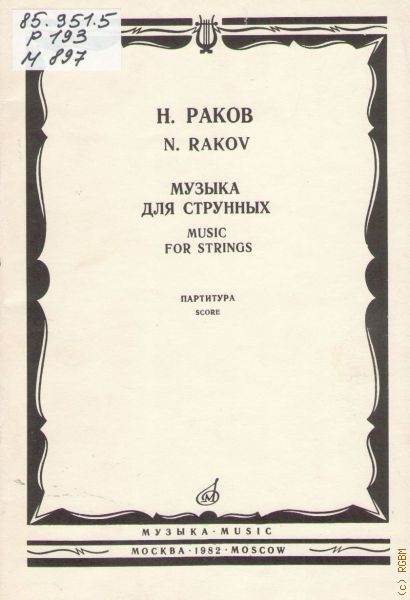
Muzika [Moscow]
1982
63 pages
Rgub.ru
|
01. Music for strings [1977]: I. Prelude (Rakov)
02. Music for strings [1977]: II. Game of glare (Rakov)
03. Music for strings [1977]: III. Intermezzo (Rakov)
04. Music for strings [1977]: IV. Humoresque (Rakov)
05. Music for strings [1977]: V. Bagatelle (Rakov)
06. Music for strings [1977]: VI. Serenade (Rakov)
07. Music for strings [1977]: VII. Chant (Rakov)
08. Music for strings [1977]: VIII. Mazurka (Rakov)
09. Music for strings [1977]: IX. Evening song (Rakov)
10. Music for strings [1977]: X. Scherzo (Rakov)
11. Music for strings [1977]: XI. Melody (Rakov)
12. Music for strings [1977]: XII. March (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Works for string orchestra; score
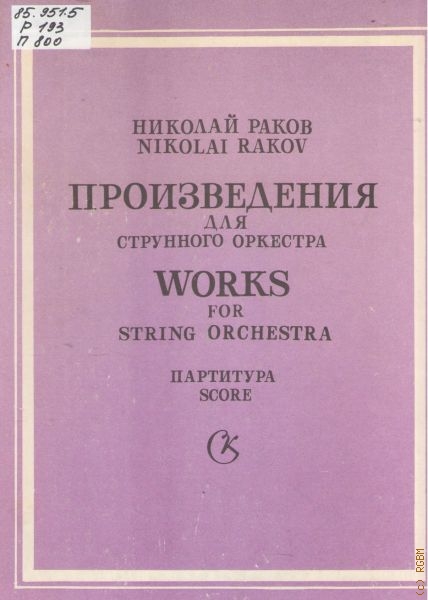
Soviet Composers [Moscow]
1984
151 pages
Rgub.ru
|
01. Poem [1981] (Rakov)
02. Poem "Strong in Spirit" (Dedication to the memory of the Hero of the Soviet Union) [1979] (Rakov)
03. Overture (Dedication to K. Ivashkevičius) [1978] (Rakov)
04. Sinfonietta [1956] (Rakov)
05. "Summer Days" for string orchestra [1969]: I. The Morning (Rakov)
06. "Summer Days" for string orchestra [1969]: II. On the Lake (Rakov)
07. "Summer Days" for string orchestra [1969]: III. Athletic March (Rakov)
08. "Summer Days" for string orchestra [1969]: IV. Walk in the Meadows (Rakov)
09. "Summer Days" for string orchestra [1969]: V. Night Games (Rakov)
10. Little Symphony [1962] (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
● Pieces in 24 keys for violin and piano
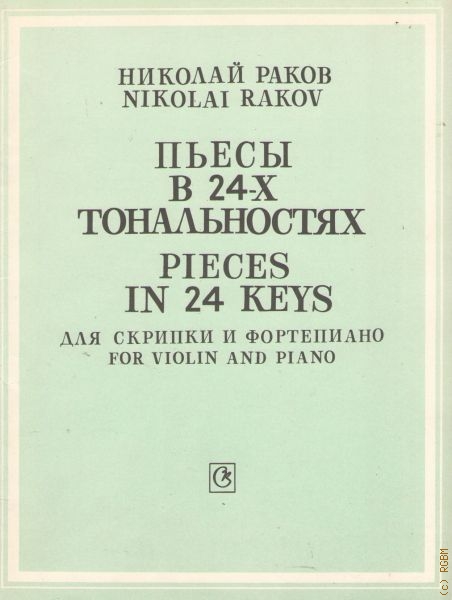
Soviet Composers [Moscow]
1984
72 pages / 44 pages(vn)
Rgub.ru
|
(正しく書き直していないため以下の内容は適切でない)
01. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: I. Prelude (Rakov)
02. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: II. Game of glare (Rakov)
03. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: III. Intermezzo (Rakov)
04. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: IV. Humoresque (Rakov)
05. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: V. Bagathold (Rakov)
06. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: VI. Serenade (Rakov)
07. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: VII. Ingout (Rakov)
08. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: VIII. Mazurka (Rakov)
09. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: IX. Evening song (Rakov)
10. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: X. Scherzo (Rakov)
11. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: XI. Melody (Rakov)
12. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: II. Game of glare (Rakov)
13. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: III. Intermezzo (Rakov)
14. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: IV. Humoresque (Rakov)
15. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: V. Bagathold (Rakov)
16. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: VI. Serenade (Rakov)
17. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: VII. Ingout (Rakov)
18. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: VIII. Mazurka (Rakov)
19. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: IX. Evening song (Rakov)
20. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: X. Scherzo (Rakov)
21. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: XI. Melody (Rakov)
22. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: II. Game of glare (Rakov)
23. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: III. Intermezzo (Rakov)
24. Pieces in 24 keys for violin and piano [1984?]: IV. Humoresque (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Tryptich for violin and piano
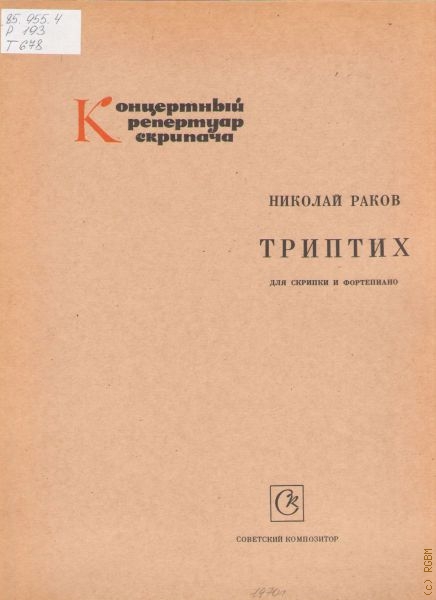
Muzika [Moscow]
1986
47 pages / 16 pages(vn)
Rgub.ru
|
01. Tryptich (Sonatina No. 3) for violin and piano [1968] (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
Variations in B minor for piano [1949]
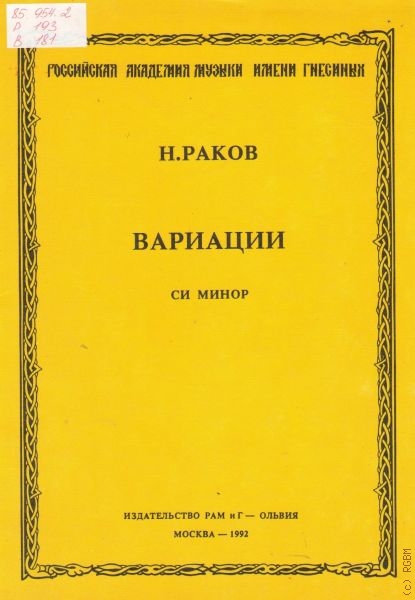
RAM and G.Olybia [Moscow]
1992
17 pages
Rgub.ru
|
01. Variations in B minor for piano [1949] (Rakov)
All composed by N.Rakov |
|
+(アンソロジー)
世界大音楽全集 第30巻 (器楽篇 ロシアピアノ名曲集 第3)

音楽之友社 [東京]
1958
236 pages
国立国会図書館
|
01. 5 Variations on the theme of Mozart's opera "Don Giovanni" in E fkat major [1822] (Glinka)
02. 4 Variations on the song "The Nightingale" by Alexandr Alabiev [1833] (Glinka)
03. Nocturne in F minor "La séparation" [1839] (Glinka)
04. Taranterlla in A minor [1843] (Glinka)
05. Variations on a Scottish theme in F major [1847] (Glinka)
06. Children's Polka in B flat major [1854] (Glinka)
07. Scherzo in A flat major [1885] (Borodin)
08. Petite Suite [1885]: I. In the Monastery (Borodin)
09. Petite Suite [1885]: II. Intermezzo (Borodin)
10. Petite Suite [1885]: III. Mazerka (Borodin)
11. Petite Suite [1885]: IV. Mazurka (Borodin)
12. Petite Suite [1885]: V. Rêverie (Borodin)
13. Petite Suite [1885]: VI. Serenade (Borodin)
14. Petite Suite [1885]: VII. Nocturne (Borodin)
15. Mazurka in A major, Op. 15-1 [1887] (Liadov)
16. Little Waltz (in G major), Op. 26 [1891] (Liadov)
17. Bagatelle (in D flat major), Op. 30 [1889] (Liadov)
18. Prelude in D flat major, Op.10-1 [1885] (Liadov)
19. Prelude in B flat minor, Op.31-2 [1893] (Liadov)
20. Prelude in C major, Op.40-2 [1897] (Liadov)
21. Prelude in E minor, Op.46-4 [1899] (Liadov)
22. Prelude in D minor, Op.40-3 [1897] (Liadov)
23. Prelude in D minor, Op.63-10 [1903] (Arensky)
24. "No.24: Aux champs" from 24 Characteristic pieces, Op.36 [1894] (Arensky)
25. 24 Pieces caracteristiques, Op. 34 [1908]: No. 12: Sketch (Glière)
26. 24 Pieces caracteristiques, Op. 34 [1908]: No. 7: In the field (Glière)
27. 8 Easy Pieces, Op.43 [1909]: No. 7: Arietta (Glière)
28. 8 Easy Pieces, Op.43 [1909]: No. 3: Mazurka (Glière)
29. 8 Easy Pieces, Op.43 [1909]: No. 4: Le Matin (Glière)
30. Sonata No. 8 in D minor, Op. 83 [1949] (Miaskovsky)
31. Sonata No. 4, Op. 19 [1922 rev.1954] (Alexandrov)
32. Sonata No. 3, Op. 24 [1941] (Bely)
33. Serenade (Rakov)
34. Slow Waltz (Rakov)
35. Tango (Rakov)
36. Concert Waltz (Rakov)
37. Ball from Children's album (Machavariani)
38. March (Khachaturian)
39. 2 Preludes [1950?]: I. (Dzubanova)
40. 2 Preludes [1950?]: II. (Dzubanova)
41. Aria (Galynin)
42. Moments Musicaux (Kvernadze)
43. Andante (Ledenev)
44. Dance (Pirumov)
45. 3 Pastorale: I. (Rauchverger)
46. 3 Pastorale: II. (Rauchverger)
47. 3 Pastorale: III. (Rauchverger) |
|
---------------------------------------
◆ 注 釈 ・ 備 考 * 大幅に加筆した部分に対応するため注釈附番が統一されてませんが, いずれ修正します *
[*1]
アメリカやカナダに居る場合, レンタル譜を請求することができる.
下記参照: Music Sales Classical - Nikorai Rakov
[*2 (2021/08/03 記述)]
『ピアノソナタ 第1番(1959)』と『古典形式によるソナタ(1959)』は同一の曲を指しています. (副題的扱い)
本サイトの作品目録の大部分はラコフ本人が存命だった1979年に音楽学者 アナトリー・ツケル(Anatoly Tsker, 1944- )が著した
書籍『ニコライ・ラコフ』の附録部分を根拠にしています. (当然ながら, 1979年以降の作品は別情報源による記載になります)
その中で, 上記作品が独立した2つの作品であると誤解し, 長らく誤った情報を本サイト上に掲載してしまいました.
大変 失礼いたしました..
[*3 (2021/08/03 記述)]
『ピアノソナチネ 第4番』について「ハ短調の3楽章制」であるように記載していましたが, これは誤りで,
正しくは「イ短調の単一楽章制」です.
このような誤解が生じた理由は,
ピアニスト: ドミトリー・ブラゴイがリリースしたLP『Rhapsody / Sonatina No. 4 In C Minor / Ballade In B Minor / Suite()』にて
ラコフの作品『ピアノソナタ 第1番 ハ短調』が収録されているのですが,
LPの盤面やジャケットにおいてその作品紹介が『ピアノソナチネ 第4番 ハ短調』や『ピアノソナタ 第4番』
などと誤って表記されていることに起因しています.
[ 写 真 表 示 ]
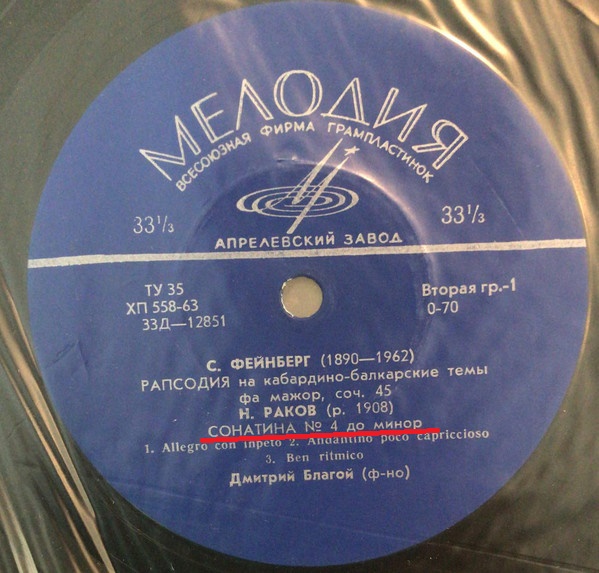
『Sonatina No. 4 in C minor』と記載されている…
|
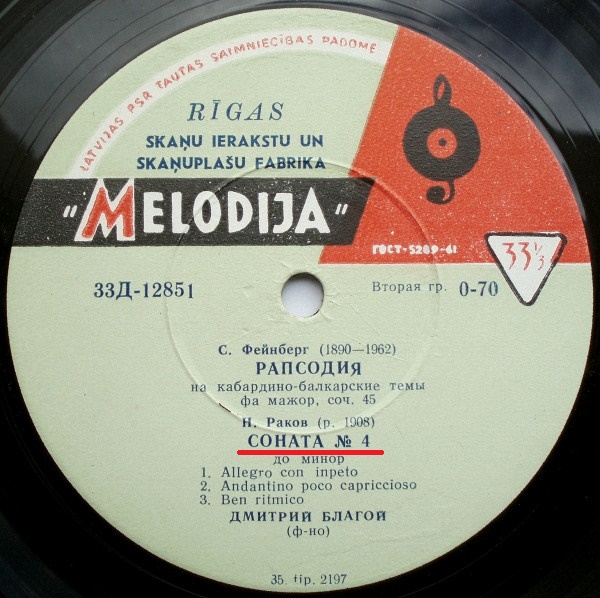
『Sonata No. 4』と記載されている…
|
大変 失礼いたしました....
[*4]
当該曲は調性はあるものの, 楽譜上 調号が置かれていないために実質的な調性を示している.
ラコフの作品は作中での転調が自由に行われるものの, 原則的に調性が明瞭なものがほとんどである.
ただし, 明らかに調性的な作品であっても調号を用いていない作品もある.
それはひとつにはミクソリディアやフリギアといった旋法的な性格の強い作品である時や,
展開のなかで複数の調を同格に扱いたい場合(← 複調という意味ではない)に用いられることが多いようにみえる.
(*cA01)
露語を英語に直した時の表記ゆれ, …というよりは ロシア語における"Nikolai"がフランス語では"Nicolas", ウクライナ語では"Mykola"にあたる人名であるといえる.
ある意味 意訳とも言えるし, 多言語でのラテン文字音写と考えてもよい. ちなみに姓の"Rakow"表記はドイツ語による.
(*cA02)
ロシア…というよりも旧ソ連諸国では道路に限らず偉人にちなんだ正式名称を残す建物・施設が多く見受けられる.
ソ連時代には都市の名前を指導者や偉人の名に基づいた名称に改名することが一度や二度ならずあった.
それらは"国の発展に尽くした功労者を顕彰する", という表向きの理由のほか, 政治的な意図も多分に孕んでいた.
あるときは当局の活動に沿った働きをした人物への叙勲であったり, 哀悼を示すものであったり, 或いは牽制や抹殺(=一度与えた名前を剥奪する)の象徴でもあった.
以下の論文は, ソビエト崩壊直後の1993年にロシアの都市地理学者 パーヴェル・イリーインが著したもので,
「偉大なるソビエトの名称変更ゲーム」(皮肉)に言及している貴重な資料である.
興味がある方は読んでみると面白いかもしれません.
参考: 『偉人にちなんだ(旧)ソビエト諸都市の改称』(1993, 訳 1995) 著: パーヴェル・イリーイン, 訳: 山田 晴通 -->
旧ソ連各地にある音楽学校や音楽院も正式名称では功績・功労のある音楽家の名前を冠していることが多々あり,
有名なところで言えばモスクワ音楽院 - 正式名称:チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院などがある.
これらの音楽家のエポニム的名称は自身の出身校や出身地にちなんだ命名がほとんどであるが, 凡そ 存命中に改名されることはない.
かくいうラコフ本人もカルーガ市内の音楽学校にその名前を掲げられている.
(*cA03)
ロシア革命以前の古い時代, 「ミハイロ=アルカンゲルスカヤ通り」, 「ニキツカヤ通り(*)」と呼ばれ,
1918年以降は革命通り, スターリン通りを経て最終的に1961年12月1日以降はレーニン通りと呼ばれるようになった.
ロシア革命前は通りの一部を「モスクワ通り」とも呼んでいた.
(*) 近くのニキータ正教会に由来, ニキータとはロシア正教会における紀元4世紀の大致命者 ニケタス・ザ・ゴスのこと.
(*cA04)
古い時代は「ミロノシツカヤ通り」と「テレニンスカヤ通り」の2つの部分に分かれていた. .
革命前は「サドヴァヤ通り(*)」もしくは「ヴォルシャヤ・サドヴァヤ通り」と呼ばれ, ロシア革命以後は「テアトルナヤ通り(*cA10とは別)」,
1930年代からは現在の「キーロフ通り」と呼ばれるようになった.
参考:Kirova St. (ロシア語) [101Hotels.com]
(*) サドヴァヤは「庭園」という意味でロシア各地にそれぞれの「サドヴァヤ通り」がある.
(*cA05)
1911年4月17日, ピョートルは妻 ナジェージダと連名で地域の人を新築完成祝賀会に招いている. .
招待状の文面は以下の通り.
1911年4月17日, モスクワ通り・サドヴァヤ通りの角に竣工しました住居 兼 商店の落成祝賀会を行います.
パンと塩(*cA06))を用意しております. 竣工式は午後2時より行いますのでそれまでにご着席ください.
ピョートル・ステパノヴィチ&ナジェージダ・ヴァシリェヴナ ラコフ
祝賀会に出席した客人はケーキやペイストリー(タルトなどの小麦粉のお菓子)をたくさん振舞われたようである.
これは妻 ナジェージダの実家 サヴェリン家が小麦を含む大規模な穀倉商人であったことが関係している.
(*cA06)
スラヴ諸国における訪問客を歓迎する習慣.
ロシア語には『Хлеб всему голова (パンは万物の源)』という諺があり, これはちょうど英語の『Bread is the staff of life. (パンは命の糧)』という言葉にあたる.
これらは聖書に由来し, スラヴ文化圏ではとりわけパンは聖なるものとして考えられてきた.
また, 塩は中世に至るまでかなり貴重で高価なものであり, 特別なものの象徴であった.
これら富と健康の標である "パンと塩" を振舞うという行為は, 客人を最大限にもてなすロシア人の気質に結び付き, 文化として根付いてきた.
現在でも結婚式や伝統行事などで見られる風習となっている.
参考:パンと塩 (ロシア語) [Wikipedia.ru]
参考:なぜロシア人はパンと塩でもてなすのか? (日本語) [RUSSIA BEYOND]
(*cA07)
.
参考:sa (ロシア語) [Wikipedia.ru]
(*cA08)
フョードル・プーシキン(Fyodor Alexseevich Pushkin, 1752-1810)
フョードルが実際にカルーガの副県知事であったのは1798年~1800年の間である.
作家 アレクセイ・プーシキン(Alexei Mikhailovich Pushkin, 1771-1825)は
フョードルの兄 ミハイル(Mikhail Alexeevich Pushkin, 1749-1793)の息子であり, フョードルからは甥っ子にあたる.
この邸宅にも何度か遊びに来ていたらしい.
プーシキン家は10世紀まで遡ることのできるかなり古いロシアの貴族の血を引く家系.
プーシキン家で最も有名な詩人 アレクサンドル・プーシキン(Alexander Sergeevich Pushkin, 1799-1837)は彼らと同世代であるが,
どういった関係があるかは今のところ不明である.
(ただし, 遠い血縁関係はあると思われる)
(*cA09)
実際には19世紀末頃に建物付きの土地を取得し, 1901年頃には邸宅の建設計画を立て, 1908年になって建設を始めた, …というのが正しい経緯のようだ.
1908年はニコライの誕生年であるが, 1901年はラコフのすぐ上のきょうだいである三女 ソフィヤの誕生年となっている.
以下は推測であるが, 「オブルプスカヤ通り」は後述するとおり, 1924年頃~1961年の間 「レーニン通り」
と呼ばれていたことから, 20世紀中ごろまではカルーガ市における街の中心部であったと思われる.
また, この通りは歴史が古いため, 現在の行政区画(番地)が古い時代の名残であると考えると,
ラコフ家旧宅のあった1区画(9番地)はそれほど 広いとは言えない.
当時の自宅と彼らが運営していた商店が同じ場所にあったかは定かではないが, (たとえ別であったとしても)
1901年以前にすでに3人の子どもがいた一家にとってこの家は些か手狭となりつつあったことは想像に難くない.
4人目の子が生まれた1901年にいよいよ新しい居宅を考え始め,
5人目のニコライが生まれる頃には住居と店先を兼ねてしまおうと計画を改め,
1911年, 3年越しの住居 兼 店舗の立派な建物を構えるのに至った……と思われる. いや, ただの妄想ですけどね…
(*cA10)
18世紀には地図に登場し, 当時は「オブルプスカヤ通り」や「オブルパ通り」と呼ばれていた.
この語は「町中の酔っ払いが一ヶ所に会する郊外の居酒屋」という意味がある.
その名の通り, この通りには多くの居酒屋や売春宿, 農場などがあった.
そのため ほかの地域に比して殺人, 強盗, その他もろもろの犯罪が起きやすく,
1912年に愛国戦争100周年を記念して「クトゥゾフスカヤ通り」と改められたのちも犯罪が絶えなかった.
19世紀後半にホテルが建設され, 1969年までは市内唯一の施設であったため様々な著名人がこの通りに滞在した.
(おそらく1924年頃 哀悼の意を込めて)「レーニン通り(*cA03とは別)」と改名され, 1961年まではその名で呼ばれていた.
通りにカルーガ演劇場などの劇場が開かれると, それ以来この通りは「テアトルナヤ通り」と呼ばれるようになった.
テアトルナヤはロシア語で「演劇の・劇場の」といった意味を持つ.
2009年, 通りの始点数百メートルを歩行者専用道路として再整備し, 以降改善が為されている.
参考:Teatral'naya St. (ロシア語) [101Hotels.com]
(*cA11)
テアトルナヤ通り9番地.
現在, ラコフ家の旧宅は取り壊され, この場所には旅行代理店「Сомбреро(ソンブレロ)」が入っている.
ソンブレロとはスペインやメキシコなどで用いられている, 鍔が広く中央部が高い帽子のこと. (社章?になっている)
参考:Sombrero []
参考:テアトルナヤ通り9番地 [Google Map]
(*cA12)
2011年4月8日公開. カルーガ市テアトルナヤ通り9番地付近の路地にあるブロンズ彫刻像. 彫刻家 スヴェトラーナ・ファルニーヴァ製作.
コンスタンティン・ツィオルコフスキー(1857-1935)はロシアのロケット研究第一人者であり, 人工衛星や宇宙船に言及したり,
多段式ロケットや軌道エレベーターを考案するなど「宇宙旅行の父」とも呼ばれる宇宙工学の偉人である.
最晩年を含む生涯の多くをカルーガで過ごし, また自転車が好きだったツィオルコフスキー.
展示されている像は囲いがあるわけではなく, 触れたり自転車のペダルを踏んでみたりサドルに座ることができるようだ.
参考: 自転車を引くツィオルコフスキーの彫刻像 (ロシア語) [KALUGARESORT.RU]
参考: バーミャトニク・ツィオルコフスコム [Google Map]
(*cA13)
ヴァシリ・ヴィノグラドフ(Vasiliy Dmitrievich Vinogradov)は19世紀末~20世紀前半にかけて活躍した建築家.
まわりの自然や先に存在した構造物を意識した, 周囲の景観に配慮した建築スタイルを得意とする.
カルーガ市内にはいくつか彼が手掛けた建築物が残っている.
参考:vinogradov //ヴィノグラドフの家(1908)
(*cA14)
Ракушкаは"貝殻"を意味する『Раковина』の愛称形である.
これは言うまでもなくラコフ(Раков)と掛けた言葉遊びである.
ちなみに"раковина"は"рака"(棺)という単語から作られた語.
以下, 余談ではあるが…
①ракушкаは"貝殻"から転じて(俗語表現ではあるが)「移動式の金属製ガレージ(のような設備)」を指すこともある.
これは外観形状が外部からの攻撃や衝撃に耐えるためのシェルターのようなものであると考えれば納得できます.
ロシアでは車を管理・保管するためのガレージの設置に関して, 場所や申請などが法律上 厳格に定められており,
機能面に優れる反面 高価であることが多いこと(正規ガレージの価格はракушкаの12~17倍にあたる),
都市部では家とは別にガレージを申請する土地が不足していること, などといった理由により,
ガレージの保有が思うようにいかない層が一定数居るという事実があります.
1991年以降, 法律の穴をつく形でおもに都市部で普及したのがこの"ракушка"という形態でした.
法律上はカーポート(日除け)と同格であったため 設置場所に関する制限を受けず,
土地を新たに取得したくない(取得できない)人たちはこぞって庭に設置することが多かったようです.
2006年以後, 当局は違法性のあるракушкаの強制撤去を始めましたが, 反発も少なからずあるようです.
…なんだこの脱線は.
②複数形 ракушки にはパスタの一種である「コンキリエ」の意味もある.
見たまま通りの「貝殻状になったパスタ」のことで日本でもよく見かけるタイプのもの.
そもそもイタリア語のコンキリエ(conchiglie)が「貝殻」を意味する語の複数形で, これが基になっています.
単数形はコンキリア(conchiglia), 大きいものはコンキリオーニ(conchiglioni), 小さいものはコンキリエッテ(conchigliette).
自分はコンキリエッテの方をよく使いますね. …なんだこの脱線は.
③раковина は手や顔を洗うために設置される「蛇口のついたボウル型の取付洗面器(洗面台)」の意味もある.
…なんでこんなこと書いてるんだろう自分..
(*c1)
オーケストラ作品『英雄行進曲』(1942)と吹奏楽作品『英雄行進曲』(1943)は編成を変えた同じ曲である可能性が高い.
こういった編成を変えた楽曲の使い回s 再利用はラコフ作品に, ままある.
(*c2)
オーケストラ作品『演奏会用ワルツ』(1946)とピアノ作品『演奏会用ワルツ』(1968)は同じ曲である.
オーケストラ用の自作を, 後年 ピアノ編曲して発表したようだ.
(*c3)
作曲者の知名度の割に, 日本では高校生を対象とする弦楽講習の際に課題曲として採用されたことがある. (2011年度)
学習途上の青少年を対象にした交響曲第2番(1957)と引き続いて作曲されている.
(*c4)
本作(1958)の第4楽章は, 後年のピアノ作品集『演奏会用練習曲』第2集(出版: 1969)収録の第9番練習曲と同じ曲である.
恐らく, シンフォニエッタのスケッチ(大譜表)をピアノ曲に仕上げたものだと推測される.
実際, 練習曲の方にはシンフォニエッタにはないピアノ的装飾音やパッセージが付加されている.
シンフォニエッタからピアノ編曲されたものはこの楽章のみであるが, どういう経緯でこれが選ばれたのかはよくわかっていない.
(*c5)
弦楽オーケストラのための作品『夏の日々(1969)』第3楽章「たくましい行進曲」と
ジャズオーケストラのための作品『競技行進曲(1949)』の原題はともに『"Спортивный"』.
この語は「Athletic(活発で元気な・運動競技用の)」「sports(スポーツの・運動用の)」「sporting(スポーツ好きな・公正な・勝ち目が平等な)」
…といった意味合いだが, 訳を与えるのは少々 難しい.
肝心の楽曲の関連性について, ジャズオーケストラ作品の方の曲の詳細がわからないので旋律が流用されているかどうかは断言できない.
(もし同じ旋律であったとしたら, 年代的にジャズオーケストラ作品を弦楽オーケストラ作品の方に流用したことになるが…)
[追記 (19/09/24)]
弦楽オーケストラのための『夏の日々』の音源とジャズオーケストラのための『競技行進曲』の楽譜を比較した際,
同じ旋律や和声を流用した作品ではなさそうである. 他のタイトルが似ている作品群とは異なり, 作曲年に20年の開きがあることからも
この曲に関しては恐らくそれが正しい(=別の曲である)のだと思われる.
(*c6)
オーケストラ作品『2つのワルツ(1973)』内の「瞑想的なワルツ」とドムラ作品『4つの小品(1973)』第4番「瞑想的なワルツ」は同じ曲である可能性が高い.
作品に対する直接の論拠はどちらに対しても充分な資料がないため出来ないが, 作品タイトル・作曲年が同じである.
特に, 彼のドムラ作品は他の編成に対して書かれた作品由来のものが多いのも事実であり,
ヴァイオリン作品『ヴァイオリン・ソナチネ第3番』とバヤン作品『三部作』の例は同じパターンであると言える.
(c31)も参照されたい.
(*c7)
この作品はラコフの出世作にして代表作. 発表二年後, この作品の成功によって「ソ連人民芸術家賞」の栄誉を手にする.
金管楽器がバリバリと炸裂するいかにもなソ連音楽に心が躍る一方で,
ソロパートは幾分技巧的に書かれヴァイオリニストだった彼の面目躍如といったところ.
ただし, 録音のバリエーションが幾つか残されているものの, 彼自身がソロパートを演奏した形跡はない.
(*c8)
正確に言うと, この曲はニ長調で始まり, 最終的にニ短調に終わる, という構成である.
(ラコフに限らず 短調曲が長調に転調して終わる曲は多いが, 本作のようにその逆を示す例は極端に少ない. )
2つのヴァイオリン協奏曲の間に書かれた作品で, 技巧的には中級学習者程度を要する.
(*c9)
クラリネットとオーケストラのための『幻想協奏曲(1968)』とドムラ(ロシアの民族弦楽器(c36))とピアノのための『幻想曲(1969)』は同じ曲である.
1967年作曲『ドムラソナタ』を皮切りにラコフはこの楽器に対する可能性を模索していた.
協奏曲の前奏部分や作品の幾つかのフレーズを省略する形でその翌年にドムラ編曲されたのが『幻想曲』である.
[追記 (19/09/24)]
1967年作曲のバヤンのための『幻想曲』も同じ曲である可能性が高い.
その場合, 記された作曲年から
バヤンのための『幻想曲(1967)』 → クラリネットとオーケストラのための『幻想協奏曲(1968)』 → ドムラとピアノのための『幻想曲(1969)』
という流れで作られた, ということになる.
[追記 (19/12/12)]
調査の結果, バヤンのための『幻想曲』はクラリネットやドムラに関する幻想曲群とは無関係の作品だと判明しました.
クラリネットの『幻想協奏曲』やドムラの『幻想曲』はト短調のAndante,
バヤンの『幻想曲』はニ短調のAndanteで曲想やメロディは異なる.
クラリネット・ドムラの『幻想曲』は臨時記号による転調を除けばト短調→ハ長調→ト短調という推移がある一方で,
バヤンのための『幻想曲』ではニ短調→変ニ長調→ホ長調→ト長調→変ロ長調→ニ短調→ニ長調, と
楽譜にして12ページしかない割に調号を伴う転調を繰り返している.
(*c10)
協奏曲と銘打ってあるものの, ヴァイオリン協奏曲群と比して規模はかなり小さい. (小協奏曲と称したほうが適切である)
また, 伴奏部は"オーケストラの"と題しているものの, 実際は弦楽合奏形態(c34)で書かれている. (管楽器は出てこない)
いずれも単一楽章であり, 演奏時間が6分~10分程度. 快速なテンポで奏されるが明らかに学習課程を意識して書かれている.
ちなみに, 1971年に第1番・第2番の伴奏部分をピアノに置き換えた2台ピアノ版『2つのピアノ協奏曲』が, 1978年には同様に『ピアノ協奏曲全集』が出版されている.
(*c11)
吹奏楽作品にもジャズオーケストラ作品にも同名の『コンバット・マーチ』が出てくるが, 同じ曲である可能性が高い.
編成だけ変更して書き直したものだと考えられる. (c9), (c31) も参照.
(*c12)
ロシアにはバラライカ(c36b), ドムラ(c36), グースリ, バヤン(c35)などの民俗(民族)楽器が存在する.
楽器編成の中にそれらの楽器を織り交ぜたものを『ロシア民族楽器オーケストラ』と呼称する.
歴史的な流れを汲めば, 演奏家・作曲家であったヴァシリ・アンドレーエフ(Vasily Andreev, 1861-1918)が,
一 大衆楽器であったバラライカやドムラの音楽的可能性・芸術的価値を高め, 自国の楽器だけの楽団を構想し, 1896年 その設立に至った経緯がある.
19世紀後半, ロシアでは西洋からの音楽や楽器が広く流入し, その中で自分たちの民族性を改めて見つめなおす気概が生まれていただけに,
その流れは至極当然のことであるように思われる. 国民楽派の台頭もそのうちのひとつであろう.
ラコフ自身の民俗楽器との係わり合いははっきりしたことがわからないものの, オーケストラ編成にとどまらず
個々の楽器のための作品を残していることから, 楽器の持つ可能性を信じていたことは伺える.
情報源に乏しく, それらの演奏や作品に触れることは難しいが, 同世代の作曲家が残した作品から雰囲気を推し量ることはできる.
たとえば, ヴァシフ・アディゴーザル(Vasif Adigozal, 1935-2006)の『ピアノ協奏曲 第2番(1964)』などがある.
(*c13)
『プリャソヴァヤ』とは, ペルミ地方を流れる川の名前である.
参考: Плясовая
(*c14)
題の『ロシアン・ゲーム』は単に"ロシアの遊戯"を意味するもので, いわゆる「ロシアン・ルーレット」とは関係ない.
(*c15)
フォックストロットとは, 1914年頃に生まれたラグタイムから派生したダンス, または その音楽の様式を指す.
現在では社交ダンスの一スタイルとして扱われているが, 言葉の原義は馬の足並みの一種である.
1930年代以降 ロシア(ソ連)ではその中程度の速度とお茶目な伴奏形(リズム)が好まれたのか多くの作品がこの形式で作られている.
(ただし, フォックストロットとスロー・フォックストロット(スローフォックスとも言う)は 一括りに出来るほど近い形式とは言い切れない側面をもつ. )
参考: だれも書かなかったフォックストロットの謎
(*c16)
20世紀の作曲家は自身の作品に作品番号をつけてないスタイルも多く認められるが,
実際には付いているが知られていない場合もある. (ハチャトゥリアンやババジャニアンにも例がある. )
ラコフの作品のうち作品番号が確認できるものは, 今のところ本作だけである.
[追記 (21/08/02)]
ピアノのための『2つの練習曲(1929)』を作品2, 管弦楽のための『マリ風組曲(1931)』を作品7
とする資料もあるにはありますが, 根拠に乏しいためここに記すにとどめます.
[追記 (21/8/14)&(21/8/20)]
『踊り 作品1』『2つの練習曲 作品2』に関しては当時そういう出版があったことを確認しました.
したがって, 作品1と作品2と作品6に関しては, 上記の表のとおり 間違いなくその対応であったと断言できそうです.
[追記 (21/9/5)]
ベラルーシの図書館に所蔵されている書籍検索によると, ラコフの初期作品に作品番号が付いているものは以下の対応となるようです.
| 作品番号 | 出版年 | 編 成 | タ イ ト ル | 作曲年 |
| 1 | 1930 | ピアノ | 踊り | 1929 |
| 2 | 1930 | ピアノ | 2つの練習曲 | 1929 |
| 3 | 1930 | | | |
| 4 | 1936 | 管弦楽 | スケルツォ | 1930 |
| 5 | 1932 | 吹奏楽 | カザフスタン民謡の主題による間奏曲 | 1931 |
| 6 | 1933 | ピアノ | 4つの前奏曲 | 1930 |
| 7 | 1933 | 管弦楽 | マリ風組曲 | 19xx |
| 8 | 1938 | 管弦楽 | 舞踏組曲 | 19xx |
| 9 | 1938 | 吹奏楽 | 組曲 第1番 | 19xx |
(*c17)
小品集である『10のノヴェレッテ(1937)』『水彩画(9つの小品, 1946)』の両作品のタイトルは, 全体を指標するものではなく
曲集中の一曲に付けられた個別の楽曲タイトルを表している.
ラコフ本人の意図はわからないが, 代表曲扱いのつもりでそういう名づけ方をした可能性がある.
『トランペットとピアノのための組曲(1957)』は, 現在では『4つのユーモレスク(4 Humoresken)』という題で通用している.
これも同じく曲集中の第4番「ユーモレスク」を代表する形でこの名前が取られているのだが, これに関しては前述の2作品と事情が異なる.
1989年10月録音, 1996年にリリースされた名トランペット奏者 チモフェイ・ドクシチェルのアルバム『Scherzo Virtuoso』にこの曲集のうち第4番が収録され,
その縁で後に曲集そのものがドクシチェル・エディション(※)として楽譜が刊行(いわば再出版)されるに至った.
その際, 彼が録音を行った第4番のタイトルにちなんで本作は『4つのユーモレスク』と名づけられ(再命名?され)たようだ.
(※…ただし, ドクシチェルは他の3曲の録音を遺していない)
(*c18)
(*c19)
ピアノ作品集『10のノヴェレッテ(1937)』第6曲「ワルツ(嬰へ短調)」と
ヴァイオリンとピアノのための『12の平易な曲集(b.1988)』第6曲「ワルツ(嬰へ短調)」は同じ曲である.
(*c20)
ピアノ作品集『10のノヴェレッテ(1937)』第9曲「マズルカ(ロ短調)」と
ヴァイオリンとピアノのための『12の平易な曲集(b.1988)』第8曲「マズルカ(ロ短調)」は同じ曲である.
(*c21)
ピアノ作品集『10のノヴェレッテ(1937)』第10曲「タランテラ(イ長調)」と
ヴァイオリンとピアノのための『12の平易な曲集(b.1988)』第7曲「タランテラ(イ長調)」は同じ曲である.
(*c22)
ここで言う「古典」は組曲形式が古典的というわけではなく, 個々の楽曲形式が古典的という使われ方である.
事実この組曲は調性が統一されておらず, 近代組曲の括りで作られた古典的形式曲集という意味合いである.
(*c23)
ピアノ作品集『ロシア民謡に基づく8つの小品 (1949)』第3曲「ワルツ(ホ短調)」と
ヴァイオリンとピアノのための『12の平易な曲集(b.1988)』第9曲「思い出(ホ短調)」は同じ曲である.
(*c24)
ピアノ作品集『少年時代(1951)』第4曲「喜劇()」と
ヴァイオリンとピアノのための『12の平易な曲集(b.1988)』第5曲「陽気な遊び(イ長調)」は同じ曲である.
(*c25)
ピオネール(пионер)とは, ソ連時代の言葉で「16歳以下で構成された少年・少女共産主義団員」を指す. (ボーイスカウトのようなものである)
英訳語"Pioneer"の第一義「パイオニア・先駆者」という意味ではないので注意が必要.
参考: ピオネール
(*c26)
二集に分けられて出版されたこの10の練習曲集は, 第1巻と第2巻で収録された作品の性格が大きく異なる.
先に出版された第1巻の5曲は, 特定の技巧の練習曲を目的としておらず, 芸術性に重点が置かれている.
後発の第2巻は, 特定の技巧に固執したチェルニー的な練習曲(第6番・第8番)と, 歌心を感じさせる曲(第7番・第9番)と,
第1巻然とした芸術性の高い第10番で構成され, 一貫性が薄いのが特徴である.
このうち練習曲第9番の原曲は自作のシンフォニー(1958)から取られている. 詳しくは (c4) を参照.
また, 1929年以降に作曲された練習曲作品を『20の演奏会用練習曲』とする文献も存在するが, それは彼の作品に於いて練習曲と題されたものの合算である.
うち, 17作品については以下のものを指していると考えられる.
・『2つの練習曲』 (1929)
・『10の演奏会用練習曲』 (1969)
・『4つの小品』 (1973) より 第4番「練習曲(オクターブ)」
・『4つの練習曲』 (1974)
(*c27)
(*c28)
『ピアノソナタ 第2番(1973)』は第"2"番とナンバリングされているが,
『ピアノソナタ 第1番(1959)』と同時期に作られた『古典形式によるソナタ(1959)』をピアノソナタと捉えるなら,
本作は事実上 3番目のピアノソナタということになる.
[追記 (21/08/03)]
『ピアノソナタ 第1番』と『古典形式によるソナタ』は同一楽曲でした. ([*2] 参照)
したがって, 『ピアノソナタ 第2番』はそのまま第2番です.
加えて, ラコフ作曲のピアノソナタは4作品(第4番まで)ある , というような記述は
おそらく間違いであるということを付記しておきます. ([*3] 参照)
(*c29)
1943年作曲『ロマンス』は複数の編成のための編曲が存在する.
ヴァイオリンとピアノのための『ロマンス(ト長調, 1943)』, チェロとピアノのための『ロマンス(ヘ長調, 1943)』は同じ曲である.
さらに, コントラバスとピアノのための『ロマンス(ヘ長調, 1943)』も同じ曲である.
楽器の特性・音域に合わせて調性は変更されている.
(*c30)
1946年作曲『ヴォカリーズ』は複数の編成のための編曲が存在する.
① ヴァイオリンとピアノのための『ヴォカリーズ(ロ短調, 1946)』
② ヴァイオリンとピアノのための『12の平易な小品(出版: 1988)』第10曲「ヴォカリーズ(ロ短調)」
③ クラリネットとピアノのための『ヴォカリーズとロシアの歌(1946)』より「ヴォカリーズ(ト短調)」
④ ファゴットとピアノのための『ヴォカリーズ(1946, イ短調)』
⑤ ホルンとピアノのための『ヴォカリーズ(1946, ロ短調)』
⑥ 声楽(ソプラノ?)とピアノのための『ヴォカリーズ(1946, 変イ短調)』
これらの曲はすべて同じ曲である. 彼の作品中 もっとも多くのバージョンが存在する楽曲であり, 彼のお気に入りだったのかもしれない.
また, 彼が直接かかわったものでないかもしれないが, 「オーボエ用」「アルト・サックス用」「チューバ(恐らくF管)用」の編曲も存在する.
なお, 後年作曲の
・トランペットとピアノのための『ヴォカリーズと間奏曲(1968)』より「ヴォカリーズ」
・パン・フルートとピアノのための『ヴォカリーズ(1950?, ト長調)』
・声楽作品『10のヴォカリーズ(1950)』
とは関連がない(…と思われる).
※ちなみに, パン・フルートとピアノのための『ヴォカリーズ』は声楽作品『10のヴォカリーズ』第7番と同じ曲である.
(*c31)
『ヴァイオリン・ソナチネ 第3番(三部作)』と同年出版のドムラ(c36)とピアノのための『3つの小品』は同じ内容である.
[c9]と異なり, こちらはヴァイオリンパートにほとんど手を加えずパート名だけを置き換えているに過ぎない. …それって手ぬk
[追記 (14/12/19)]
実際の事情としては, (ドムラとピアノのための)『3つの小品』の方が先に構想され, 後から『三部作』にヴァイオリン編曲された…というのが正しいようだ.
1949年頃からラコフは通常の西洋音楽では用いない, ロシアの民族楽器やその音楽に興味を向け始めていたのだが,
1960年代になるとそれらをソロ楽器として扱う方向に手を広げてきている. (最初はバヤンに手を出している)
そういう流れの中で, 彼がドムラのための『3つの小品』の作曲に至ったことは想像に難くない.
一方で, 残されたドムラ作品に共通するのは"技巧をを凝らした演奏会用の作品ではなく, どちらかといえば教育・学習用を想定した難易度"である点が認められる.
ラコフの専門はアカデミックな立場でいえば楽器法であったが, その頃の彼が力を入れていたもうひとつの重要な仕事は青少年のための初等音楽教育だった.
そのため, 音楽教室で生徒たちが楽しく易しく自国が誇る民族楽器に触れられる場を作品を通して提供していた面があったのではないかと思われる.
話を元に戻すと, いずれも1968年作曲であるが, ドムラの『3つの小品』は1969年に, ヴァイオリンの『三部作』は1970年に出版されているため,
ドムラ → ヴァイオリン という流用過程があったと考えるのが自然である.
もっとも, 彼がドムラとヴァイオリン双方の楽器に共通したメロディを勘案して, たまたまドムラ作品のほうが1年早く出版されただけである可能性は否定できないが….
余談だが, この作品はラコフ自身による録音が残されている. (ただしラコフはヴァイオリンではなくピアノ伴奏をしている)
当然のことながら, 録音シーンの前線に立つ演奏者はドムラ奏者よりヴァイオリニストのほうが多く, その方が一般的なスタイルであり,
楽器の特性や音域を考慮した上で, 互換性がある(と考えてもよい)ヴァイオリンを使わない手はない.
そういう意味でヴァイオリン版の『三部作』が出来上がった可能性も示唆しておく.
このヴァイオリン版の『三部作』は『ヴァイオリン・ソナチネ 第3番』のサブタイトルのようなものであるが,
実際, 1~3楽章のいずれをとってもソナタ形式 (或いはソナチネ形式)で書かれた楽章は存在しない.
(元となった『3つの小品』はソナタ形式を念頭に置いて作られたものではなかったので当たり前ではある)
…それならばなおさら『3つの小品』をわざわざ『ソナチネ』に変更して発表する明確な理由はなく, 正直理解に窮するところを否定できない…のもまた事実である.
[ 譜 例 表 示 ]
| Sonatina No.3 for violin and piano |
3 Pieces for domra and piano |
|---|
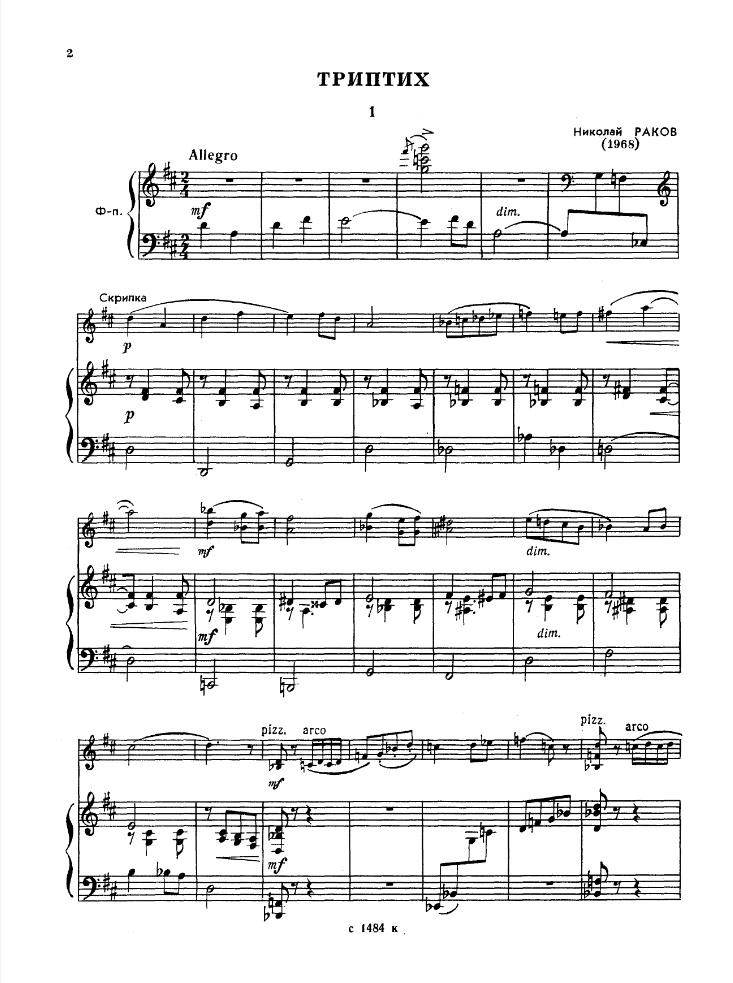
1st mvt. |
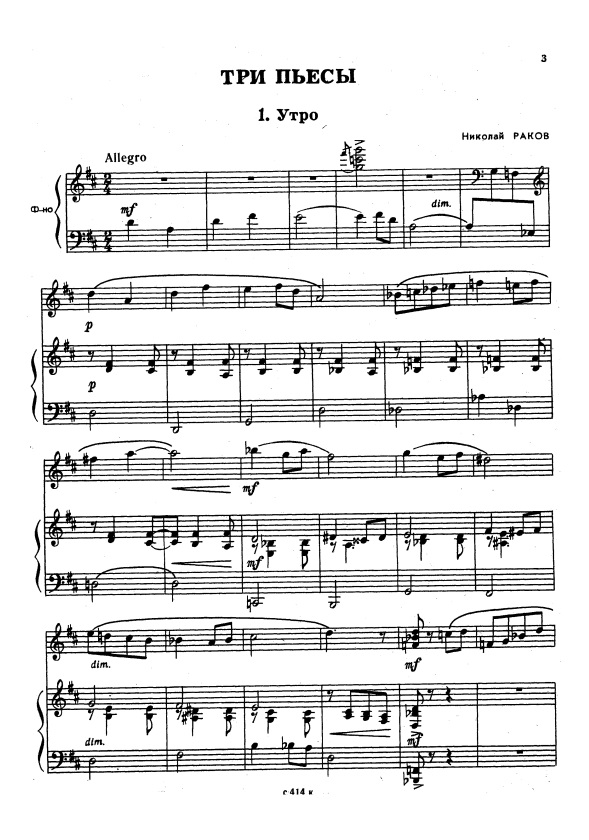
I. Morning |

2nd mvt. |

II. |

3rd mvt. |

III. |
(*c32)
アカデミックな教育家としてのラコフの専門分野は楽器法(管弦楽法)であったが,
一方で, 幼児音楽教育に注力していた面もあった.
[ 写 真 表 示 ]
この曲集に収録された楽曲の半数は, 過去に別作品に収録されたものをヴァイオリン編曲する形で存在している.
なお, 第10曲「ヴォカリーズ」に関しては, 原曲に当たる『ヴォカリーズ(1946)』自体がvn&pf編成であるため, 編曲されてはおらず
要するに再録という形になっている.
(*c33)
(*c34)
ヴァイオリニストだったことが影響してか, ラコフは合奏形態の中で特に弦楽合奏を好んでいた.
『小交響曲』『交響曲第3番』『夏の日々』をはじめとした中後期の代表曲や4つある『ピアノ協奏曲』(の伴奏部)はすべて弦楽合奏のための作品である.
さらにチェロのみ複数台で構成するいわば"チェロ合奏"がお気に入りだったようで, この項目で分類されているものはその編成の楽曲ばかりである.
youtubeにあげられた実演動画を見てみると, 一瞬 異様な光景に思えるものの, 柔らかで力強いアンサンブルの妙に彼が惹きこまれたのもわかるような気がしてくる.
(*c35)
(*c36)
12世紀にモンゴルから現在のウクライナやベラルーシあたりに持ち込まれたと伝えられる弦楽器.
3~4本のスチール弦と円型(半球形)の共鳴板が特徴的だが, この形は1896年に先述のヴァシリ・アンドレーエフが施した改良が元になっていると言われ,
1648年頃を境に当時のドムラは徹底的に駆逐されているため, 伝来当初の形について現在はっきりとしたことはわかっていない.
現在は, 3弦ドムラと4弦ドムラが用いられ, 高い方から1弦, 2弦, 3弦, (4弦)と呼ばれる.
ただし調弦が異なり, 3弦ドムラはd2-a1-e1と4度調弦なのに対し, 4弦ドムラはe2-a1-d1-gの5度調弦で扱われる.
音高がソロ向きということもあり, バラライカオーケストラやロシア民族楽器オーケストラではメロディを担当することが多い.
一方で, ロシアの民族弦楽器として名高いバラライカの起源は17世紀の終わりごろにアジア方面から伝来した二弦楽器と考えられている.
3本の弦(ナイロン弦2本と金属弦)を携えた三角胴の共鳴板をもつ現在の形は1883年になって上述のアンドレーエフとその仲間であるV.イワノフ・F.パセルフスコム・S.ナリモフの手によって改良されている.
ドムラ以上に幅広い開発・拡張が行われており, 現在は①ピッコロ②プリマ③セクンダ(セカンド・プリマと考えられる)④アルト⑤バス⑥コントラバス, と多彩な同族楽器が存在する.
そのためロシア民族音楽で活躍する場が広く, 独奏やバラライカ合奏, 果てはバラライカオーケストラ(ロシア民族楽器オーケストラ)まで組織することがある.
高い方から1弦, 2弦, 3弦でその調弦は②プリマを中心とし, a1-e1-e1となり, 2弦と3弦を同じ音に合わせるといった特色がある.
④アルトは②プリマより1オクターブ低い楽器でa-e-eと調弦する場合とa-e-Hの4度調弦する場合がある.
③セクンダは②プリマの5度下の楽器でd1-a-aと調弦するが, 場合によってはd1-a-eの4度調弦を行う.
この4度調弦は低音楽器を補強する役割のときに行われ, 実際⑤バスは④アルトの1オクターブ下として, ⑥コントラバスは④アルトの2オクターブ下として
それぞれd-A-E, D-A1-E1で調弦される.
…バラライカの方に力を入れすぎている...
(*c37)
一般に『グレゴリオ聖歌における歌唱法および旋律の技法のひとつ』であり, 歌詞1音節に対して2~3或いはそれ以上の音高の素早い移動を伴った音符を装飾的に当てはめる様式を指す.
「メリスマ」という言葉はともかく, 技法としては西洋音楽に限らず広く一般化されており, ドイツ語圏のヨーデルやモンゴルのチンメゲレル, 日本のこぶしなどに同様の概念が散見される.
ただし, 本作は歌唱ではなくドムラ作品であるため, 「メリスマ」の語源となったギリシャ語本来の意味である「歌」や「旋律」に根差したタイトルであるかもしれない.
弦楽器であるドムラは歌心を表現しやすい楽器であると思われるが, 実際のところ曲を聴いてみなければこの辺りの真意は分かりかねるのが実情である.
[追記 (21/08/13)]
この曲の原題(ロシア語)は『Напев』.
英訳語としての第一義は確かに"melisma(メリスマ)"であるものの, 他にも
"canto(詩編, イタリア語で"歌"の意)", "air(アリア)", "tune(旋律, はっきりとした節回し)"
といった意味をもつ.
(*c38)
1930年作曲 "Myud (ミュード)" の意味は特定しづらい.
以下 3つのいずれかであると考えられるが, 副題が『ピオネール(c25)の行進』であることを踏まえると恐らく③が正しいと思われる.
①タタールスタン共和国に存在する自治体 参考: Myud の天気予報
②1931年開業の 十月鉄道 モスクワ地域部沿線上の鉄道待避施設 参考: МЮД (разъезд)
③1915-45年まで開催されていたロシア国内の進歩的な若者のための政治祝典. ワールドユースデー (国際青年デー)とは関連がない
参考: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ ・・・訳すなら「国際青年の日」. 頭文字を取るとМЮДとなる.
(*c39)
(*c40)
原題は『Ой, дуб, дуба』(ウクライナ語)
そもそもこの曲は作品『Українська народна пісня(ウクライナ民謡)』の第2番なのだが,
どうやらこの作品はウクライナ民謡をラコフが採譜し, 合唱曲用に編曲したものらしい.
第1番に関する詳細・演奏は一切出てこないが, 反面この第2番は人気のようで, いくつもの動画がヒットする. (上記関連動画参照)
ちなみに原曲(?)にあたる民謡とはメロディラインや和声進行が異なり, より歌いやすいように配慮されている. 参考: 原曲(?)
(*c41)
ロシア語の原題は『Солнце низенько』
"солнце"は直訳すると「太陽(sun)」であるが, 「太陽のような人」の意味合いで大事な人に対する呼びかけにも使われる. 参考: ロシア語 愛してる
"низенько"は「shorty(shortie)」, 幼い子供やかわいい女性に対して用いられる砕けた表現である.
[追記① (14/12/17)]
この曲の正式なタイトルは『Сонце низенько』(ウクライナ語)である.
ロシア語の"солнце"とウクライナ語の"сонце"はどちらも「太陽」を表す語であるが,
ウクライナ語の"низенько"は「(位置が)低い・低くなる」を表す言葉となり,
題の示すところは, とどのつまり「The Sun Set(日没) / The Sun is Low (陽は低く)」という意味合いになる.
[追記② (14/12/21)]
元となったウクライナ民謡は, ウクライナの作曲家 ミコラ・リセンコ(Mykola Vitaliyovich Lysenko, 1842-1912)による
ウクライナ語のオペラ『ナタルカ・ポルタフカ (1889)』の第3幕で歌われていたアリアである.
ラコフはそれをテノールとオーケストラ編成用に編曲し, 1943年LP録音している. (テノール: イワン・コズロフスキー)
ちなみに発表初期の頃, このオペラの登場人物のひとり ミコラ(Mykola)は, 作曲家 イーゴリ・ストラヴィンスキー(Igor Fyodorovich Stravinsky, 1882-1971)の父で
オペラ歌手であったフョードル・ストラヴィンスキー(Fyodor Ignatievich Stravinsky, 1843-1902)に演じられていた.
また, 元となったオペラの歌曲集はペトルッチ楽譜ライブラリー(Imslp)で誰でも参照することができる. [参考] Natalka-Poltava (この曲は PDFファイルの53~54ページに該当する)
(*c42)
ロシア語の原題は『Цвели, цвели цветики"』
これを発音すると, おおよそ [ツヴェーリ, ツヴェーリ, ツヴェチキ] のようになる.
語幹と語末の音(-i)で韻(頭韻・脚韻)を踏んでいるような格好になるが, ロシア語の派生語と文法規則に照らして, 敢えてこれを狙ったところがある(…かもしれない).
「цвели」は動詞「цвести (花が)咲く」の過去形,
「цветики」は名詞「цвет (花; bloom, flower, blossom)」に指小接尾辞(縮小辞)「-ик」がついた単語「цветик(小さい花)」の主格複数形である.
[追記 (14/12/17)]
この曲は『Два Українська народные песни (2つのウクライナ民謡)』の第1番にあたる.
(c40)同様, ラコフが一から作曲したわけではなく, 民謡を採譜・編曲した作品に相当する.
原曲は10小節(3+2+3+2)の節まわしを6回繰り返す単純なものであるのに対し, ラコフの編曲はABAの三部形式に仕上げるため,
中間部(B)にあたるメロディを創作している. その結果, 原曲の一部の詩と6番の歌詞を省略する点が大きく異なる.
(*c43)
ソ連の名ピアニスト: グリゴリー・ギンズブルク(Grigory Ginzburg, 1904-1961)が発表した編曲作品『ロシアの歌(Russian Song)』
本作はその原曲にあたる. 歌心を愛したギンズブルクの琴線に触れるものがあったのかもしれない.
(*c44)
ロシア語の原題は『Ничто в полюшке』
「полюшке」は名詞「поле (草原)」にに指小接尾辞(縮小辞)「-шк」がついて変化した単語「полюшко (野原)」の前置格.
余談だが, 日本でも有名なロシア民謡(軍歌)「Полюшко-поле(ポーリュシカ・ポーレ)」で使われている語でもある.
(*c45)
作詞者が異なるものの, 題が『(季節) + (時間帯)』の組み合わせで統一されている.
ある種のシリーズものと捉えても良いかもしれない.
(*c46)
ロシア語の原題は『Здравствуй, лен!』
…であるが, これは恐らく『Здравствуй, лень!』の誤植ではないか, …と推察される.
「лен」は「county(行政区)・feoff(領地)・fee(封土)」という意味(※下記)になり, 呼びかけ語である「Здравствуй(おはよう)」とつながらない.
「лень」は「laziness(怠惰・不精)・sloth(ものぐさ・怠け者)」という語である.
[追記 (21/08/02)]
ラコフの教え子のひとり エドゥアルド・アルテミィエフ (Eduard Nikolaevich Artcemyev, 1937- )の声楽作品にも
『Здравствуй, лень!』(作詞: ナターリヤ・コンチャロフスカヤ)という楽曲がある.
ラコフの楽曲とは作詞者が異なるので詞の内容もおそらく関連がないと思われるが
このことからも, やはり上述の通り「лен」ではなく「лень」が正しい…んじゃないかなぁ.
無理やり 「領土・領土権」→「領主さま」と曲解できなくはないですが…無理があるような気がします.
(※) 上記の意味では, おおよそ中世ロシアの時代に用いられた言葉の用法による.
① 家臣に与えられた財産(領地). またそれらを所有する権利のこと.
② ①のような不動産を有することに負う義務.
またそれらの意味の他に「linen (リンネン=亜麻)」を指すこともあるそうだ.
(*c47)
笳(あしぶえ)とは, 牧童などが使う葦(あし)の葉で出来た簡素な笛のことである.
(*c48)
モスクワ音楽院でのラコフの専門科目は楽器法(管弦楽法)であった.
1943年から教授として現場の教育に長く携わっていた.
声楽曲に於けるこの曲集の持つ意味は, (実物に触れていないのでわからないが)四声課題のようなものだろうか. (二声だけど)
◆最終更新日: 2022/02/16